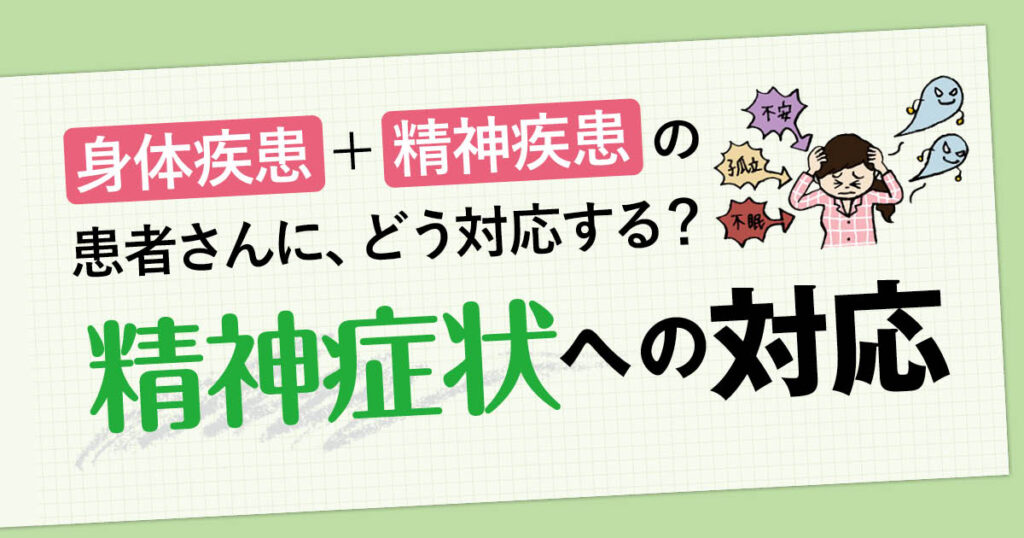精神疾患に処方される主な薬剤の1つが「抗うつ薬」。作用や気をつけたい副作用など、基礎知識を紹介します。
抗うつ薬は頭の中の停滞をかき混ぜて浮上させるイメージ
抗うつ薬はシナプスでのセロトニンにかかわって抗うつ作用をもたらすとされています。イメージは、頭の中の停滞をかき混ぜて浮上させる感じ。これにより、患者さんによってあせりが強くなることがありますし、妙にハイテンションになる“躁転”が起こることもあります。投与後はそういったことが起きないか注意が必要です。
また、かき混ぜることで渦運動となり、外部からの刺激を弾く働きもあります。例えば、不安を誘発する刺激を弾くことで、不安症の治療に用いられます。ただ、刺激を弾きすぎると“刺激に反応しない”ことになり、特に高用量を長期に用いていると抗うつ薬によるアパシー(無気力)という副作用につながる場合もあります。
一般病棟では、旧来の三環系*1や四環系*2はあまり使われないでしょうか。SSRI以降の新規抗うつ薬が多いと思います。種類は下記の通り。
主な新規抗うつ薬
SSRI
分類
Selective Serotonin Reuptake Inhibitor(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)
一般名(商品名)
●フルボキサミン(デプロメール、ルボックス)
●セルトラリン(ジェイゾロフト)
●パロキセチン(パキシル)
この記事は会員限定記事です。