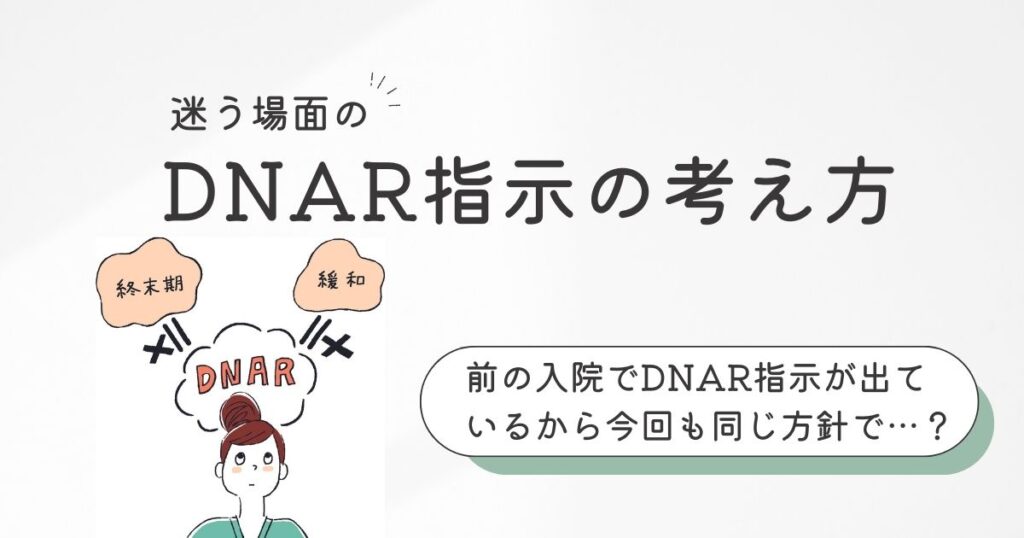DNAR指示について、よくある誤解を切り口にして解説。今回は「前の入院でDNAR指示が出ているから今回も同じ方針で…」という誤解です。
よくある誤解➂前の入院でDNAR指示が出ているから今回も同じ方針で…は間違い!
DNARの同意は撤回可能。一度同意があった後も検討を
皆さんの医療機関では、一度出されたDNAR指示は定期的に、または患者の病状や状況に応じて見直しが行われていますか?
日本集中治療医学会が2016年に実施した、蘇生不要指示に関する医師会員への調査1では、回答者の約8割が「見直している」と回答していますが、約2割は「見直していない」と回答しています。
日本集中治療医学会『DNAR指示の勧告』の第4項2で、「DNAR指示の妥当性を患者と医療・ケアチームが繰り返して話し合い評価すべきである」と明記されていることからも、DNAR指示については、患者の病状や状況、かかわる医療者の変化に応じて繰り返し検討し合意形成する必要があると考えます。
患者や家族の意向は、病状や生活状況の変化、どのように生きたいか、もしくはどのような最期を迎えたいかに関する気持ちに応じて当然揺れ動くものです。一度DNARに同意したとしてもそれは撤回することも可能であること、何度も繰り返し検討を重ねていくものであることを、患者や家族に説明し、その機会を保証することも大切です。
早い段階でのDNAR指示の注意点
『DNAR指示の勧告』の解説2にも書かれていますが、DNAR指示は患者が終末期に至る前の早い段階に出されていることもあります。疾病構造が変化し、複数疾患が併存していることも少なくないうえ、クリティカルな病状にある場合や侵襲を伴う治療を行う場合には、予期していない急な病状の変化を危惧することは急性期病院では避けては通れない問題です。
一方で、「認知症であること」や「緊急入院であること」「身寄りがないこと」「ADLが低いこと」「高齢者であること」だけで、病状の重症度にかかわらず、DNARが検討されている現状も明らかになっています(図1)3。このような状況で適切な医療が差し控えられることは、患者の医療を受ける権利をも奪ってしまう可能性があり、軽視できない重大な問題です。
この記事は会員限定記事です。