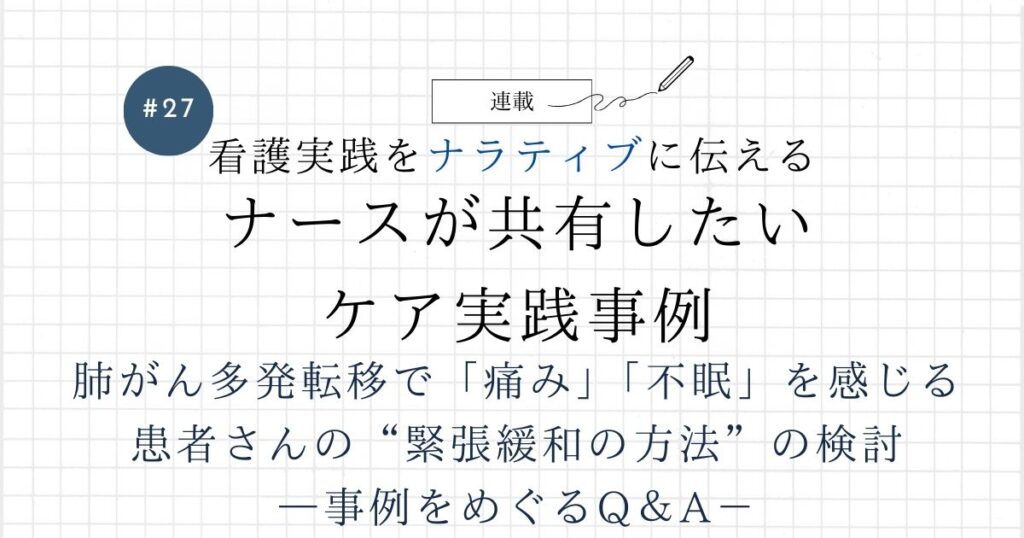事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は肺がん多発転移で「痛み」「不眠」を感じる患者さんの“緊張緩和の方法”の検討をめぐるQ&Aを紹介します。
今回の事例:【第26回】肺がん多発転移による痛みと不眠に苦しむ患者への緊張緩和ケア
〈目次〉
この事例を取り上げたのはなぜ?
Aさんの精神・心理状態をどう考えた?
リラクゼーションや、自己コントロール感を取り戻すためのケアの目的は?
Aさんがどう変化することが目標だった?
事例をめぐるQ&A
この事例を取り上げたのはなぜ?
大橋 瀬尾さんが、Aさんとのかかわりを今回、呈示された理由を教えてください。
瀬尾 Aさんは以前、入院中に適応障害の診断を受けた経過があり、また外来担当医や外来スタッフからの事前の情報では精神症状を疑わせる側面が多かったので、外来患者のこの1回の面談日で私が提供可能なことを、対話しながら検討し続けました。
当初は、精神科の専門医療につなぐことなど“今後の予想プラン”を思い描いていましたが、また違う経過がみえてケアをつなげることができたため、当日のかかわりについて検討してみたい事例だと考えました。
Aさんの精神・心理状態をどう考えた?
大橋 Aさんについては、「肺腫瘍の多発性骨転移(Stage Ⅳ)と聞いて落ち込み、変になった」「やる気が出ない」「うつではないか」「気が休まらない」「緊張」「痛みが原因の不眠」など、さまざまな心の状態についての表現がありました。
このような言葉があると、“抑うつ状態”“うつ病”などとすぐに判断したくなると思います。瀬尾さんは、Aさんの精神・心理的状態をどのような状態だと考えましたか?また、そのように考えた理由は何ですか?
瀬尾 「疼痛コントロール」が十分でないことによる「不眠」が続いたことにより、心身のエネルギーの低下から、生活活動においての意欲 ・ 能動性の低下、楽しみの減退が起こっており、「抑うつ気分」を呈した状態と判断しました。
また、この「痛み」「眠れない日々」の苦悩が共有されてこなかったことへの枯渇感、医師への両価感情(こんなに痛むことをわかってほしかったのに/これ以上伝えたら嫌われる、診てもらえなくなる、治療に対しての批判になるかも)によって表現を抑圧し、よって孤立感も伴っていた心理状態と思われました。
体験として困っていること、その際どういった感情が湧いていて何を考えたのかを具体的に聴き、共感する姿勢を提供したことで、身体や表情に少し良好な変化が起こったことから、「不眠」にしても「疼痛コントロール」にしても「抑うつ気分」にしても、薬物調整だけを検討するだけでは不十分であったと考えました。
この記事は会員限定記事です。