多職種連携に関連する悩みや疑問は、他職種に相談することで解決するかも!今回は、化学療法に伴う食思不振がある患者さんのメニューを再検討するケースについて。管理栄養士と言語聴覚士が解説します。
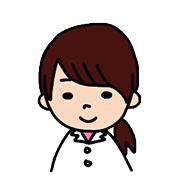
うめだうめだ
管理栄養士(RD)
管理栄養士、7年目。給食委託会社を経験して、現在は整形外科・内科で勤務。患者さん1人ひとりに合った栄養・食事のサポートを大切にしている。疾患や病態によって食事量が減少してしまった場合は、その方がどんなものであれば栄養補給ができるのか、患者さんの声を聞くことを大切にしている。

みややんみややん
言語聴覚士(ST)
言語聴覚士、12年目。急性期、回復期病院などを経験して、今は訪問STとして勤務。大切にしているのは傾聴と共感。「食事が進んでいない」というワードに敏感。とにかく口の中や食事場面をこっそりのぞいている。
●管理栄養士(Registered Dietitian)
病気の方や高齢で食事がとりづらくなっている方から、健康な方まで、1人ひとりに合わせて専門的な知識と技術をもって栄養指導や食事指導を行い、食から健康をサポートする。
●言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist)
リハビリテーション(リハ)スタッフの1つ。脳卒中の後遺症や神経難病によって会話や発音がうまくできない、摂食嚥下障害があるなどの困難に対してリハビリ、サポートを行う。
化学療法に伴う食思不振がある患者さん。栄養バランスに配慮しつつ、メニューを再検討したい!
泌尿器科で働いている看護師です。化学療法(抗がん剤治療)をしていると、悪心や浮腫によって、食事をとれなくなってしまったり、味を感じにくくなったりして食事量が減ってしまう患者さんが多いです。
まずはある程度のカロリーをとってほしいので、主食を麺類に変更したり、味の濃いものを勧めたりしていましたが、どうしても栄養が偏ってしまわないかが気になってしまいます。栄養のバランスも考えて、食事をとってもらえるような工夫はないでしょうか。
ナースが最初にできること、RDとSTに相談するとよいこと
食事が進まないとき、患者さんの「食」にかかわる部分がどんな状態か確認したり、メニューを変えたり、できることはいろいろあります。具体的にどうすればよいのか解説します。
「お口の中、のぞかせてください!」➡口腔内の乾燥などをチェックしよう
相談内容や患者さんの状態からすると、STが特別に介入すべき嚥下障害の可能性は低いですね。でも、「嚥下障害はないから、大丈夫ですよ」と言うだけでは、患者さんは困ったまま。
そんなときは、口の中をのぞいてみると、解決の糸口が見えることがあります。治療の影響で唾液が出づらく、口が乾燥しやすくなって味がわかりづらくなり、それによって食欲がわかないということがあるのです。意外と見落としがちな口の観察、まずはのぞいてみましょう!新しい発見があるかもしれません。
そして、専門的な口腔ケアが必要な場合は、歯科衛生士に相談してみましょう(乾燥ってどんな感じ? と思った方は、「口腔乾燥」「評価」などで検索してみてください)。
潤いのケアをしよう
続いて、口腔乾燥に対する実際のケアについてアドバイスをします。ナースもSTも、口腔ケアを行うことが多いですよね。ケア用品にはさまざまなものがありますが、スポンジブラシや口腔ジェルを使うことが多いでしょうか。
まず、スポンジブラシの水はギュッと絞って使うべし!
特に介助でケアをする場合、絞りが不十分だとスポンジに含んだ水が口腔内で溢れて、これがけっこう苦しいんです。一時的にでも嚥下機能が低下していると誤嚥につながる可能性もあり、注意が必要です。
そして、口腔ジェルはチューブ裏面の説明書きをよく読んで使うべし!
塗ったままでよいもの、「吐き出してください」と書いてあるものなど、じつは用法はものによってさまざま。自分の指で塗りづらい方は、少量のジェルを舌に乗せ、ぐるぐる口腔内に塗ってもらってもよいのではないでしょうか。
さらに、手軽に行える唾液腺マッサージをプラスしてみましょう(下記参照)1。即時効果が得られることも多く、患者さんにとっても効果を実感しやすいです。
①耳下腺マッサージ
人差し指から小指までの4本の指をほおに当て、上の奥歯のあたりを後ろから前へ向かって回す(10回)
②顎下腺マッサージ
親指を顎の骨の内側のやわらかい部分にあて耳の下から顎の下まで5か所くらいを順番に各5回ずつ押す
③舌下腺マッサージ
両手の親指をそろえ、顎の下から上にグーッと押す(5回)
(文献1より引用)
「おいしく楽しく食べる」「頻回食で少しずつ」がポイント!
食べたくない、食欲がないときは、頻回食で「食べたいもの」を「食べたいとき」に「おいしく楽しく食べる」ことを大切にしましょう。
栄養のバランスも考えて食事をとってもらいたいときは、主食・主菜・副菜ごとに食べられるものを考えます。
例えば主食は、一口大のおにぎりやサンドイッチにして、食べたいときにいつでも食べられる工夫をします。主菜はタンパク質を意識して、卵豆腐や茶碗蒸しなど、喉ごしがよく食べやすいものにしましょう。副菜は、ビタミン・ミネラル類の補給を意識して、野菜や果物・乳製品を用意してみます。
また、患者さんとの何気ない会話に、食事をおいしく楽しくするヒントがあることがあるので、ぜひ患者さんの声をRDに届けて、相談してみてください。
味覚の変化に合わせた食事で食事量アップ!
治療の影響で、味を感じる味蕾(みらい)細胞が減少したり、感覚が変化したりして味覚が変化することがあります。
甘味に敏感な場合、砂糖やみりんを使用せずに、塩やしょうゆ、味噌などを使って少し濃いめの味つけにしたり、酢やレモン、ゆずなどの酸味を利用しましょう。
また、汁物は食べられることが多いので、ぜひ勧めてみてください。塩やしょうゆの味が苦く感じる、金属のような味がしてしまう場合、塩味の使用を控えてだしを効かせる、ごまやゆずなどの香り、酢などをワンポイントに使うこともおすすめです。さまざまな調味料で風味をつけることで食べやすくなります。
味が感じられない場合、濃さを加減しながら、甘味・酸味・塩味と試みてください。食事が人肌の温度だと食べやすいこともあります。また、亜鉛欠乏の可能性もあるので、医師への相談、血液検査の依頼なども視野に入れましょう。
患者さん1人ひとりの状態に合わせた、ひと工夫で食事量アップにつなげることができます。ただ、こうした工夫すべてを現場ナースが対応するのは大変でしょう。家庭からの持ち込みの調整や、RDに食事の調整がどこまでできるか相談・対応を依頼するなど、お互いに協力しながらできればと思います。
- 1.日本歯科予防センターホームページ:自宅で出来る!口腔機能向上トレーニング.
http://www.shikayobou.com/training/(2024.8.6アクセス)
※この記事は『エキスパートナース』2021年6月号連載を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。






