老人ホームに入所し、訪問リハビリテーションで歩けない状態から居室内歩行自立まで回復するも、家族に帰宅を拒否され、無気力になってしまった例。多職種連携のポイント、退院支援の注意点などを解説します。
家族と意見がすれ違い、患者さんの希望の実現が難しいときはどうする?
●70歳代後半、男性
●慢性硬膜下血腫、アルツハイマー型認知症
●もともと妻と共に一軒家の自室で生活。
●要介護認定は要介護1で、1人では入浴が困難なため、デイケアを週2回利用していた。
●本人のがんこな性格と認知機能の低下から、たびたび妻とはもめることがあった。息子夫婦が隣町に住んでいる。
●自宅で下肢機能や認知機能の急激な悪化が見られ、病院を受診。過去の転倒によるものか、頭部打撲があり、慢性硬膜下血腫の診断を受け手術を受けた。
●その後、回復期リハビリテーション病棟へ転院しリハビリを実施。下肢機能が改善してくるも、車椅子は必要であり、家族の意向から老人ホームに入所のうえ訪問リハビリ希望となった。
●入居時、本人は「歩けるようになれば家に帰りたい」と、家族は「たまに外へ連れ出せるようになれば」と話しており、本人と家族の意向に差異が生じていた。
●老人ホームでは他のサービスとして、同敷地内のデイサービスを利用。本人はしっかりしている(と思い込んでいる)ため、集団でのレクリエーションなどは好きになれず、不参加になることも多かった。しかし、訪問リハビリには意欲的であった。
●入居時から、バイタルサインを管理しながら歩行訓練を中心に開始。リハビリ開始時は歩行器使用で20m程度の歩行能力だったが、次第に歩行距離を延ばし、介入から2か月程度で150m程度の連続歩行が可能となった。また、居室内もつたい歩きで自立となった。
●要介護認定の区分変更は申請中。
●本人も歩くことに自信がつき、「家に帰りたい。家も族と話し合いたい」と発言することが多くなった。しかし、妻の体調がすぐれないことを理由に面会の機会が減り、息子家族に相談するも後ろ向きな回答が多く、本人は不満を募らせていた。
●やっと面会できる機会があり、妻と直接話をしたが、妻は「家にはもう帰れない」と本人に告げ、本人は「妻に愛想を尽かされた。生きる意味がない」と生きる活力を失ってしまった。
●その後はリハビリにも消極的になり、「動いても帰れないから意味がない」とリハビリを拒否するようになった。引きこもり傾向が強くなり、認知症の症状も悪化。リハビリ拒否は続いた。
※事例は、メディッコメンバーの経験に基づいて設定した架空のものです。

鳥ボーイ
とりぼーい
お笑い芸人を経て看護師12年目。現在は急性期病院の集中治療室で、たくさんのシリンジポンプと戦っている。

バサカ
ばさか
作業療法士(OT)、7年目。大学院に通学しており、多職種でのディスカッションの機会も多い。

かなこ
かなこ
看護師11年目。内科病棟を経て、現在は手術室での勤務。

たみお
たみお
理学療法士(PT)、11年目。慢性期病院で入院患者のリハビリテーションと、訪問リハビリテーションを担当している。
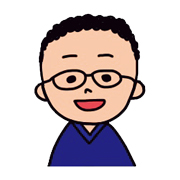
おぬ
おぬ
看護師10年目。脳外科、回復期、在宅を経験し、現在は精神科救急病棟勤務。
メディッコメンバーの視点
鳥ボーイ(看護師) 本人の意欲と家族の気持ちがすれ違う場面は、急性期病院の退院支援でもよく見受けられます。特に高齢の夫婦2人暮らしの場合、介護力の不足が勝ってしまい、患者さんの「帰りたい」という気持ちはなんとなく優先されていない気がします。
今回のケースでも、息子夫婦が隣町に住んでいることや、妻の体調不良、あとは患者さん本人の認知症の程度などが、今後の話を進めるうえでのポイントかなと思います。
バサカ(作業療法士) 本人の思いと受け入れ側の思いにずれが生じているケースは、精神科でも何度も直面しており、しっかりと考えなくてはいけないところです。本人の生活だけでなく、家族全員の生活を考えられるとよいのかなと思います。
かなこ(看護師) こういうケースは確かに現場でもありますね。本人はものすごく家に帰りたいと訴えているけれど、家族は介護疲れもあり、施設への入所を希望している……。入院前の自宅での様子がわからない部分もありますが、老老介護だといろいろと大変だったんだろうな、と感じました。
たみお(理学療法士) 本人と家族との意見のすれ違いは、現場でも本当に多くて、悩ましい事例だと思います。本人と家族の気持ちが、両方ともわかる部分があり、うまく折り合いをつけるのが難しいところだと思います。
おぬ(看護師) 受け入れる家族の気持ちを考えると、過去の本人の生活歴や住宅の状況など、課題はたくさんあると思います。本人のがんこな性格とそれに疲れた家族の気持ち、そして本人にとって、この先の自分の居場所の不明確さを考えると、ゴールの見えない問題という感じがしますね。
看護師の視点からの解決策①
鳥ボーイ(看護師) 患者さん本人のことから考えると、家に帰りたい意欲から熱心にリハビリに取り組み、歩行できる距離がかなり増えていることはとてもポジティブに見えます。しかし、妻の視点から考えると、活動範囲は広がったものの、アルツハイマー型認知症があるためかえって危険なことや、介護負担が増加するのではないかという懸念があります。
患者さんがどの程度の活動や作業ができるかなどをリハスタッフに確認し、妻や家族への具体的な情報提供が必要かもしれません。ADLが上がれば退院できるというわけではないので、他職種とのゴールの共有は必要だと思います。
また、妻の体調不良がどういったところからくるものなのかも聞けたらよいですね。例えば、「ADLが上がった夫が自宅に帰ってくることへの不安」や「介護においての息子夫婦との関係」など、身体的な問題以外の可能性も含んでいることがあります。
かなこ(看護師) 私も、妻の現在の体調が気になりました。妻自身に何か持病があり、ADLがある程度自立していたからこそ、夫婦だけでの生活ができていたのか?ということも考えられるのかなと思いました。
患者さんのADLがある程度上がってきたのであれば、息子家族の協力が得られるときに試験的に外泊してみるというのもありですよね。実際の療養環境と自宅は違います。家に帰って生活してみることで、いろいろと課題などが見えてくるのかなと思いました。
鳥ボーイ(看護師) そうですよね。息子夫婦が隣町に住んでいるという距離感が実際どのくらいか、判断は難しいですが、どの程度の介護なら可能なのかを確認することも重要だと思います。妻が1人ですべてを背負っていないかが、看護師としては心配なところです。
かなこ(看護師) 入所時から本人が自宅への帰宅を希望していたのであれば、入所した時点で、入院前の生活状況、家の構造、息子夫婦がどの程度介入していたのか、息子夫婦の生活背景なども含めてケアマネジャーとやりとりをしておくとよかったのではないかと思います。
そして、家族と本人で意見のずれがあるのであれば、まずは本人の意向に沿うとした場合、現実的に在宅での生活は可能なのかどうかについて、ケアマネジャー・妻・息子夫婦と早い段階でやりとりをしておく必要があります。
ただし、現在の状況で無理でも、リハビリ介入をすることでADLが上がり、在宅で生活できるようになったという事例も過去にたくさんありました。なので、一度のやりとりで「在宅の生活は無理」と判断するのではなく、リハスタッフと実際にやりとりをして、患者さんのADLの状況を確認しておくことも大切だと思います。
鳥ボーイ(看護師) 退院支援は、急性期では「患者さんの疾患がどの程度まで回復するか」に目を向けられがちですが、回復期であればあるほど、取り巻く環境の因子が複雑なケースが多い気がします。今回のように、妻や息子夫婦に対しても健康面のサポートだけでなく社会的なサポートが足りているのか、「どのようなことが満たされれば患者さんの思いが叶えられるのか」という視点で、患者さんだけでなく、家族全体へのサポートまで考慮すると別の活路を見いだせるかもしれませんね。
家族のサポートの程度などは看護師が情報収集可能かもしれませんが、自宅の環境や社会的サービスの活用についてはケアマネジャーとの連携が求められると思います。
作業療法士の視点からの解決策
バサカ(作業療法士) 作業療法士としては、患者さんから「家に帰りたい」と言われたときに、家に帰ってどのように生活をしていきたいのか、詳細な聞き取りができるかなと思います。また、帰宅後に同居する予定になる奥さんや、近郊にお住まいの息子夫婦からもお話を伺いたいところです。
現状や自宅の状況、今後の生活に対しての考え方など、家族を含めた対象者全員の思いを知ることがすり合わせの第一歩なのかなと感じます。家族にも本人の作業療法の場面での様子をお伝えしたり、看護師さんと連携を図ったりと、病棟での様子をお伝えし、現状を理解していただくことによって、家族の受け入れも捗るのではないかと思います。
コメディカルを含めて、関係職種全員と家族を巻き込んだカンファレンスを開けていたら、意思共有もできたはずだと思います。
理学療法士の視点からの解決策
たみお(理学療法士) 理学療法士としては、身体面のアプローチは順調に進んでいたとは思いますが、本人が見据える在宅面(家屋構造や家族関係など)の情報も聴取できていたのかが気になるところです。
施設と自宅では環境が違うので、現状の能力で自宅環境に適応できるのか、他に介護が必要な部分(食事、入浴、トイレ動作など)はないだろうかなど、身体レベルに応じて環境とのすり合わせをしておく必要があると思います。介護が必要な場面や日ごろの様子など、施設の看護師や介護士から細かく聞き取りをしておくとよかったと思います。
また、今回のケースでは、一緒に生活している妻が体調不良になったため、介護環境が受傷前と変わっている可能性があります。その点も踏まえて、家族やケアマネジャーとのやりとりができていればよかったと思います。
患者さんには認知症もあり、がんこな性格から、家族はこれまでにいろいろと介護負担を強いられてきた状況かもしれません。本人もその状況から、障害受容はあまりできていないと考えられるため、お互いに理解し合えていない部分があるのではないでしょうか。
そのような相互の理解を深めるためにも、家族と本人を含めたカンファレンスを開催して、今後どのような方向性にするかを話し合いながら進めていくことが必要だと思います。
看護師の視点からの解決策②
おぬ(看護師) 私は、本人が訪問リハビリには意欲的だったという点が気になりました。男性患者さんのなかには、そもそも集団のレクリエーションが苦手な人も多いです。
デイサービスでも基本的には新聞を読んだりと、他者との交流が少ないのではと思います。訪問リハビリに意欲的だったのは、個別性が重視されており、集団行動ではなかったからというのも理由だと思います。そして、目に見えて回復がわかるというのもよかったのかもしれません。
家族が帰宅に後ろ向きなのは、歩行できるようになったとはいえ、まだまだ介護が必要な状態が多く、また本人のがんこさもよく理解されているだろうから、本人と家族との間でなにか問題があるのかもしれません。ここでは家族に対し、自宅に戻ることへの不安や悩みを傾聴する必要があると思います。
看護師に言いにくいなら、長年付き合いのあるケアマネジャーなどに相談するといいですね。住宅改修で家族の悩みが解決するという場合もあるので、このあたりもケアマネジャーが詳しい情報をもっていると思います。
かなこ(看護師) なるほど。誰かよその人がいるとよい人なのに、家族だけになると途端にわがままでがんこになってしまう人もいますからね……。
おぬ(看護師) また、本人の意欲低下ですが、今の状態では家族に対する絶望感と今後の不安があり、なかなかリハビリ再開に意欲が向かわないのかもしれません。ここは無理をせず、まずは今後の方向性をしっかり決め、家族にも本人にも無理のない環境にしてから、そこへ向けてのリハビリを再開するというほうがよいと思います。
本人も精神的な面での落胆が大きいでしょうから、うつ症状が出現しないか注意深く観察していきたいですね。
*
患者さんとその家族で思いが異なるとき、どちらかが間違っているわけではないので判断が難しくなります。お互いの気持ちをしっかりすり合わせるためにも、リハビリや病棟、施設などでの様子など、さまざまな場面を見ている多職種で情報を共有し、関係者みんなの状況をしっかり知ることが大切です。
この事例のまとめ
●入院した段階から退院調整は始まっている。退院調整を行う際は、まわりの家族の状況などを含め、丁寧に情報収集をする。
●利用者本人や家族の力を多角的に判断し、その状況に合わせて多職種で共通のゴールをすり合わせておく。
●身体的なサポートだけでなく、精神的・社会的なサポートが足りているかどうかも忘れずにチェックする。
この記事は『エキスパートナース』2020年11月号連載を再構成したものです。
当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。
以上の解決方法・対処例は、ケースをもとにメディッコメンバーが話し合った一例です。実際の現場では、主治医の指示のもと、それぞれの職種とこまめに連携をとり、進めていってください。







