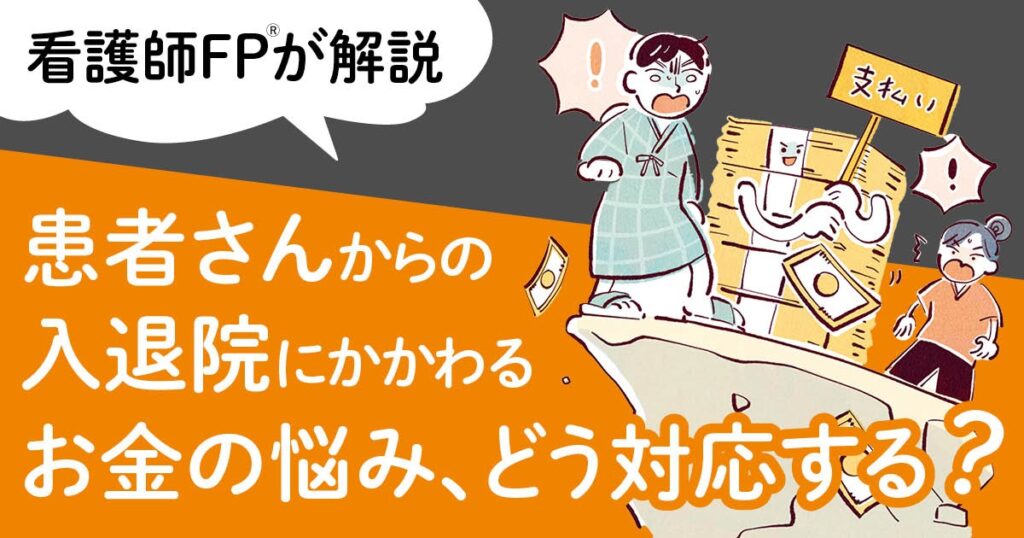患者さんからお金の心配ごとを打ち明けられた場合、看護師としてどう対応したらよいのでしょうか。自身もナースとして臨床現場を経験したファイナンシャルプランナー(FP)が、よく聞くお金の疑問・悩みについて解説する全7回の連載です。
【第1回】患者さんのお金の悩みにどう答える?ー看護師FP®が解説
〈目次〉
●看護師と連携する他職種の役割を確認
・医療ソーシャルワーカー(MSW)とは?
・介護支援専門員(ケアマネジャー)とは?
・ファイナンシャル・プランナー(FP)とは?
・社会保険労務士(社労士)とは?
【第2回】患者さんから入院費の相談、どう答える?―看護師FP®が解説
〈目次〉
●「お金が足りない」に込められた複数の意味とは?
●患者さんの不安の本質をつかみ、看護師と医療ソーシャルワーカー(MSW)が連携
●患者さんと確認したい内容
1.高額療養費制度の理解度と、想定している入院期間
2.食事代やレンタル代、個室差額ベッド代などの状況
3.入院費以外のお金に関する心配ごと
4.退院した後の生活をどのように考えているのか
【第3回】治療や介護サービスの費用の相談、どう答える?―看護師FP®が解説
〈目次〉
●介護サービスの費用は患者さんからよくある悩みのひとつ
●介護サービスへの理解度や費用の認識を再確認しよう
●患者さんと確認したい内容
1-1 介護サービスの費用に対しての認識
1-2 かかっているのが医療費と介護費どちらかなのか、どちらもなのかも確認
2 施設入所に関しての本人の考え
3 介護費用がどのくらい家計を圧迫しているのか
【第4回】退院後の収入についての相談、どう答える?―看護師FP®が解説
〈目次〉
●退職後も健康保険の傷病手当金を利用できるかを確認しよう
●健康保険の説明は「言い切らない」ことが大切
●おさえておきたい傷病手当金のポイント
●退職後の継続給付について
●傷病手当金の注意点
【第5回】保障や医療助成の疑問への適切な回答は?―看護師FP®が解説
〈目次〉
●高額療養費制度に加え、さらに費用を抑えられる可能性も
●高額療養費制度で支払う自己負担額は?
●治療開始時に限度額適用認定証を発行すると負担が減る
●さらに自己負担を軽減するには?
1.世帯合算
2.多数回該当の場合
3.その他公的な助成
【第6回】治療費が家計の負担に…どう答える?―看護師FP®が解説
〈目次〉
●お金の不安がどのくらい治療に影響を与えている?
●近年問題になっている「経済毒性」とは?
1.支出の増加
2.資産・収入の減少
3.不安感
●経済毒性の本当の問題とは?
●住宅ローンは治療の長期化で一番影響が出る
【最終回】終末期やACPにかかわる患者さんの悩みへの回答は?―看護師FP®が解説
〈目次〉
●終末期にかかわる話題はタイミングが重要
●ひとり暮らしのがん患者さんの事例
1.資産(自宅)の現金化
2.事務委任契約の検討
●話題の順番を大切に、じっくりと話し合おう