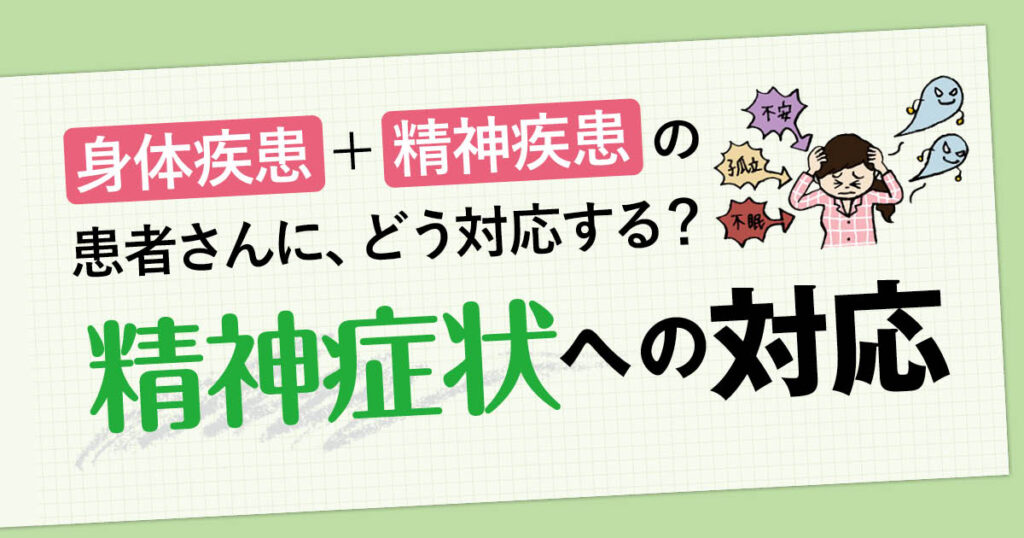一般病棟でもよく出合う精神疾患「うつ病/双極症」について、薬剤治療の進み方、経過観察とアセスメント、対応のポイントをまとめました。実際に現場で、どのような言葉かけで生かしていけばいいのかも紹介します。
疾患の基礎知識
うつ病
うつ病や双極症の患者さんは“後悔”にがんじがらめになっています。抑うつそのものは、疲れた神経を休めるための防衛反応ですが、思考が“後悔”にとらわれて身動きできなくなっているのがうつ病の状態です。
症状としては、何ごとにもおっくうになり、趣味も楽しく思えません。疲れやすくなり、食事もおいしく感じなくなります。頭が回らなくて考えることがつらくなり、眠りも難しく、果ては「いっそのこと消えてしまいたい……」とさえ思ってしまいます。
イライラや攻撃性を伴うことも多く、それが患者さん自身に向かうときもあれば(自責)、医療者に向かうときもあります(他責)。それらが“後悔”に絡めとられた舞台で繰り広げられ「取り返しがつかない」という表現になります。
躁・軽躁
躁や軽躁は、逆に気が大きくなって、自信をもって物事をズバッと言ったり行動したり。すべてにおいて抑制のタガが外れ、苦しい状況の中で一転して攻勢をかけて、中央突破を図ろうとする反応とも言えます。“後悔”によって「何とか取り返そう、埋め合わせをしよう」というとらわれが生じます。
しかしそれにはかなりのエネルギーを使うため、躁や軽躁のあとには抑うつになることが多いのです。ただ、特に軽躁というのは聞き出しにくく、うつ病として治療されていることも多いです。
入院中にやたらと多弁になったり、「寝なくても大丈夫」と言って夜中に行動していたりというのが出てきたら躁うつ病を疑いますし、抗うつ薬による治療中にこうなってきたら、躁に転じたということで“躁転”したと言います。
薬剤治療の進み方
抑うつだけのうつ病と、躁や軽躁もある双極症。これらの薬剤治療は異なります。うつ病には抗うつ薬を用い、双極症には気分安定薬を主に用います。抗うつ薬の副作用で主要なものは嘔吐や便秘などの消化器症状やめまい、ふらつきで、投与後1週間以内に軽快することが多いです。
投与後24時間以内に生じうるものとして、セロトニン症候群があります。これは興奮・ミオクローヌス・高熱・頻脈など、精神や神経系の暴走のような症状を示します。
経過観察とアセスメントのポイント
特に入院中だと、活動範囲が狭まる、好きな食事メニューも残してしまう、いつも読んでいる新聞や本を読まなくなる、夜中もお布団の中でもぞもぞしている、話をしていても動きや感情がゆっくりになっている、逆に落ち着かない感じがあるなどが観察ポイントになります。
そういった観察ポイントで当てはまるところがあれば、しっかりと患者さんに聞きましょう。「最近、新聞を読んでないですね。どうかされました?」など、心配して気にかけている姿勢を出します。
このことで患者さんは「きちんと看てくれているんだ」と思ってくれるかもしれません。やはり入院
中は孤立ぎみになることが多いため、そこは医療者の細やかな気づきが大切になってきます。
この記事は会員限定記事です。