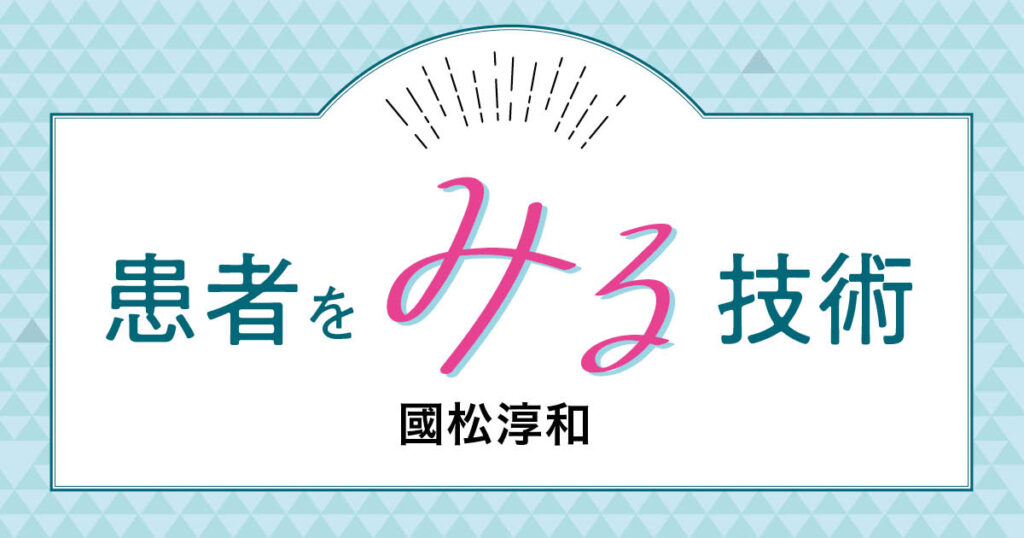皆さん、こんにちは!内科医の國松淳和と申します。
新しい年度になりました。この連載も2年目に入ります。特に内容が大きく変わるわけではないのですが、「患者をみる技術」というのは臨床現場で職種を問わず一貫して必要であり、重要なスキルだと私は思っていて、何様かと思われるかもしれませんが、今年度もこの連載を張り切って参りたいと思います。
年度始めにあたり、今年度の裏テーマを一応決めてみました。それは「対話」です。「……てことは、ついにコミュニケーションスキル/接遇の講座ですか?聞きたい!」などと思われるでしょうか。悪くない線ですがちょっと違います。エキスパートナース編集長も私も、2人ともコミュニケーションという言葉があまり好きではないのでそれはないです。
あくまで「患者をみる技術」を突き詰めるのが私個人のテーマです。患者さんを良くしていくためには、考えを「言葉にする」ということはとても大事です。
こういうと、「私は文章が下手だから」とか言うかもしれません。別にいきなり文章が上手になる必要はないですし、そういう勉強をしてほしいわけではありません。自分の考えを言葉にするための、最良のトレーニングは「人に話す」ことです。自分の考えを、言葉を使って人に話すようにしましょう。
これは、1年目看護師だけではないですよ?総合病院の師長さんも、看護学校の教員でも、ベテランナースでも、はじめてプリセプターになる人も、新2年目ナースでも、パートさんでも、ああすみません医師も薬剤師も臨床検査技師ももう全員です。
一人一人が、自分の考えを人に伝えることを大事だと思えることができれば、人の話を聞くようになります。自分の考えを話せる空気をつくれていますか? 結局はこのあたりが課題になるでしょう。そんな理想的なことなんてできないと思われている方もいるかもしれません。
しかし考えてみてください。私、「対話をしよう」などと嘯(うそぶ)いておりますが、対話をするなんてそもそも当然じゃないですか。お仕事なんだから。そんなあたりまえのことができそうもないという空気を、私は打破したんですよね。大丈夫でしょうか。私だけ空気違いますでしょうか。空気とかそういうことは私にとってどうでもいいんです。この連載で、少しでも皆さんが、何かを掴むことができればそれでいいなと思います。
それでは2度目にはなりますが、張り切って参りましょう!
何はともあれ
まずははじめに、この春から看護師になられた皆さん、看護師国家試験合格おめでとうございます。国家試験に受かった後に、一緒に喜んでくれた人がいますね?その人たちのことをずっと忘れないでください。今後、看護師としてつらいことがあったら、その人たちのことを思い出すといいと思います。
きっとそんなに大勢いないでしょう。2、3人とかじゃないでしょうか?お金と自分以外では、その人たちのためだけに看護師をしていくとよいと思います。
いいですか?ここ重要ですよ?患者さんや社会のためとかではありません。ごく限られた、自分に近い、自分のことをやさしく応援してくれる人だけを信頼していけばいいです。逆に言えば、それ以外の人たちは全員「お仕事の相手」として接しましょう。この種の「割り切り」あるいは「気持ちの入れ替え」が、国家資格をもった職種の人たちには必要なのです。
「合格を一緒に喜んでくれた人なんていない!」と言う人がいるでしょうか……。まあ大丈夫です。そういう人は私が喜んでいますから。
勉強していく仕事
看護師になるプロセスで、すでに結構しんどかったかもしれません。過去の人生で一番つらかったと言う人も聞きます。あのつらさって、「評価されてる感」というのがその要因の1つだと私は思っています。学校というところはそうかもしれません。
ただし労働というのは、誰かに評価されるためにがんばるところではありません。スキルを身につけて、ベタな表現ですが「手に職」をつけるために勉強をしながら仕事をしていくというのが、われわれの仕事(国家資格)です。
ナースは人間関係の問題が何かと課題になると聞きますが、それは本質を捉え間違えています。空気を読む、みたいなコミュ技ではなく、臨床の技術を勉強しないとだめです。
「人間関係が問題だ!」のような種類の課題を先に立てていることが問題だと思っています。そもそも職場の人同士で仲よくなる必要がないです。これはおわかりですか?必要なのは、技術を高め合うための対話や、患者ケアという成果をあげるための職場の人との協調です。
どうしてもだめな人が職場にいる
何度も何度もかかわりを試みて、長いこといろいろうまくやろうとしてみたけれど、全っ然無理。こういう人は正直いると思います。
私の考えは非常にシンプルで、その人が変わってくれることは無理だと思います。その原因にはいろいろあり、一概には回答できないと思います。私に相談していただければ回答します。
つらくなってハマる前に
この春、新しい職場に来たという人もいるかもしれません。うまくやる……というか、ただでさえしんどい仕事を継続していくためのコツがあります。
これは臨床現場どうこうというよりライフハックに近いんですが、「いつも機嫌がよい人」をとにかく一生懸命探し見つけることです。命がけで探しましょう。その職場に見つからなかったら他部署・他職種、あるいはネット友だちとかでもよいかもしれないです。
いつでも機嫌がよい人だなあ、元気をくれる人だなあと思える人がいたら、その人は自分にとってのみならず、そのコミュニティ全体にとって宝だと思って大切にしてみてください。
ありがたい人間関係というのは、むしろお金で購入したいくらいで、その(ゴキゲンな)人とかかわれるのだったらどんどん課金するくらいのつもりでもいいかもしれませんね。おごるからお茶しに行こうとか、交通費出すので一緒に外出してほしいとか。
いつも機嫌が悪い人
ちなみに、いつも機嫌が悪い人というのがいます。残念ながら一定数います。これはしょうがないかもしれません。この人たちは、自分に余裕がないんです。余裕がないという理由が本当に多岐にわたるので、またこれが説明が難しいのです。
例えばこんな不機嫌さんです。新人の指導役を任されるくらいの年数の看護師さんだとしましょう。新人のめんどうをみていると時間的に余裕がなくなり、もともとすごくいろいろきっちりちゃんとやりたいタイプだけど、いつもやってるその“きっちり”ができなくなる。
それがストレスになってしまう。心理的にも時間的にも余裕がなくなり、そう思って接するのでかえって時間がかかってしまう。またそれがつらくなり、いつもの仕事がきっちりできず、それがストレスになるというループ。
このように、冗談抜きでこの程度のループでいつも不機嫌な人もいます。この負のループを、新人のほうから断ち切るのは難しいです。
できれば管理者が見つけて、苦手なことをさせない工夫が必要です。その工夫のためには、ナース個々の特性をよく知るということがきわめて重要です。
多分この連載では、今後「特性」という言葉を私は多用すると思います。例えばさっきの「きっちりナース」さんは、新人の指導は極度に苦手かもしれませんが、普通の人が苦手なことがすっごく好きで得意かもしれません。そして、そのことが師長さん(上司)に伝わってないだけかもしれません。ていうか、そこまできっちりやらなくていいんですけどね……。
医療現場って、まだまだスタッフを平等に扱おうとしますよね。私、それはもう限界にきていると思います。これからは、漫画『おはようKジロー』で岡本慶司郎(Kジロー)が冠学園で作った野球部のようなチームづくりがよいと思います(誰もわからない)。
えっとつまり、苦手を克服させるような教育は、あまり汎用性が高くないと私は思っています(得意を伸ばせ!)。
やっぱりコミュ力…?
そうではありません。コミュニケーション能力という、曖昧な言葉や概念は、私は取り入れたくありません。正直、私は自分のことを全然コミュ強者だと思っていません。
コミュニケーションなんぞに大切な時間を費やしてはいけません。費やすべきは職能を上げるための勉強です。技術を高めるぞという気概が、重要です。
勉強は知識をつけ、技術を高めるのに役立ちます。それをあきらめないこと。知識と技術を高めるために一部の人は経験(時間)が必要かもしれませんが、高まってくれば余裕ができます。余裕ができると人と穏やかに対話できるようになります。
ちなみに穏やかな対話の起点は、「余裕がある側が聞いてあげる」ことです。ただし、聞き手(教わる側)はそれに甘えてはいけません。このあたりは、今はまだはっきりわからなくて大丈夫です。
人のつらさはわからない
人は元気そうに見えても、つらさを抱えていることがあります。しかも、そういう人に限って、そのことを奥深くにしまっていて、他人からはとてもわかりにくくなっています。
安易に人の気持ちをわかった気にならないほうがよいです。そこで大事なのは、とにかく何か言葉にしてもらうことです。
その一番よいプラットフォームが「対話」なんです。自分は孤独だな、対話なんてできないなと思われる人もいるかもしれません。孤独だと思ってしまうことをとりあえず私は否定しません。むしろそう思える感性がある人なんだなあと、肯定的にリスペクトします。
ただ、私がそのような人とお話しているうち、自己愛特性が強くてそれをこじらせているんだなと気づいてしまうかもしれません。このあたりは連載でいつか取り上げましょうか。
励ます人になる
先ほど「いつも機嫌がよい人」という人がいるものだという話をしました。世の中はうまくできていて、人は「励ます人」と「励まされる人」の2つに分けられます。この読者のなかにも、教わることなく他人を励ませられる人が必ずいると思います。
私が一番主張したいのは、これはもう確信なのですが、「本当は励ませられる人なのに自分が励ます側だと思っていない人」「対話が不足しているために、言葉にできず励ますことができずにいる人」がいるはずだということです。これはもったいない。
なんか、励ますって青くさいですよね。もうその“よさげ”な感じにただ嫌悪感を覚える人もいるでしょう。「励ますなんてちょっと無理」みたいに鬱陶しく思う人もいると思います。
ですが、私は思うんです。そういう人は、その「励ますのなんてやだ」という気持ちを口にせずにいてほしいです。そういう空気が目立ってくると、励ますことができる人たちが口をつぐんでしまうのです。これが問題です。
もっと対話をしよう
まとめです。機嫌よく過ごす。そのご機嫌を他の人に分け与える。
それが無理ならいつも楽しそうにしている人となるべく一緒に過ごす。とにかく機嫌がよい人がこの社会の宝です。機嫌が悪い人は、他のことでがんばりましょう。でも、その機嫌の悪さを伝播させないでください。
最初のうちは、「接し方」「声のかけ方」などを考えたりして、人間関係を小手先でよくしようとしてはだめ。人間関係は後からついてくるものです。まずは中身。
そこで、人に迷惑をかけずにやれるのは勉強です。勉強は、明日からすぐ役立つ勉強と、いつ役立つか・そもそも役立つかすらわからないような勉強と2種類あります。じつは重要なのは後者です。
そして、私のこともたまには励ましてください!編集部に届いたポジティブな声は全部、編集長がまとめて私に教えてくれます!励ましていただくと何がよいかというと、楽しく連載を執筆できます。連載はじつはフレッシュなもので、結構執筆しているときの気分や考えが取り入れられることが多いです(書籍作品の執筆と違うところ)。
今日は読んでくださりありがとうございました。私の連載が、皆さんの「弱音」を拭えるものでありますように。
この記事は『エキスパートナース』2022年4月号連載記事を再構成したものです。
当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。