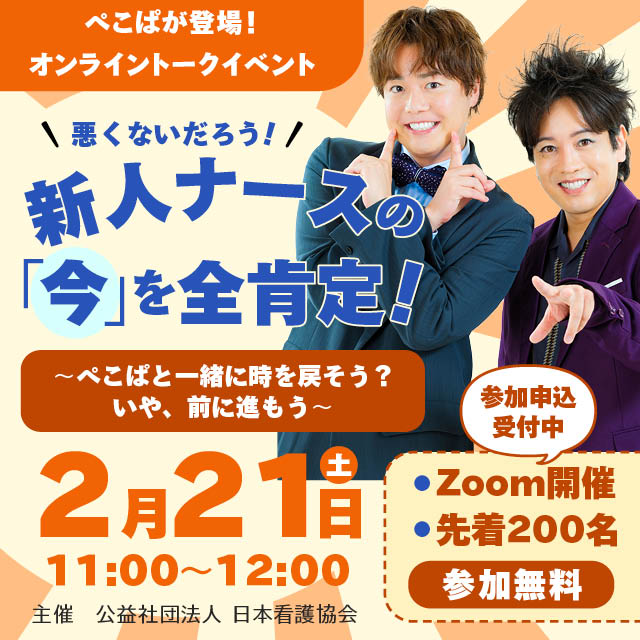20世紀半ばから現在に至るまで、看護は多くの変化と困難を乗り越えてきました。その中で「書く」という営みを通じて、看護実践の価値を問い続けた川嶋みどり先生が、これまでの経験と想いを綴った言葉を厳選し、一冊の本にまとめたのが『川嶋みどり看護の羅針盤 366の言葉』 (ライフサポート社、2020年)。
この連載では、本書に収載された看護の現場や看護職の想いだけでなく、個人としての視点や感性も込められた366の言葉を、毎日1つずつご紹介します。
人々の生活の中から
生まれた専門職として
普通の人の気持ちに
寄り添うことのできる
センスを磨きたい
日々の看護においても、発想の貧困や感性の鈍麻は、技術の未熟以上に患者を苦しめることになる。人々の生活の中から生まれた専門職として、普通の人の気持ちに寄り添うことのできるセンスを磨きたい。それは一見何気ないように見えて、そのセンスのありようが、病者にとっては療養の質を左右することにもなる。
たとえば、絶飲食を解かれて最初に口にする流動食の味やのどごしを、その病者がどのように体験しているかについての看護師の想像力の有無は、その後の回復を左右するとさえ言えると思えるからである。
(出典:『看護時鐘 のどもと過ぎた熱さをいま一度』120ページ、看護の科学社)
●「川嶋みどり 看護の羅針盤」の記事はこちら
●そのほかの連載記事
当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。