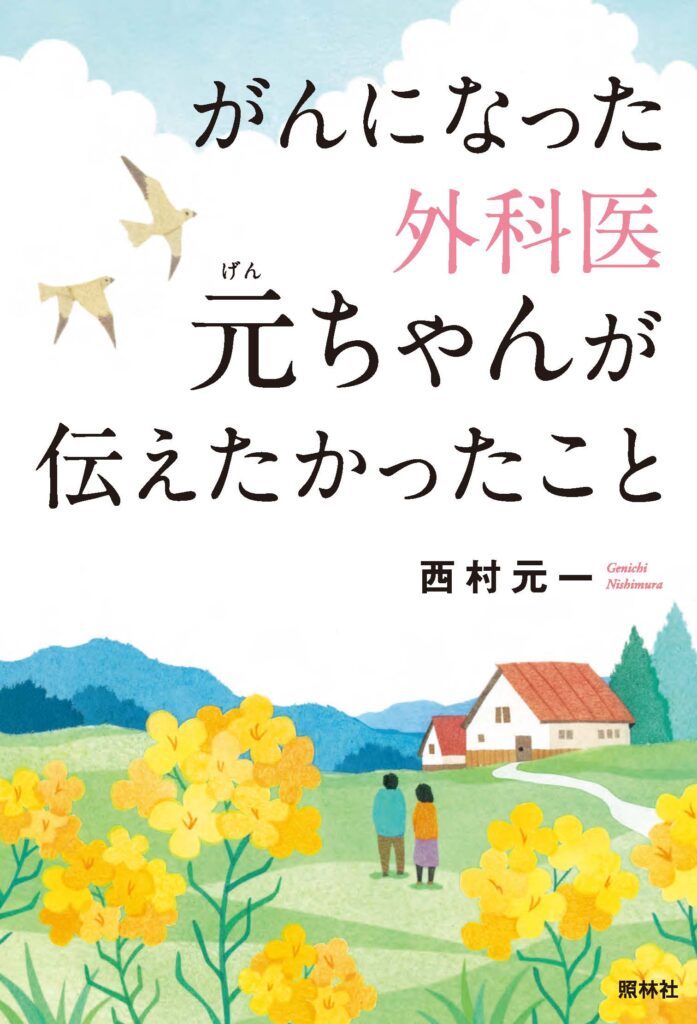西村元一先生が、がん患者となった2年半を綴ったエッセイ『がんになった外科医 元ちゃんが伝えたかったこと』を連載でお届け。患者になってみてわかった、チーム医療の課題とは?
ただ休むよりも、役割や居場所があることが力になる
今回の入院では、たくさんの方がお見舞いに来てくださいました。また、このような状況にもかかわらず「回復したら、また一緒に仕事ができるように席を空けておくよ!」と言ってくださった方々もおられ、その言葉が闘病への意欲をもたらしてくれたことは間違いありません。
「無理はしなくてもいいよ、ゆっくり休んだら!」と言われる方が大半ですが、やはり「何か役割があること」「自分の居場所があること」が今後療養するうえでの目標にもなりますし、生きていることを実感できるのではないかと今は思っています。当然、病状によって違ってくると思いますが……。
ただ今後は、できるだけやりたいことだけに絞り、自分自身の時間、そして家族や仲間との時間をもっと大切にしていきたいというのが実感です。
先日、幼なじみである国際医療福祉大学の高橋泰教授がお見舞いに来てくれました。いろいろ世間話をしたあとに「10年前と今はどういうふうに治療が変わったと思う?」と聞かれたので、「明らかに治療成績は今のほうが向上していると思うよ。そして10年前にはチーム医療なんてほとんどなかったと思う」と答えました。
薬物療法は明らかに進歩してきており、手術に関しても器具や術後管理がこの数年で大きく変化してきています。そして何よりも、現在普通に見聞きする「チーム医療」は、ここ10年ほどで一般化されたと言っても過言ではないと思います。
理想のチーム医療をめざす日々から、チーム医療を受ける立場に
そのあとで「患者となって、チーム医療のいいところとそうでないところを感じた?」と聞かれました。
チーム医療は自分自身の大きなテーマとしてきました。看護師さんたちと一緒にストーマ管理をしていたのがチーム医療の最初で、その後、栄養管理、化学療法、クリニカルパス、感染対策、緩和ケアなど、患者さんのために理想のチーム医療をめざしてみんなで取り組んできたつもりです。
ただ最近は「何のためのチーム医療なのか」を悩む場面も少なくありませんでした。医療者の業務軽減、役割分担やリスクマネジメントなどもチーム医療の目的であり、広い意味では患者さんのためと思われます。しかし普及とともに、「○○さんの治療」から「多くの患者のうちの一人の治療」に対象が変化してきているように思います。「チーム医療は一人ひとりの患者さんにとって本当にメリットがあるのだろうか?」と考え始めたときに、自分が患者になってしまいました。
チーム医療が進んで、看護師のみならず薬剤師、栄養士、理学・作業療法士、MSW(メディカルソーシャルワーカー)などがどんどん表に出てきました。そして褥瘡対策チームやNST(栄養サポートチーム)など組織横断的な専門家チームができたことにより、「どこに相談すればよいか」が明確になりました。
医学は日進月歩以上に進歩しており、スタッフがすべての領域を網羅することは難しくなってきています。「どこに相談すればよいか」がわかりやすくなったのは、チーム医療が一般的になったからこそだと思います。今回の入院でも、本当にたくさんの職種の方々にお世話になりました。
忙しい医師だけでは不安。すべて把握している「誰か」をチームに
さて今回、患者となってみると、チーム医療はまだ未成熟である、もしくは弊害もあると感じられました。
一点はコミュニケーションについてです。チーム医療で一番大事なのは言うまでもなく情報共有であり、電子カルテとカンファレンスがメインと思われますが、忙しい業務のなかでのカンファレンスはけっこう限界があるものです。やはり中心は電子カルテということになります。
しかし、スタッフ個々の心がけしだいと言ってしまえばそれまでですが、電子カルテの記載のみで「状況をすべて把握している」と勘違いする人もいるはずです。業務に追われてしまい、患者とは最低限のやり取りしかできないのかもしれませんが、カルテの記載は必要最小限のもので、かなりはしょられている可能性があることを考えておく必要があります。
また患者さんの気持ちは日々(場合によっては一日のなかでも)変化します。電子カルテの情報のみにとらわれず、ときどきは患者とコミュニケーションをとって自分自身でも確認することが重要ではないでしょうか。そしてそのコミュニケーションで救われる患者も少なくないと思います。
もう一点、これは以前からですが、役割分担されすぎていることで、チームの他職種の業務内容に関していわゆる「傍観者」になってしまっている場合があります。やはり他職種の領域でも、少しは踏み込んでいくことが重要だと思います。
またそれにも関係しますが、患者の立場になってみると、自分の全体の病態を把握しているはずの主治医以外に、「自分のことを全部わかってくれている人がいるのかな?」と時おり不安になります。やはり患者に寄り添うという意味で、「治療方針」「他職種のかかわり」「精神的状態」などすべてを把握している「医師以外の誰か」が、チーム医療には必須であると実感した日々でした。
※この記事は『がんになった外科医 元ちゃんが伝えたかったこと』(西村元一著、照林社、2017年)を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。