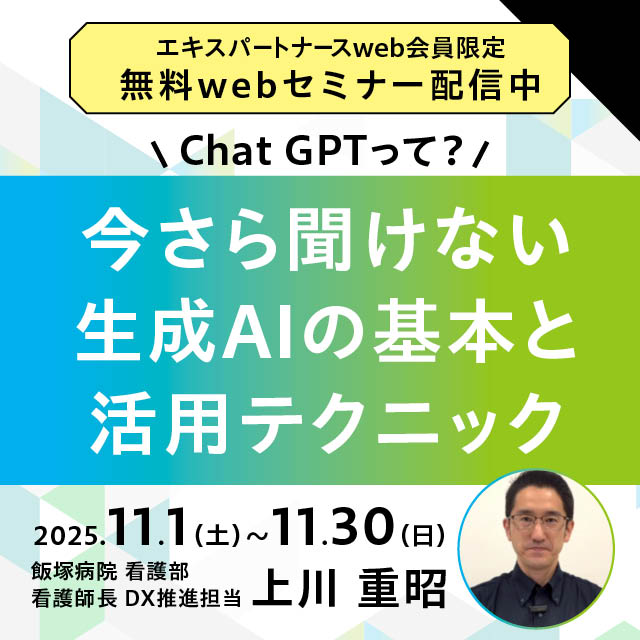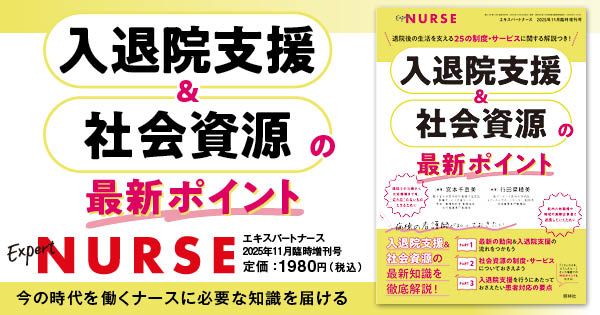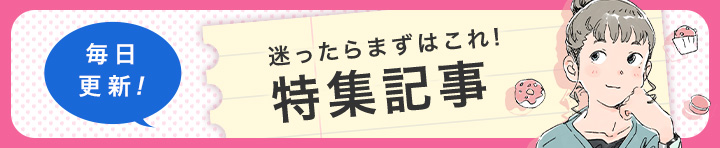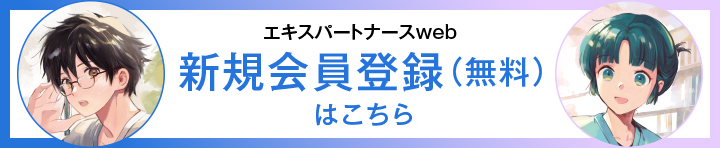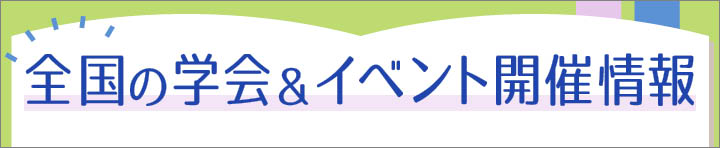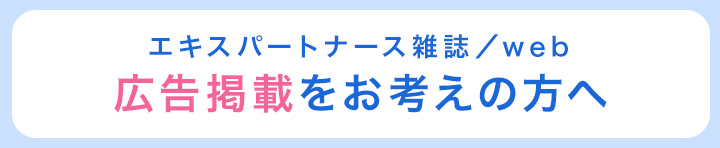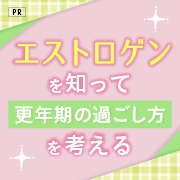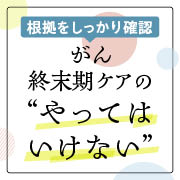-
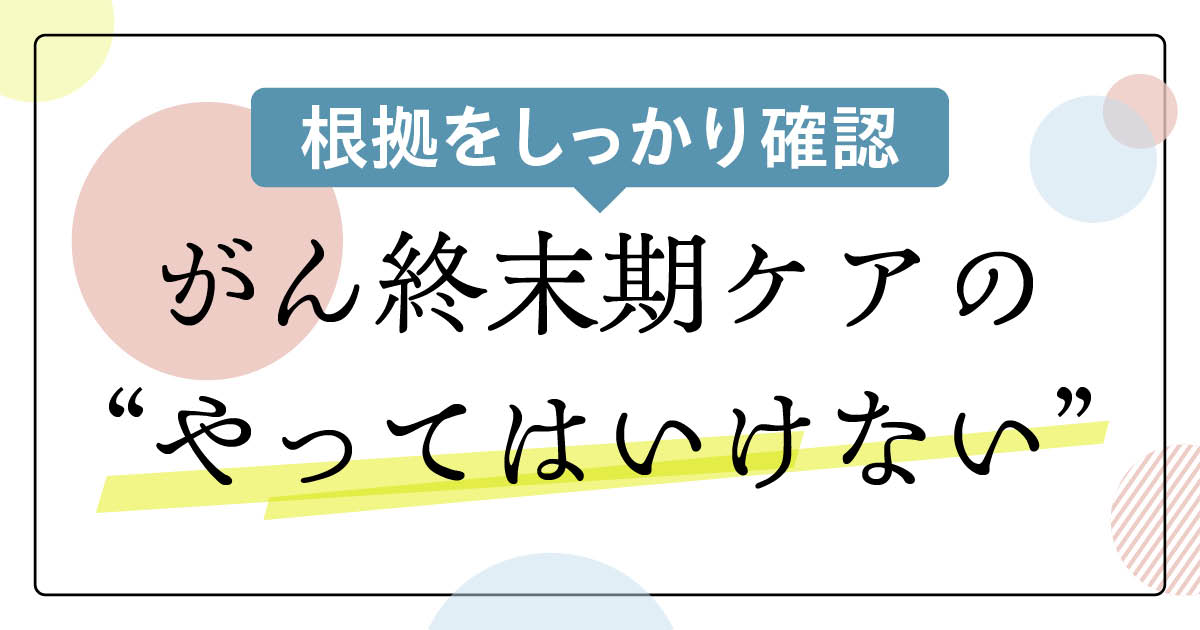
がん終末期の排便コントロール:便秘の原因やアセスメント方法とは?#9
- 会員限定
- 特集記事
-
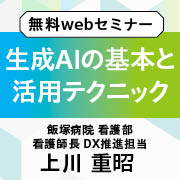
【無料webセミナー配信中】Chat GPTとは?看護に役立つ生成AIの基本と活用術
- 会員限定
- 動画
-

【新規会員登録(無料)キャンペーン】PDFを1冊まるごとプレゼント!
- 会員限定
- お知らせ
-

川嶋みどり 看護の羅針盤 第322回
読み物 -
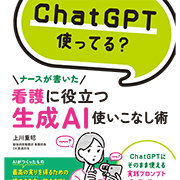
生成AIで何ができる?メール・レポート・要約など看護師にも役立つ活用術
特別記事 -

川嶋みどり 看護の羅針盤 第321回
読み物 -

「オルト」の意味とは?―看護師のための医療ことば図鑑
マンガ -
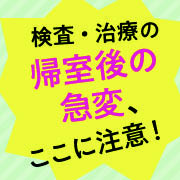
【連載まとめ】検査・治療後の急変に注意!帰室後に確認すべきサインと対応ポイント
特集記事 -
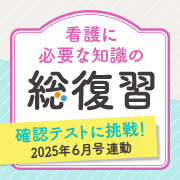
年末の振り返りに!看護師のための知識チェックテスト【特集連動】
- 会員限定
- 雑誌連動記事
-
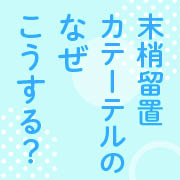
【連載まとめ】末梢留置カテーテルの“なぜこうする?”
特集記事
特集記事
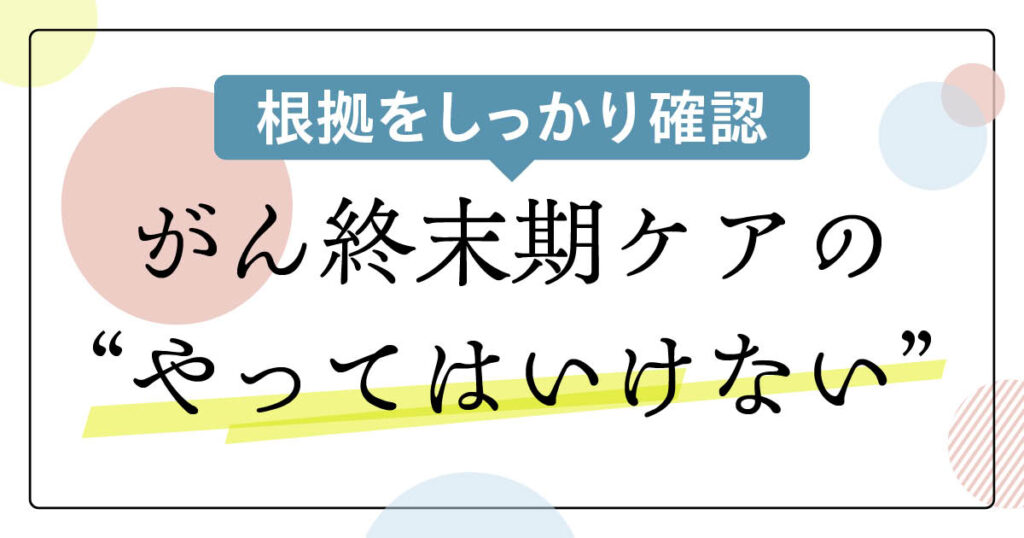
がん終末期の排便コントロール:便秘の原因やアセスメント方法とは?#9
がん終末期では経口摂取がなくても排便コントロールが必要です。便秘は食欲不振や嘔吐、せん妄の誘因になります。便秘の原因や排便アセスメントのポイントをわかりやすく解説します。 「がん終末期ケアの“やってはいけない”」の連載まとめはこちら がん終末期ケアのNG経口摂取していなくても、排便コントロールを怠ってはいけない〈理由〉食べていなくても便秘は起こり、食欲不振や悪心・嘔吐、せん妄などの誘因になるから 便秘はがん患者さんにおいて高頻度に起こり、患者さんのQOLを低下させ、場合によっては痛みよりも大きな苦痛を引き起こす可能性があります。 しかし、医療者は、「食べていないから便が出なくても大丈夫」と便秘を過小評価してしまう傾向にあります。食事がとれないときでも、腸からの分泌物、粘膜表面の落屑、腸内細菌などのため、排泄は起こります。 便秘を見過ごし放置しておくと、食欲不振、悪心・嘔吐、 腹痛(疝痛)、 排尿困難、 尿失禁、 せん妄の誘因となってしまいます。 便秘の定義とは? 便秘の定義を、表11に示します。 表1 便秘の定義 ●便秘とは、患者の主観的な感覚で、便が長いあいだ腸管内に停滞したために、水分が減少して硬い状態(宿便)になり、排便に困難を伴う状態を指す●2~3日に1回しか排便がなくても、便の硬さが普通であり、排便に困難を感じないときには便秘とは考えられない●逆に、毎日少量の排便があっても、それが硬く、排便に努力と苦痛を伴い、腹部膨満感などの不快症状を伴うものは便秘と考えられる (文献1より引用) 排便のアセスメント方法は? 終末期では75%のがん患者さんに便秘がみられ、便秘の予防や何らかの排便処置が必要となっています2。 排便習慣は個人差が大きく、客観的評価だけでは不十分であり、患者さんの主観的体験に基づいて便秘の評価をしていくことが必要です。排便のアセスメント(表2)をして便秘の予防に努めることや、下剤を適切に使用することが大切です。 表2 排便のアセスメント 1)患者に確認すること(主観的体験)●それまでの排便習慣や最終排便の日時●排便状態(回数、便の硬さ)●排便時の仏痛や便失禁の有無●血液や粘液を伴うか否か●排便に有用な要因はあるかの確認 2)治療など医学的な背景(客観的評価)●病態●現在使用している薬剤●下剤の種類や量などの使用状況●坐薬や浣腸の使用状況や頻度 (文献2を参考に作成) がん終末期の便秘の原因は? このブロック以降のコンテンツは非表示になります 便秘の原因を表3に示します。終末期になると、便秘の原因は1つだけでなく、複数あることが考えられます。 表3 終末期における便秘の原因と対応 ①がんによる直接的原因●腫瘍の直接浸潤・転移・圧迫による消化管閉塞〈対応〉胃管挿入や胃瘻、人工肛門など外科的療法も考慮する●骨盤神経障害などに伴う麻痺性イレウス(排便反射の消失)●高カルシウム血症に伴う麻痺性イレウス〈対応〉高カルシウム血症の治療としてビスホスホネート製剤の投与を考慮する ②がんに伴う二次的な影響●食物摂取量の低下●低繊維食●脱水●全身衰弱●活動性の低下●不安などの精神的ストレス●排便環境の不備 ③治療薬物の影響●オピオイド●抗コリン薬●抗うつ薬●鉄剤 など〈対応1〉オピオイド、抗うつ薬は特に注意し、原因薬物の中止もしくは変更を考慮する〈対応2〉オピオイド使用時の便秘は必発のため、事前に下剤の投与などの予防対策を立てる 終末期の排便マネジメントで重要なことは、個々の患者さんの排便習慣、便秘の原因、病態生理を把握して、予防的にかかわることです1。 また、排便コントロールは、医療者だけでできることではありません。患者さん、ご家族とともに、便秘の原因・対処方法・目標について話し合っていきましょう。その際に、セルフケアができるように患者教育を行い、患者さんの排便習慣に合わせた取り入れやすいケアを考えていきましょう。 羞恥心・自尊心に配慮した排泄ケアを検討する 排泄行為は、今までの生活のなかで培われたものが大きく影響していると言われます。 患者さんは排泄を手伝ってもらうことに羞恥心を感じており、さらに、身体機能の衰退を感じている状況では「自分でできなくなってしまった」という自尊心の低下も生じてきます。 そのため、看護師は、排泄コントロールだけに集中するのではなく、患者さんの信念や価値観を理解し、患者さんとともに排泄ケアの方法を考案していきましょう。 まとめ●便秘の原因をアセスメントし、患者・家族と相談しながら予防的なかかわりをもつ●患者の羞恥心、自尊心に十分に配慮する 引用文献1.田村恵子 編著:がんの症状緩和 ベストナーシング.Gakken,東京,2010:134-139.2.恒藤暁 編:最新緩和医療学.最新医学社,大阪,1999:102-106. 参考文献1.日本緩和医療学会 緩和医療ガイドライン作成委員会編:がん患者の消化器症状の緩和に関するガイドライン(2011年版).金原出版,東京,2017:31-33. この記事を読んだ方におすすめ●【連載まとめ】重篤な便秘の見きわめや看護ケアのポイント●【連載まとめ】排泄ケアの基礎と実践:看護現場で役立つポイント●そのほかの連載記事 次回の記事:【第10回】がん終末期の清潔ケアのコツとは?苦痛に配慮した工夫と皮膚トラブル予防(12月9日配信予定) ※この記事は『エキスパートナース』2015年6月号特集を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。
- 会員限定
- 特集記事
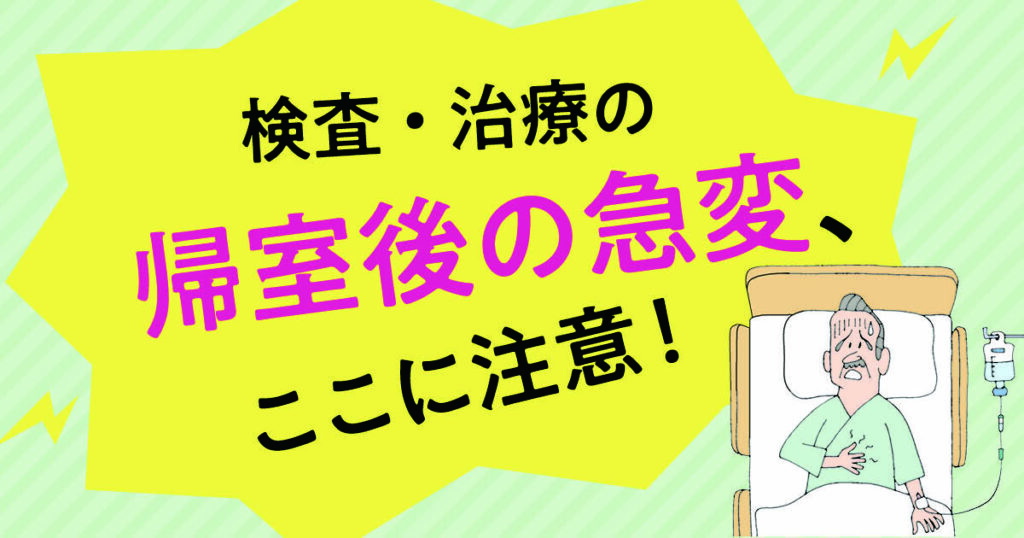
【連載まとめ】検査・治療後の急変に注意!帰室後に確認すべきサインと対応ポイント
別部門での検査・治療から帰ったあとに起こる急変は意外と多い!「帰室時の状態」や「異常への対応」をわかりやすく紹介する全22回の連載です。 【第1回】心臓カテーテル検査の目的・穿刺部位・帰室後の状態 〈目次〉●心カテ検査を行う目的は?●左心カテーテル検査の流れ●帰室時は両手が不自由、出血のリスクも 【第2回】心カテ後の帰室後急変:注意すべき急性合併症とは? 〈目次〉●病棟間ギャップを解決するための配慮点●急性冠動脈閉塞●出血・血腫●造影剤アレルギー●迷走神経反射(ワゴトニー) 【第3回】心カテ検査後の帰室後ケア:出血予防の安静援助と疼痛緩和の実践ポイント 〈目次〉●出血をさせないための安静への援助・橈骨動脈・上腕動脈穿刺の場合・大腿動脈穿刺の場合●徐々に出現する疼痛緩和 【第4回】内視鏡検査・治療の目的と帰室後に注意すべき症状 〈目次〉●内視鏡検査・治療を行う理由・内視鏡検査・治療の種類●注意したい内視鏡検査・治療・内視鏡的拡張術・内視鏡的粘膜剥離切開術・内視鏡的止血術・止血機序からみた内視鏡的止血術の種類●帰室時には疼痛、腹満感などの症状が現れる 【第5回】内視鏡検査・治療後の帰室後に注意すべき出血・穿孔への対応 〈目次〉●出血・ショックの5徴候●穿孔・主な穿孔部位と症状・徴候 【第6回】内視鏡検査・治療後の誤嚥や低酸素血症を防ぐ鎮静覚醒後のケア 〈目次〉●誤嚥や低酸素血症を防ぐための鎮静覚醒後のケア●前処置は大腸内視鏡検査の要 【第7回】血液透析の目的と帰室後の血圧変動のリスク 〈目次〉●血液透析(HD)の目的は体内の環境を整えること●血液透析(HD)では拡散と(場外)濾過が行われる●帰室時は血圧の変動に注意 【第8回】血液透析の帰室後は血圧低下・意識消失・脳梗塞、不整脈に注意! 〈目次〉●血圧低下・意識消失・脳梗塞●不整脈 【第9回】血液透析の負担を軽減!帰室後に行うべき看護ケア 〈目次〉●透析中の負担を軽減する●体重増加を抑える(除水量を増やさない)●次の透析までの期間にも注意(心臓突然死や不整脈)●透析患者さんの負担は想像以上 【第10回】脳アンギオとは?目的・検査手順・帰室後の注意点 〈目次〉●くも膜下出血の出血源、脳出血の原因などを探るために脳アンギオを行う●ヨード造影剤を使用し造影・脳アンギオの流れ・前処置・検査室●帰室時は穿刺部の止血のため、数時間~半日程度の圧迫・安静 【第11回】脳アンギオ後の急変:穿刺部出血・塞栓症・ヨード造影剤アレルギーへの対応 〈目次〉●穿刺部の出血・固定に必要な物品と固定の例●穿刺部の血腫・仮性動脈瘤●塞栓症●ヨード造影剤アレルギー・造影剤(非イオン系尿路・血管造影剤)の副作用 【第12回】脳アンギオ帰室後のケア:安静保持支援と穿刺部の観察ポイント 〈目次〉●安静の保持・飲食の開始●圧迫解除後の穿刺部観察●安静解除後のその他の注意点●コラム:“安静保持”が重要。認知機能・理解度の把握を 【第13回】ERCPとは?検査目的と手順、帰室後の注意点 〈目次〉●胆道疾患の診断などのためにERCPを実施●口腔から内視鏡スコープを挿入、体位には苦痛を伴う・ERCP の流れ●帰室時は麻酔からの覚醒途中 【第14回】ERCP後の急変:膵炎、臓器損傷、造影剤アレルギーに注意 〈目次〉●ERCP後膵炎●内視鏡による臓器損傷●造影剤アレルギー 【第15回】ERCP後膵炎予防のための安静援助と重症化を防ぐ観察ポイント 〈目次〉●ERCP後膵炎予防のための安静への援助●重症化を防ぐための合併症に対する観察●コラム:部門間のコミュニケーションが重症化を防ぐ 【第16回】気管支鏡検査とは?目的・手順・帰室時の注意点 〈目次〉●気管支鏡検査とは?肺がん、間質性肺炎といった病気を疑う場合に実施●位置や疾患によって検査の種類を選択・気管支鏡検査の流れ・気管支鏡検査の種類●半覚醒状態で帰室するケースが多い 【第17回】呼吸器疾患の確定診断に有用な気管支鏡検査:帰室時の申し送りポイント 〈目次〉●呼吸器疾患の確定診断に気管支鏡検査が役立つ●帰室時の申し送りで気をつけたいポイント 【第18回】気管支鏡検査の2大合併症:肺・気管支からの出血と気胸への対応 〈目次〉●肺・気管支からの出血(2大合併症の1つ)●気胸(気管支鏡の2大合併症の1つ)●コラム:リドカイン中毒の症状はすぐに医師へ報告を 【第19回】気管支鏡検査前の口腔ケアと鎮静覚醒前の看護ケアのポイント 〈目次〉●検査後約2時間の鎮静覚醒前のケア●口腔内の細菌などによる発熱や肺炎●コラム:退院時の指導のポイント 【第20回】放射線治療の目的と流れ、帰室後の身体状態は? 〈目次〉●放射線治療を行う理由・がんに対する放射線治療の流れ●放射線治療で何をやってきたか・がんのDNAを切断する放射線の間接作用のイメージ●帰室時の身体状態は?●コラム:ペースメーカや埋め込み型除細動器などがある患者への対応 【第21回】放射線治療後の急変:放射線肺臓炎と出血のリスク 〈目次〉●放射線肺臓炎・放射線治療との併用で放射線肺臓炎を併発するリスクがある抗がん薬●原疾患に関連する出血 【最終回】放射線宿酔・放射線皮膚炎・粘膜炎への看護ケア 〈目次〉●放射線宿酔のケア●放射線粘膜炎のケア●放射線皮膚炎のケア●コラム:照射野やマーキングの場所を避けて貼付薬を貼るために そのほかの連載はこちら
特集記事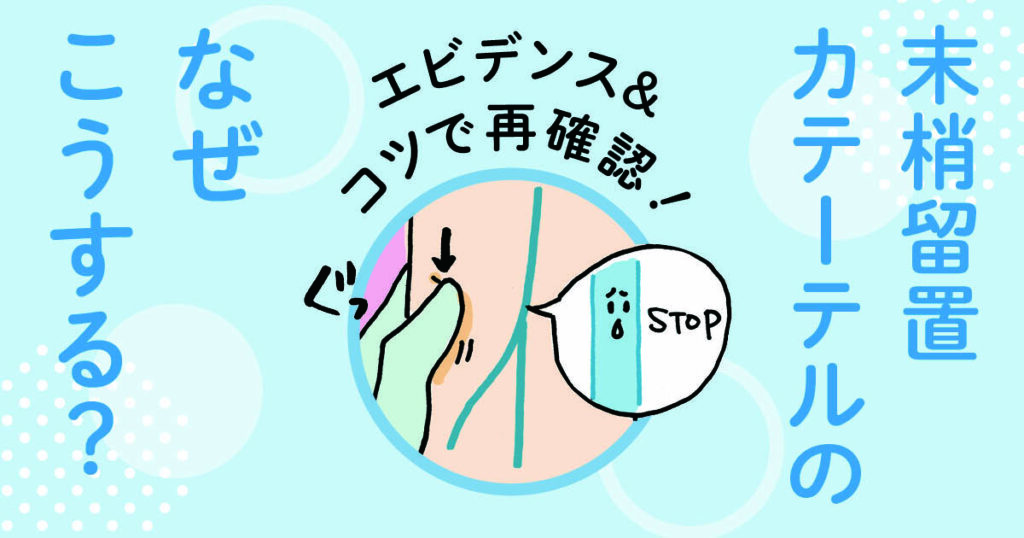
【連載まとめ】末梢留置カテーテルの“なぜこうする?”
日常的に行う末梢留置カテーテルの穿刺や管理について、それらを「なぜ行うのか」を解説する全13回の連載です。確実な実施のため、根拠とコツをもう1度おさえましょう! 【第1回】高齢、浮腫や肥満がある患者の末梢静脈ルート確保 〈目次〉●高齢、浮腫や肥満がある患者では「皮膚の伸展」などを行ってから穿刺に移行する・ルート確保のコツ①高齢患者の場合には、皮膚を固定しながら針を進める・ルート確保のコツ②浮腫・肥満がある場合は、“血管のありそうな部位”を指で押さえる・ルート確保のコツ③ショック状態の患者の場合は、他の投与方法も検討する・ルート確保のコツ④血管を怒張させるための体位も重要・ルートの固定:適切な長さを設定し、不要な三方活栓は外す 【第2回】ルート確保の基本―穿刺部位・穿刺血管の選択方法 〈目次〉●穿刺部位の選択:患者の可動性を制限しないところを選択する●穿刺血管の選択:「よく見え」「弾力のある」「蛇行していない」血管を選択する●神経の分布部位を避ける 【第3回】急変場面での穿刺部位は肘正中皮静脈が第一選択 〈目次〉●急変場面での穿刺部位は「肘正中皮静脈」が第一選択・急変場面での選択基準は、「確実性」が最も重要・可動性のある部位を選択せざるを得ない場合は皮膚傷害に注意●ルート確保のキホン:“末梢が締まっている”とき、血管確保のために保温してはいけない 【第4回】末梢静脈ルートは上肢でのルート確保が基本 〈目次〉●「どうしても」という場合以外は、上肢でルート確保できる部位をさがす・下肢でのルート確保は、やむを得ない場合にのみ選択される・下肢にルート確保する場合も血管・神経の走行を理解して実施する 【第5回】末梢静脈ルート確保時の駆血のポイント 〈目次〉●ルート確保時の駆血は、「静脈は怒張、動脈は触れる」程度の圧で、1~2分をめやすに行う・駆血は「静脈は怒張、動脈は触れる」程度の圧が最適・駆血時間は神経傷害や皮膚傷害を避けるため、1~2分をめやすに 【第6回】末梢静脈カテーテルの固定方法のポイント 〈目次〉●ルートは刺入部と別に固定し、追加補強を行う・ルートが牽引されたとき、留置針まで抜けてしまうなどの恐れがある・剥がれにくくする固定時の工夫・不穏患者には「ルートを見えなくする方法」も有用 【第7回】末梢静脈ルートの長さのめやすと調節時の注意点 〈目次〉●ルートの長さは患者ごとに適切に設定し、三方活栓はなるべく使用しないことが望ましい・感染・接続外れ予防のため、接続箇所を少なくする 【第8回】末梢静脈からの薬剤投与の際に血管痛を防ぐには? 〈目次〉●血管痛を防ぐためには、「等張液に近い浸透圧の薬剤」を「緩徐」に投与する・血液の範囲を越える pH・高浸透圧の薬剤は、静脈炎・血管外漏出を引き起こす恐れ・末梢からの投与に注意が必要な主な製剤(抗がん剤は除く) ●静脈炎の痛みは「薬剤の浸透圧」「投与スピード」の調整で対応する 【第9回】抗がん剤以外の血管外漏出時は冷罨法を実施する 〈目次〉●抗がん剤以外の血管外漏出時の対応は、「温罨法」ではなく「冷罨法」で行う・薬剤漏出時、カテーテル抜去後の対応として冷罨法を実施する・血管外漏出を引き起こす原因と対策①患者側の原因②薬剤側の原因・血管外漏出後に皮膚傷害を起こしやすい薬剤とその理由③その他の原因 【第10回】薬液が滴下しない原因は閉塞以外にもある 〈目次〉●薬液が滴下しなくなったときに「閉塞」と決めつけず、他の要因も検討する・閉塞時に確認したい「5つの確認ポイント」①患者の体位②関節の屈曲③ルートなどの圧迫と屈曲④血管外漏出や留置針内腔の閉塞⑤粘度の高い薬剤や複数のルートを同時に開放している場合 【第11回】感染管理:末梢留置カテーテルは96時間以上留置できる 〈目次〉●留置期間を延長しても静脈炎・感染の徴候がなければ交換は必要ないと考えられる●ルートの交換は7日以内の実施が望ましい●カテーテル留置期間中は皮膚の状態を毎日観察する 【第12回】末梢留置カテーテル刺入部のドレッシング材の選択 〈目次〉●刺入部が観察しやすい透明なドレッシング材を用い、滅菌されたポリウレタンフィルムで固定 【最終回】末梢留置カテーテルにおける生食ロックの選択 〈目次〉●ヘパリン生食と生食で、ルートの開存や静脈炎発生に差はない●陽圧ロック実施の際は、必ず「生食注入をしながら」シリンジを外す・陽圧ロックの手順 そのほかの連載はこちら
特集記事