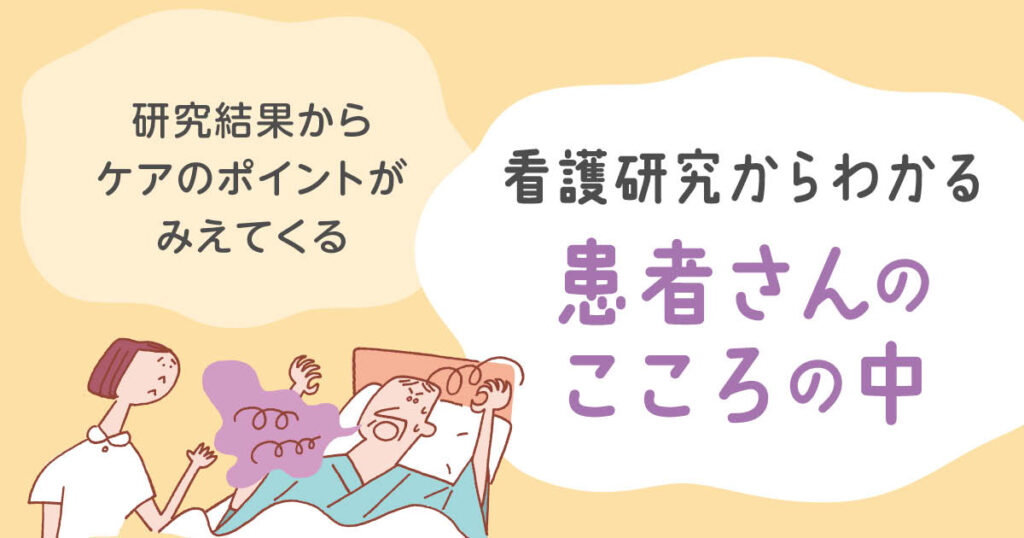患者さんの体験・心理についての「研究」を原著者に紹介してもらい、臨床で活用したいこころのケアを探ります。今回は血液透析を行う慢性腎不全患者さんの気持ちの構造を紹介します。
血液透析患者さんは、どんな気持ちで治療をつづけている?

血液透析療法は、一般的に1回3~4時間、週3回の通院が必要になります。そのため、患者さんは治療時間を確保し、食事・水分の管理、運動療法や薬物療法を行い、よりよい状態で生活が継続できるよう生活を調整することが求められます。
患者さんは、根本的に病気であることを望んでおらず、できれば透析をしない生活に戻りたいと思っています。そのため、知識提供に重点を置く教育・指導だけでは、これまでの生活習慣を変更することは容易ではありません。
透析療法を受けながら患者さんが人生や生活を再構築するためには、その人が生きていることに自他ともに価値を感じ、できるだけ良好な体調を維持しつつ社会生活が継続できることが大切です。
そこで患者さんが自分の気持ちを管理していく、看護師はそれをサポートすることが大変重要です。
ここでは、「血液透析療法を受けながら生活している慢性腎不全患者の“気持ち”の構造」を紹介し1、どのようにしたら患者さんの気持ちをより深く理解できるかを検討します。
本研究は、以下の倫理的配慮のもとに実施されたものです。
●本研究は、研究倫理審査委員会(聖路加看護大学〈現、聖路加国際大学〉)の承認を受けました。
●対象者には口頭および文書で研究目的・方法・参加の自由・拒否や途中辞退の自由・個人情報の保護などを説明し、同意をいただいて実施しました。
●面接時には、精神的心理的な状態に常に注意を払いながら行いました。
研究の方法
疑問(調べたこと)
●慢性腎不全患者さんが血液透析療法を受けながら生活しているなかで、どのような気持ちを抱いているのか?
研究対象
●透析導入1か月~22年4か月(平均7年)までの患者さん19名(男性10名、女性9名)
研究方法
●Carl R.Rogers(以下、C.Rogers)のカウンセリングの理論を枠組みとした
●面接を行い*1、「透析をしながら生活をしているなかで抱いている気持ち」を自由に話してもらう。面接方法はC.Rogersのカウンセラーの3条件(「自己一致」「共感的理解」「無条件の積極的関心」)を満たすように心がけた*2
●面接内容の逐語録と録音を何度も繰り返し聞きながら、“気持ち”の構造を明らかにしていく
*1:この研究では筆者が、C.Rogersの理論に基づく全日本カウンセリング協議会認定2級カウンセラーの資格を有し、Person-Centered-Approach国際フォーラムへ複数参加していることから、本研究での面接者の質の保証とした。
*2:C.Rogersは、『人の経験と自己概念(私らしさ)が一致することにより、個人がその人らしく自己実現の方向に向かうとしている。そして、そのような状態は、「自己一致(自分自身の経験に正直であり統合されていること)」「共感的理解(あたかも相手になったかのように相手の気持ちを受け取り理解していること、それを伝えること)」「無条件の積極的関心(相手がどのような条件にあっても、独自の存在として尊重して関心を寄せること)」という3条件を備えた他者(カウンセラー)とのかかわりのなかで促進される』2,3としている。
発見:患者さんの“気持ち”と“気持ち”を構成する3つの要素と構造
透析患者さんは「“私らしさ”のありよう」と「感覚的経験」を同時に経験している
この記事は会員限定記事です。