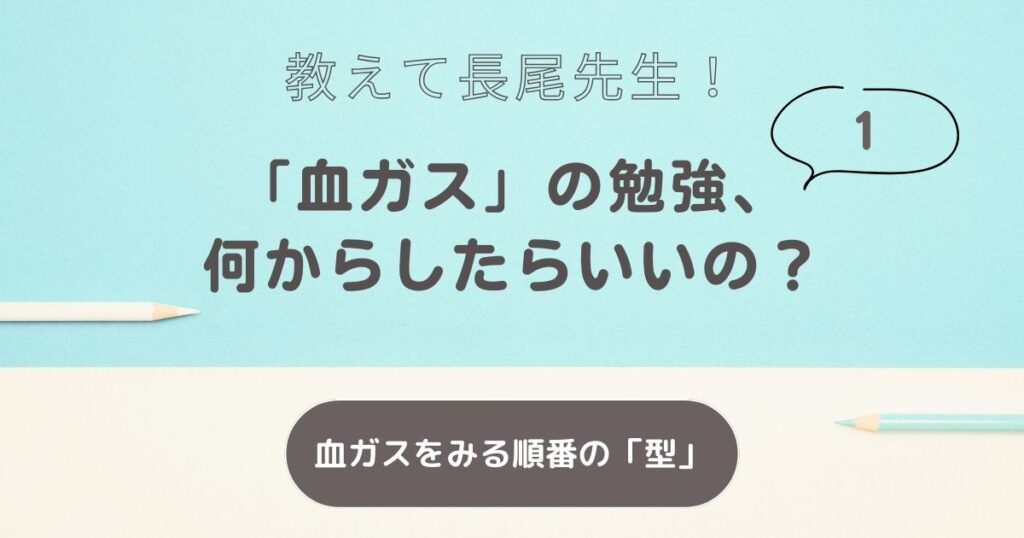動脈血液ガス分析(血ガス)の“ここだけ”おさえたいポイントを、会話形式でわかりやすくレクチャーする全5回の連載です。「やり直したいけれど、何から勉強したらいいのかわからない……」という人は注目です!
【第1回】血ガスの基準値とみる順番を覚える!
用語が多く、難しいと思いがちな血ガス。理解するポイントは、「正常からどうはみだしているか」です。まずおさえておきたい、「みる順番」とは?
〈目次〉
●私たちが血ガスを“ややこしい”と感じる理由
●血ガスの型を覚えれば、 そんなに難しくない!
【第2回】血ガス「pH」の基準値と異常値
そもそも、なぜ医師は血ガスをとりたいのでしょうか。その理由を知れば、血ガスの“みかた”が覚えやすくなります。「アシデミア」と「アルカレミア」についても知っておきましょう。
〈目次〉
●なんのために血ガスをとるの?
●pHの異常を表す言葉:「アシデミア」と「アルカレミア」
・pH(水素イオン濃度)のポイント
【第3回】血ガス「pH」を異常にしている原因は?「PaCO₂」編
pHの変動に影響を与えるのが「CO2」と「HCO3-」。動脈血の中の二酸化炭素の値である「PaCO2」についてみていくと、pHの異常には2つのパターンがあります。
〈目次〉
●「pH」を異常にしている原因は?
●パターンA.アシデミア(pH<7.35)で、PaCO2が増えている
●パターンB.アルカレミア(pH>7.45)で、PaCO₂が減っている
・PaCO2(動脈血二酸化炭素分圧)のポイント
【第4回】血ガス「pH」を異常にしている原因は?「HCO₃-」編
「HCO3-」つまり重炭酸イオンの観点から、pHの異常の原因を探ります。それには、「代謝性アシドーシス」「代謝性アルカローシス」の原因を考える必要があります。
〈目次〉
●「pH」を異常にしている原因は?
●パターンC.アシデミア(pH<7.35)で、HCO3-が減っている
●パターンD.アルカレミア(pH>7.45)で、HCO3-が増えている
・HCO3-(重炭酸イオン)のポイント
【最終回】血ガスをみるために大切な呼吸回数と治療の方向性
日ごろから大事なのが、呼吸回数の測定。また、血ガスの値をアセスメントしていくだけで、最終的には「どんなところに原因があるか、どういう方向性で対応したらよいのか」までわかります。
〈目次〉
●血ガスをみるべき状態を判断するには、「呼吸回数」を測定!
●方向性をイメージしてアセスメントしよう