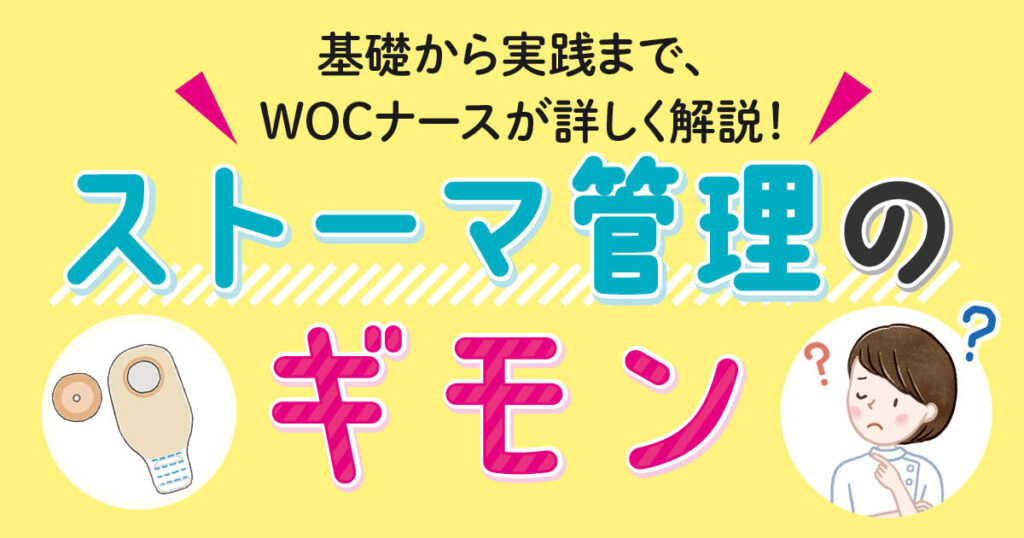ストーマについての「これだけは知っておきたい!」という“基礎のギモン”から、現場から寄せられた“実践的なギモン”までをWOCナースが解説する全30回の連載。どの病棟でも出合うストーマ患者さんのケアに活かせます。
【第1回】ストーマサイトマーキングを行う意味は?
〈目次〉
●術後の合併症の予防、ストーマ装具装着の安定性を高めることができる
●マーキングによって患者さんの今後が変わることを意識する
【第2回】待機手術のマーキングのポイントは?
〈目次〉
ポイント1 ストーマサイトマーキング前の確認事項
ポイント2 ストーマ種類別造設位置の考え方
・ストーマ造設の基本的な位置と便の状態
・ストーマの種類
ポイント3 ストーマサイトマーキングの基準
【第3回】待機手術のマーキングの手順は?
〈目次〉
●ストーマサイトマーキングの手順
●体型による考慮点
●ストーマサイトマーキングの評価
【第4回】腹直筋がわかりにくいときの対処
〈目次〉
●CTもしくはエコーを使用して、腹直筋を確認
【第5回】ストーマ周辺観察のポイント
〈目次〉
●ストーマ造設後は「ストーマ粘膜部」「ストーマ粘膜皮膚接合部」「ストーマ周囲皮膚」の領域を観察
・粘着式ストーマ装具周辺の名称
・部位別の合併症について
【第6回】ストーマ壊死、ストーマ浮腫の観察ポイントと対応
〈目次〉
●代表的な合併症の症状や原因、対応をチェック
●ストーマ壊死
●ストーマ浮腫
【第7回】ストーマ出血、ストーマ創感染、ストーマ粘膜皮膚接合部離開の観察と対応
〈目次〉
●ストーマ出血
●ストーマ創感染
●ストーマ粘膜皮膚接合部離開
【第8回】皮膚障害の観察ポイントと対応
〈目次〉
●皮膚障害
・皮膚障害までには至っていないが、注意が必要な状態
【第9回】ストーマ脱出、傍ストーマヘルニアの観察ポイントと対応
〈目次〉
●ストーマ脱出
●傍ストーマヘルニア
【第10回】ストーマケア用品の種類とストーマ装具の分類
〈目次〉
●「①装具交換時に必要」「②装具の安定性を高める」「③トイレに行く回数を減らす」「④管理のしやすさを向上させる」の4つの観点で分類
●ストーマの種類と「粘着性」の意味について
・粘着性ストーマ装具の分類
・ストーマ袋の構造
【第11回】ストーマケア装具の構造や素材による違い
〈目次〉
●構造に「追加の内容」「素材による違い」がある
・面板の高さの違いについて
【第12回】患者の個別性に応じたストーマケア用品の使い分け
〈目次〉
●選択基準を参考にしながら、実際の患者さんの状態と照らし合わせて決定
●皮膚が弱い(テープにアレルギー反応がある)患者さんでの選択
【第13回】水様便が続く場合の装具の選択
〈目次〉
・メーカー別凸面型装具の凸部の高さ
【第14回】ストーマ造設直後や合併症を起こした場合などでの装具選択
〈目次〉
①ストーマを造設した直後の患者さんでの装具選択は?
②ストーマの形が正円でない患者さんでの装具選択は?
③ストーマ合併症(浮腫、壊死)を起こした患者さんでの装具選択は?
【第15回】ストーマ造設患者のセルフケア項目と装具交換の指導
〈目次〉
●ストーマ造設患者のセルフケア項目
●装具交換の指導を行うために看護師に必要な知識・技術
●手術前から収集しておくべき患者情報
【第16回】ストーマ抜糸は必ず行ったほうがよい?
〈目次〉
●縫合部分に炎症が起きていない場合の抜糸は不要なこともある
・表皮剥離を起こした状態
【第17回】円背での皮膚トラブルの対処法
〈目次〉
●円背のある患者さんについて、テープで押さえているが皮膚トラブルが続く場合は?
・姿勢を見て、面板の選択やケア用品の追加を判断する
【第18回】がん薬物療法中の皮膚トラブルへのケア
〈目次〉
●保湿剤などの見直しと、副作用によっては治療も必要
・免疫関連副作用(iAE)の発疹
【第19回】ストーマ造設後の便秘への対応
〈目次〉
●基本的には通常の患者さんの便秘時の対応と同様
【第20回】浮腫を起こしやすい食事とは?
〈目次〉
●塩分や飲酒などが代表的、過量な飲酒も原因に
【第21回】パウチ取り替えの際に便をこぼす場合はどうする?
〈目次〉
●ケアの時間を調整して食直後を避けることが大前提
【第22回】ストーマを緊急造設する場合とは?
〈目次〉
●消化管穿孔や腸間膜動脈閉塞症などの場合がある
・ストーマ造設のパターン
【第23回】緊急時のマーキングの必要性と注意点
〈目次〉
●マーキングを行わないと装具を安定して貼付できなくなる場合がある
・緊急時は、腹壁が通常とは異なる
・平常時のストーマサイトマーキングの一例
・緊急造設時のストーマサイトマーキングの一例
【第24回】緊急造設時のストーマ合併症の危険性
〈目次〉
●ストーマ合併症の重症度が高く、合併症の種類も多い
・正中創の感染によって陰圧閉鎖療法がおこなわれている一例
・ストーマ早期合併症の重症度と背景因子、手術因子の関連
・ストーマ合併症の用語の定義とグレード分類
・患者さんの心を知ることからケアがスタート
【第25回】在宅でのストーマ管理への指導
〈目次〉
●セルフケアに向けて早期の指導、家族や同居人のストーマへの理解が大切
・在宅に向けたストーマ管理への指導内容
①装具選択、交換方法の決定
②家族指導について
③継続的なフォロー
④パンフレットや教育コンテンツの活用
【第26回】ストーマ装具からの漏れの原因と対応~ストーマ管理
〈目次〉
●装具が合っているかチェックする必要がある
【第27回】ストーマ装具交換時の漏れへの対応
〈目次〉
●事前の準備、第三者の手伝いがポイント
①排泄物をすぐに拭き取る準備をする
②タンポンガーゼを準備する
③装具はすぐに貼付できるように、あらかじめ準備をしておく
④第三者の手を借りる
【第28回】在宅療養者のストーマ装具からの漏れへの対処法は?
〈目次〉
●「必殺技」はないため、そのたびに原因を探ってケアを見直す
【第29回】パウチの付きが悪い場合はどうする?
〈目次〉
●患者さんの肌の状態に原因があるかも。日常ケア用品の見直しを検討しよう
・保湿剤入りの清拭洗浄剤・泡状石けんの例
【最終回】コロナ禍を経て知っておきたいストーマケアでの感染対策
〈目次〉
●自己管理ができるかの確認が大切
・感染予防のポイント