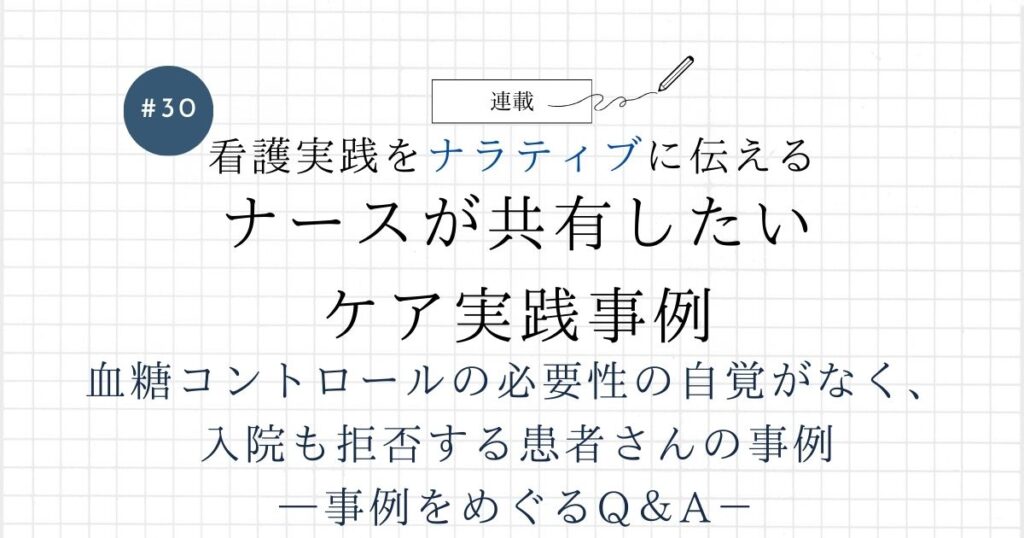事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は血糖コントロールの必要性の自覚がなく、入院も拒否する患者さんの事例をめぐるQ&Aを紹介します。
今回の事例:【第29回】入院治療を拒否する糖尿病患者への看護介入
〈目次〉
慢性疾患看護専門看護師として大切にしていることは?
初対面でAさんの手に注目したのはなぜ?
外来でのインスリン導入を判断した理由は?
手洗いや爪切りのケアにどんな期待があった?
事例をめぐるQ&A
慢性疾患看護専門看護師として大切にしていることは?
米田 永渕さんが慢性疾患看護専門看護師として臨床で大切にしていることは何でしょうか?
永渕 糖尿病などの慢性疾患の療養は、患者さんの日々の生活の中で行われます。私は、療養方法の「指導」ではなく、患者さんの生活と療養が調和できるように「支援」するという意識をもって、日々の看護を実践しています。
“患者さんがどのような生活を送られているのか”“生活をするうえで何を大切にされているのか”“これからどんな生活を送りたいと思われているのか”をお聞きするように心がけ、病気の管理ではなく、患者さんの生活に視点をもつことを大切にしています。
初対面でAさんの手に注目したのはなぜ?
米田 なぜ初めてお会いしたとき、Aさんの「長く爪が伸びた汚れた手」に着目したのですか?
永渕 人の手には、その人の生活が現れます。どのような生活をされているのかを読み取る1つの手段になります。力仕事をされる方であればマメができていたり、力強い手をされています。屋外の作業をされる方は日焼けをしていますし、主婦の方でしたら手荒れをされていたりします。
つまり、その人の手を切り口にして、生活の聞き取りに進むことができます。これは、私のこれまでの看護師としての経験から学んだものです。そのため、Aさんの手に着目したのだと思います。
外来でのインスリン導入を判断した理由は?
米田 永渕さんが、この患者さんはインスリン療法の外来導入が可能であると判断した理由を知りたいです。
永渕 正直なところ、私も少し不安な面はありました。しかし、このご夫婦がこれまでかかりつけ医の通院を継続されていたことや、ご主人が治療の必要性を理解されご自分たちの生活で実行可能な方法を考えて意思表示をされましたし、何よりもお2人の面談中の視線や会話のやりとりからご夫婦の絆の強さを感じました。
そのため、このお2人であれば、外来でのインスリン導入も協力して取り組むことが可能ではないかと考えました。
この記事は会員限定記事です。