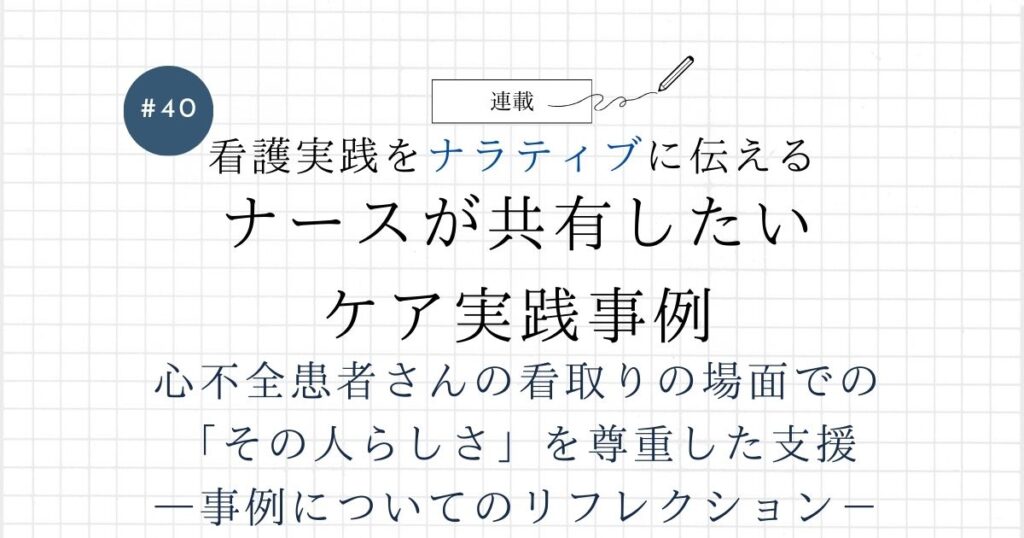事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は心不全患者さんの看取りの場面での「その人らしさ」を尊重した支援を振り返りながら、別角度から、ナースの“思い”について分析します。
今回の事例:【第38回】心不全患者の終末期における「その人らしさ」を尊重した看護介入
〈目次〉
“気づき”から始まるエンド・オブ・ライフケア
エンド・オブ・ライフケアと看護師の倫理
事例についてのリフレクション
“気づき”から始まるエンド・オブ・ライフケア
読者の皆さんはこの戸田さんの事例をどのように受け止められたでしょうか。
ある人は「患者さんへのメンタルケア」、またある人は「苦痛緩和」、またある人は「意思決定支援」「家族ケア」……さまざまな角度で捉えることができる事例です。
戸田さんはAさんとのかかわりのなかで“自分が生きていることで迷惑をかける”という言葉から、自分の存在価値を問うスピリチュアルな苦痛に気づきます。
苦痛には「身体」「心理」「社会」「スピリチュアル」の4側面が存在すると言われています。
QOLの指標にもなるこの4側面に、患者さんの言動から“気づく”ことがこの介入のスタートラインとなっており、この介入がエンド・オブ・ライフケアということになります。
エンド・オブ・ライフケアと看護師の倫理
エンド・オブ・ライフケア(EOLケア)は、死別時のケアのみでなく、患者や家族、医療者が「死」を意識したときからスタートすると定義されています1。ケアとしては、苦痛や症状の緩和、意思決定支援、患者さんやご家族とのコミュニケーションなど複合したケアが含まれます。
この介入には戸田さんだけでなく、担当医や病棟看護師がチームとなって取り組み、Aさんが望む最期や家族が考える看取りについて、一緒に迷い、考える様子が記述されています。
この記事は会員限定記事です。