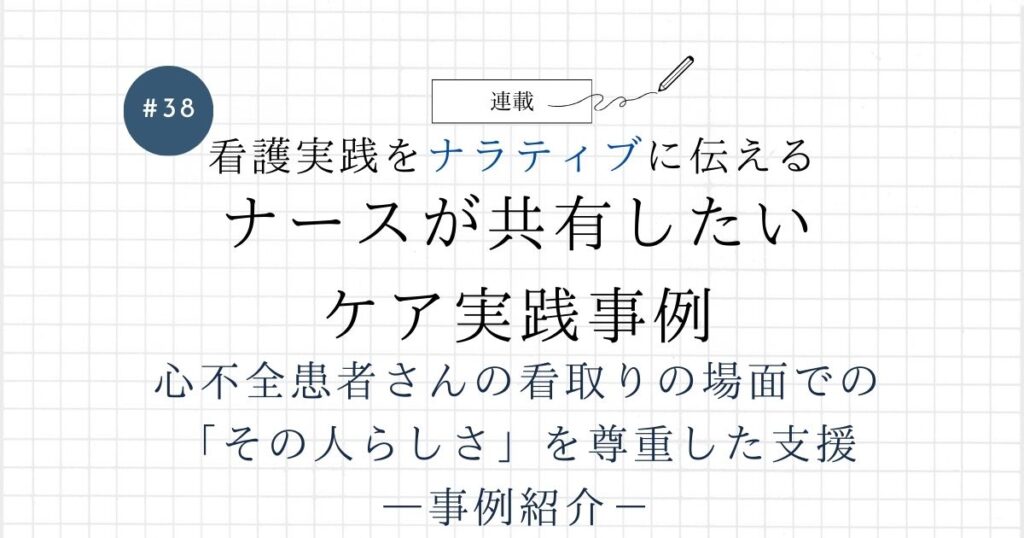事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は心不全患者さんの看取りの場面での「その人らしさ」を尊重した支援についての事例を紹介します。
〈目次〉
心不全により死を意識したAさんの思い
エンド・オブ・ライフをチームで支える
患者さんが家族と過ごす最期の時間:看取りのケア
心不全患者さんの看取りの場面で「その人らしさ」を尊重して支援できること
60代男性患者のAさん。独居で、遠方に兄家族がいます。
2007年に急性心筋梗塞を発症し、広範囲前壁梗塞でIABP(大動脈内バルーンパンピング)装着のもとPTCA(経皮的冠状動脈形成術)を施行しました。退院時の左室駆出率は25%程度で、重度の左室機能不全がありました。
外来で定期検査と内服調整をしていましたが、徐々に心拡大と左室駆出率の低下を認め、低心拍出量症候群および右心不全でCCUに入室しました。
心不全により死を意識したAさんの思い
CCUでは、肺動脈カテーテルを挿入し、強心薬と肺血管抵抗を下げるための硝酸薬が開始になりました。
入室2日目、受け持ち看護師からAさんが死を察知していること、家族とは疎遠であり今後の意思決定をどうすればよいか悩んでいることについて、私に相談がありました。
Aさんは、「私が生きることで迷惑をかけ、人がつらい思いをしてしまうことになるのならば死んだほうがいいのではと思います。よくなるのであれば治療は受けたいと思います」と言いました。
主治医と受け持ち看護師、私は対応について検討し、まずは主治医に電話で兄家族へ病状説明をしてもらうとともに、“来院は可能か”“どこまでサポートができるのか”を確認してもらいました。
兄家族からは、“来院はできない”“医師がよいと思うことをしてほしい、可能な限り患者の意思を尊重してほしい”“いつでも連絡はしてよい”という返事がありました。
また、Aさんはスピリチュアルペインを抱えており、看護師は苦悩に寄り添う必要があることを確認し、実践しました。
エンド・オブ・ライフをチームで支える
1)意思決定支援
その翌日、Aさん自身に現状と今後の治療について、急変時にどのような救命措置を希望するかについて説明をしました。
Aさんの心理的負担が強くならないように、兄家族の返事の内容について伝えながら、急変時対応については決断をすぐにしなくてもいいことを説明しました。
Aさんの意思決定ができるまでは兄家族の代理意思決定が適切であると判断し、医療者間で共有しました。
その後、心不全は軽快し、一般病棟に転床しました。主治医とAさんは話し合い、侵襲的な治療はせず、退院後は兄家族の元に転居する予定にしていました。Aさんは定期的に兄家族と連絡を取り合っていました。
1か月が経過したころ、退院の日にちは決まっていましたが、食欲不振と意欲低下がありました。食事や水分摂取ができなくなり、内服困難になったことから、再度、低心拍出量症候群になり、CCUへ入室することになりました。
主治医からAさんには、心臓のポンプ機能が徐々に落ちており、CCUに入れば今度は退室できないかもしれないと説明がされました。Aさんは納得のうえ、CCUへの入室を希望しました。
入室後、前回と同様に肺動脈カテーテルを挿入し、強心薬と硝酸薬を開始しました。Aさんと話をしたうえで兄家族に連絡をとり、DNARの方針になりました。
2)医療チームの合意形成支援
患者さんの治療と看護ケアの方針については、複数にわたって主治医と受け持ち看護師、リーダー看護師とで話し合い、医療チームで合意ができるように調整しました。
薬物治療は限界まで行っていること、CRT(心臓再同期療法)は現状では手術リスクが高くてできないこと、年齢的に心臓移植の適応はないこと、末期心不全であり補助循環装置の装着の適応はないことを医療チームで共有しました。
その結果、基本的な方針として、患者さんのQOLを重視し、患者さんの希望に沿った治療と看護ケアを行うことにしました。
3)苦痛緩和
胃管を挿入しましたが、不快感が強く、Aさんの意向で抜去しました。
呼吸困難症状が出現したため、Aさんと兄家族の同意のもと、モルヒネの持続投与を開始しました。しかし、モルヒネ開始の翌日にはせん妄症状が出現し、危険行為が増えました。主治医に相談し、鎮静薬としてデクスメデトミジンを開始しました。
兄家族はAさんのことをとても気にかけており、週末には来院できるという返事がありました。主治医と検討し、来院までは極力、言葉が交わせるように調整をすることとし、看護師間で情報共有をしました。
また、看護師が鎮痛と鎮静の調整に迷いを感じていたため、Aさんの呼吸困難とせん妄の症状の違い・薬剤の調整方法を電子カルテ上に記載し、判断に困らないようにしました。 週末の兄家族の来院まではモルヒネで呼吸困難症状を緩和し、せん妄の危険行為に対しては最小限の鎮静薬を使用することができました。
患者さんが家族と過ごす最期の時間:看取りのケア
主治医から兄家族に、死期が差し迫っているため、可能な限り早く来院してもらうように連絡をしました。兄家族の来院後、Aさんは会話をすることはできませんでしたが、個室の病室で一緒に過ごすことができました。
主治医から、兄家族は仕事の都合があり、長くても月曜日に帰るつもりであること、肺動脈カテーテルから滲出液が多量に出ており抜去のタイミングを考えないといけないことについて、私に相談がありました。抜去すれば同時に薬剤をすべて止めるつもりであるが、その選択をしてもよいのかという相談でした。
家族の同意があれば、それは可能であることを伝えました。兄家族に状況を説明し同意が得られたため、肺動脈カテーテルは抜去しました。
私は病室内で過ごしている兄家族と話をしました。Aさんは天涯孤独と思っていたようですが、兄家族はいつでも帰ってきていいと話していたこと、前年の夏にはAさんが遊びに行き、とても楽しく過ごしていたことを教えてもらいました。
私は兄家族に遠方から来院してAさんと過ごしてくれていることに感謝の気持ちを述べ、Aさんもとてもうれしがっているであろうと伝えました。
また、Aさんのことについて他愛もない会話をし、兄家族がAさんと穏やかな気持ちで接することができるように、場の空気をつくるようにしました。
兄家族から“小康状態であれば一度帰りたい”という申し出がありましたが、主治医と検討をし、採血結果で判断することにしました。
著明なアシドーシスの進行を認めていたため、そのまま待機してもらうと、間もなく呼吸が停止し、血圧が下がるとともに心拍も停止しました。
兄はその際「一緒に帰ろうな。もう何も考えなくてもいいから、一緒に帰ろう」と声をかけていました。私たちは兄家族が見守るなかで、死亡確認をしました。
※この記事は『エキスパートナース』2017年1月号特集を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。