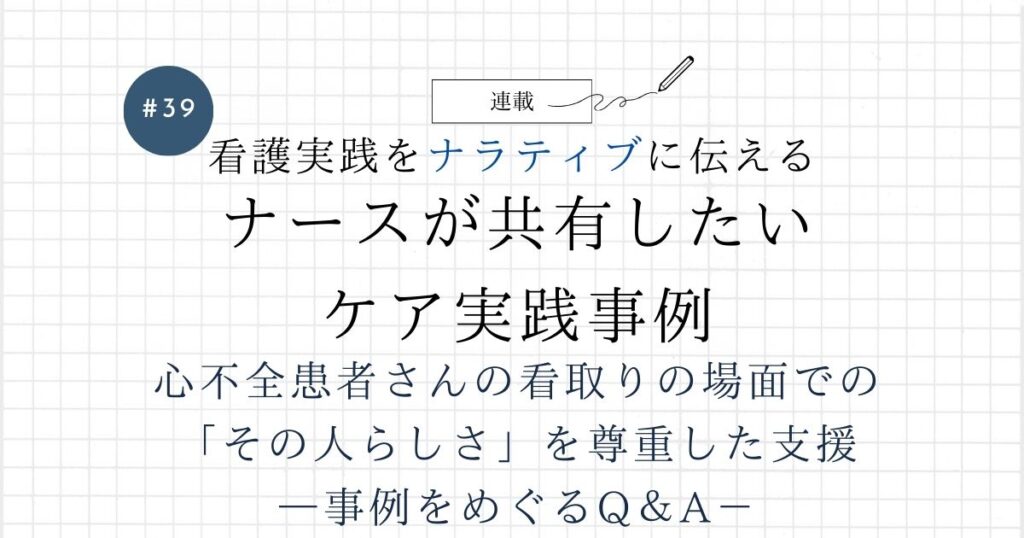事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は心不全患者さんの看取りの場面での「その人らしさ」を尊重した支援をめぐるQ&Aを紹介します。
今回の事例:【第38回】心不全患者の終末期における「その人らしさ」を尊重した看護介入
〈目次〉
スピリチュアルペインがあると感じた理由は?
エンド・オブ・ライフ(EOL)ケアにチームでどう取り組んだ?
どんな理論をもとに意思決定や代理意思決定を支援した?
EOLケアは何からスタートする?
事例をめぐるQ&A
スピリチュアルペインがあると感じた理由は?
宇都宮 Aさんにスピリチュアルペインがあると戸田さんは最初に感じられたのですが、それはAさんのどの言動からでしょうか?
戸田 「私が生きることで迷惑をかけ、人がつらい思いをしてしまう」という言葉です。これは“自律存在に由来するスピリチュアルペイン”を意味していると感じました。
自律存在に由来するスピリチュアルペインとは、自分が自律した人ではなくなることに関する苦悩、つまりは人としての存在価値がなくなったと感じることを含みます。
この場合、「そのような苦しみを感じているのですね」と、患者さんの苦悩に寄り添うことが必要になります。
エンド・オブ・ライフ(EOL)ケアにチームでどう取り組んだ?
宇都宮 チームでエンド・オブ・ライフ(EOL)ケアを行うということを戸田さんは考えられましたが、チームのなかで、どのようにそれを共有していきましたか?
戸田 つね日ごろから、主治医や受け持ち看護師との1対1でのコミュニケーションを大事にしています。そこで、主治医の基本的な考え方を理解し、受け持ち看護師から患者さんに関する細かな情報を得ます。加えて、私自身も患者さんに介入しながら情報を得ます。
これらの患者さんにかかわる情報を集積し、即時性の必要な内容についてはベッドサイドカンファレンスを行い、記録に残していきました。
この記事は会員限定記事です。