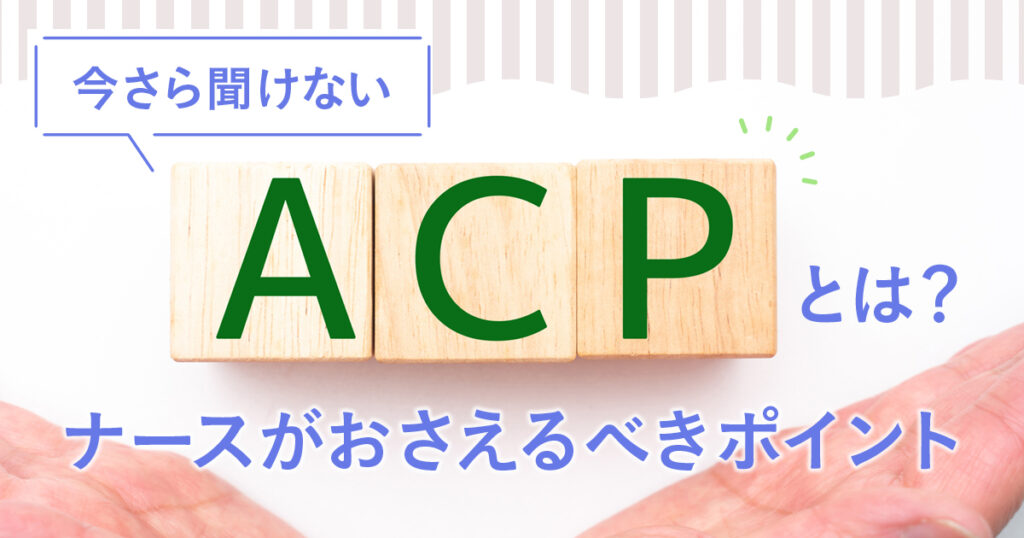病院で慢性疾患(心不全)をもつ患者に行うACPのコツを紹介。ACPに対する心不全患者さんの心理や、ACPの進め方、話し合いの時期の決め方などを事例を交えて解説します。
心不全におけるACPの重要性
心不全は、がんと同様あるいはそれ以上に不良な予後を有しながらも、患者さんならびに医療者において、その認識は乏しく1、客観的に予測される余命よりも患者さん本人が考えている余命のほうが長い1と報告されています。このようななかで医療者は、患者・家族の希望が明らかになっていないと、救命という選択肢を提示する傾向にある1とも言われています。
やはり私自身、実際の現場でこのような状況を経験することがあります。しかし近年は、このような状況を変えようと日々チームで悩みながらかかわっている医療者が増え、ACPや緩和ケアに関してさまざまな学会でディスカッションする場面も多くなってきました。
ACPに対する心不全患者の心理は?
前述した通り循環器領域では、緩和ケアやACPに対して積極的に検討する施設が増えてきました。一方で医療者は、“心不全患者にACPをしなければいけない”という思いが強くなり、患者さんの心理状態を考えずACPを進めてしまうことがあります。
ある患者さんは、医療者の一方的なACPがつらすぎて転院して来られました。転院して来られたころの患者さんは、医療者への不信感と身体的・精神的苦痛を抱えてQOLも低下していました。じつは、心不全を発症したあと約15年の間で再入院がなく、入院した時点でステージDと診断され、現実を受け入れられないなかで意思決定を突きつけられている状況でした。
本来は、患者さんが病状を受け入れながら揺れ動く気持ちに寄り添って“待つ”ことも大切なかかわりになります。また、病状と患者さんの心理状態に合わせながら、協働的意思決定(shared decision‐making:SDM)*モデルを活用した話し合いが必要です。
*【協働的意思決定】患者と医療者が情報共有を行い、話し合いを重ねて意思決定を行うこと(インフォームド・コンセントは医療者側の情報提供の側面が強く、SDMと言えない場合もある)。
心不全患者におけるACPの進め方は?
再発予防に対する療養指導は、ACPの一環であると考えています。心不全は、疾患を抱えながら長い療養生活を送ります。そのため患者さんは、自分が抱える疾患と向き合い、どのように折り合いをつけながら生活をしていくかが重要となります。
このとき必要なことは、医療者が患者さんに対して、疾患と向き合うために病状について適切な説明を行うことです。さらに患者さんは、病状を理解したうえで、「大切にしたいこと」「譲れないこと」「そのために何をするのか」「病状に合わせて生活をしていくために折り合いをつけながら、どのように生活をしてくのか」を、医療者と一緒に考えていきます。
このプロセスは、病気の節目(再入院のタイミングなど)や暮らしづらさを感じた時などに、繰り返し行っていきます。
心不全患者へのACP支援の事例
私がかかわった別の患者さんは、15年前に冠動脈バイパス術(CABG)を実施しましたが、その後も経皮的冠動脈インターベンション(PCI)を繰り返していました。
もちろん、心不全増悪による再入院の頻度は増え、「おおむね年間2回以上の心不全入院を繰り返し、有効性が確立しているすべての薬物治療・非薬物治療について治療ないしは治療が考慮されたにもかかわらずニューヨーク心臓協会(New York Heart Association:NYHA)心機能分類Ⅲ度より改善しない」とガイドライン2で定義される、いわゆるステージDに近い状態となっていました。
患者さんは、再入院のたびに医療者と一緒に“今の病状”“これからたどる過程”“患者自身が譲れないことを踏まえた療養生活”について話し合ってきました。そのため患者さんと医療者は、長い療養生活のなかで信頼関係を築くことができており、“終末期を迎えた時にどのように過ごしたいか”を含めてネガティブにとらえず話し合うことができています。
紹介した患者さんは、「動けるうちは仕事もしたいし、趣味の釣りにも行きたい。しかし、家族に負担をかけたくないため、心臓移植の選択はしないが、それ以外でできる治療を選択したい。それでも症状が取りきれない場合は、苦痛を取る治療を並行して行ってほしい。そのタイミングがきた時には、必ず自分に伝えてほしい」という希望を語っておられます。
この記事は会員限定記事です。