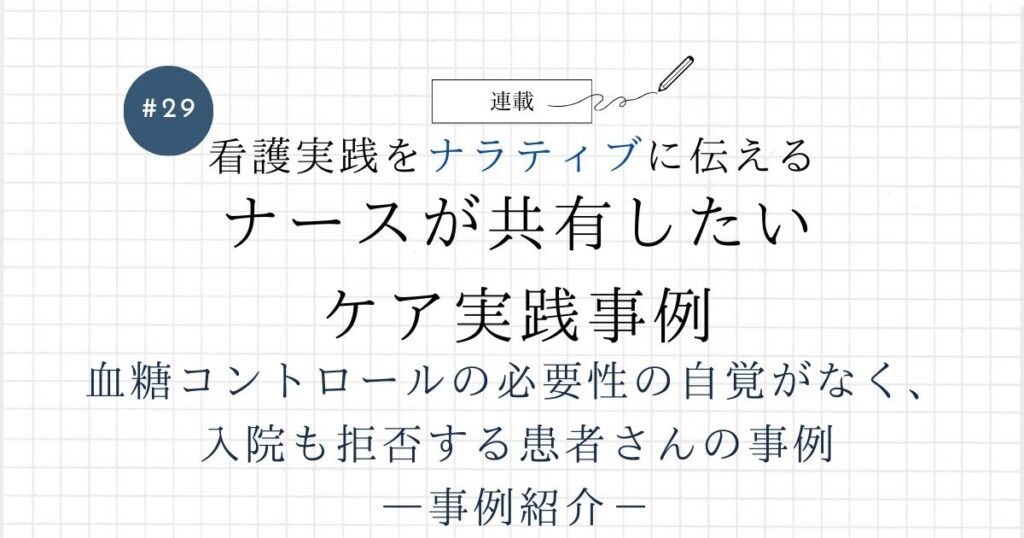事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は血糖コントロールの必要性の自覚がなく、入院も拒否する患者さんの事例を紹介します。
〈目次〉
血糖コントロールの必要性の自覚がなく、入院も拒否する患者さんの“変化のきっかけ”
「入院での治療は無理」と語る夫とAさんの状況
外来でのインスリン導入。しかし高血糖状態・体重増加は続く
フットケアの継続で起こった変化
血糖コントロールの必要性の自覚がなく、入院も拒否する患者さんの“変化のきっかけ”
Aさん、50歳代、女性。ご主人と2人暮らしをしています。
5年ほど前より2型糖尿病の指摘を受け、内服薬での治療を継続していましたが、血糖コントロール不良の状態が持続し、コントロール改善のために私の勤務する病院を紹介され、受診されました。Aさんにはうつ病もあり、精神科にも通院されています。
初回の外来受診で、Aさんは車椅子に乗り、ご主人とお2人で外来を受診されました。
看護師の質問に対しても返答が少なく、うつろな表情でうつむき、今にも眠ってしまいそうでした。手の爪は長く伸び汚れており、肩まで長く伸びた髪は乱れていましたが、気にする様子はないように見受けられました。
AさんのHbA1cは12%と非常に高く、尿中ケトン体陽性であり、早急なインスリン注射導入による血糖コントロールが必要な状況でした。
そこで、Aさんとご主人に対して医師より、“このままでは高血糖によるさまざまな障害が起こり、命にかかわる事態になる可能性も高く危険であること”“改善のためには入院によるインスリン導入が必要であること”の説明が行われました。
Aさんはご主人のほうを見つめ、不安そうな表情で涙を流し、ご主人からは「入院はできません。外来での治療はできませんか?」と入院治療を拒否されました。
「入院での治療は無理」と語る夫とAさんの状況
私は、Aさんとご主人が入院治療を拒否される原因に何があるのだろうかと気になり、お2人に語りかけました。
私 「Aさん、急に入院と言われてびっくりされましたね。入院して治療を受けることは難しいですか?Aさんが治療を受けることに対してどう思われているのか、教えていただけませんか?」
Aさん 「お父さん(夫)が一緒じゃないと怖い」
夫 「いつも一緒にいるから、私がいないとダメなんです。不安になるみたいで。だから入院だったら付き添わないと無理だと思います。……ここの病院では付き添いはできませんよね」
私 「個室に入院できれば、付き添うことも可能です。ただし、個室の料金が別にかかってしまいますし、重症の患者さんが優先となります」
夫 「入院費用もかかるし、経済的に余裕がないので、個室の入院はできません。外来に連れてくることはできるので、外来でインスリンの治療をしてもらえませんか?」
私 「ご主人は外来での治療をご希望ということですね。Aさんはどうですか?」
Aさん 「お父さんと離れたくないから、私もそっちがいいです」
私 「Aさんもご主人も、外来でのインスリン注射の開始を希望されるということですね。今のAさんの身体にとってインスリンは生きていくうえで非常に大切なものです。もし外来での治療でうまくいかない場合は、入院が必要になると思います。Aさんとご主人ができるだけ一緒に生活できるように、外来でのインスリン注射をがんばって一緒にやっていきましょう」
─私は、Aさんはご主人のサポートを受けることで、生活を送ることができていると感じ、Aさん夫婦が希望される外来での治療がAさんにとっては最もよい治療環境ではないかと考えました。
外来でのインスリン導入。しかし高血糖状態・体重増加は続く
私はAさん夫婦の希望と、“Aさんの心理状態では夫と離れての入院生活は困難と考えられる”ということを医師へ伝え、外来でのインスリン療法が開始されました。
指導の際、Aさんに注射器に針をつけてもらいましたが、手の動きが緩慢でうまくつけることができず、Aさん自身も“自分の体に針を刺すのは怖い”と言い、インスリン注射を自分ですることを拒否されました。
そこでご主人にインスリン注射の手技指導を行いました。指導の間も、Aさん自身は興味を示されず、注射から目を逸らし、眠たい様子でうつらうつらされていました。
このように外来受診による1日2回のインスリン注射療法が開始され、ご主人は毎日のインスリン注射と血糖値の測定を欠かさずにAさんに実施されました。しかし、血糖値はなかなか下がらず、Aさんの体重はどんどん増加していきました。
血糖値が改善しない原因として、間食が多いという問題がありました。しかし、Aさんに間食を控えるように説明しても、なかなか改善されない状況でした。
私は、これまでのAさんの状況から、Aさんは自分の身体の状況に関心がないので、説明だけでは、Aさんの行動が変わることは難しいのではないかと考えました。 そこでAさん自身が自分の身体に関心をもつことができるように支援することを始めました。
フットケアの継続で起こった変化
Aさんの足には爪肥厚があり、神経障害からの下肢痛も訴えていました。自分の身体への関心をもつための支援として、私が直接Aさんの身体に触れることではたらきかける“フットケア”を行うこととしました。
私はフットケアの時間を利用して、Aさんの手をきれいに洗い、爪を切り、伸びた髪の毛もきれいに結いました。
Aさんに「とてもきれいになってすっきりしましたね。髪型もかわいくなって、若返りましたよ」と少し冗談を交えて伝えました。Aさんは大きな声で笑い、うれしそうにきれいになった手を触っていました。次にAさんへ、足浴や爪切りなどのフットケアを実施しました。
私は、ケアが終了したあとにAさんに、ケアした部分に触れて確認するように促し、「きれいになりましたね。どうですか?」と問いかけました。このようなフットケアを月に一度、半年ほど継続しました。
7回目のケアのとき、Aさんから「お父さんに毎日注射してもらっているけど、なかなか血糖値が下がらない。血糖値はどうしたらよくなるの?」という質問がありました。
私はAさんの行動変化の契機が訪れたと判断し、血糖値と間食やジュースなどの関連を説明しました。そのあとから、Aさんはジュースをお茶に変えるようになり、しだいに血糖値も改善していきました。
私はAさんに、「Aさんが血糖値を下げたいと思ってお茶に変えられたことで、血糖値が下がりましたね」と伝え、このことを継続するように説明しました。
Aさんからは「気をつければ、血糖値も下がるのね。お茶は続ける」という言葉が聞かれ、ご主人も「ジュースをお茶にしたのがいいみたいですね。続けるようにします」とご夫婦で血糖コントロールに取り組まれるようになり、血糖値も安定しました。
※この記事は『エキスパートナース』2016年10月号特集を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。