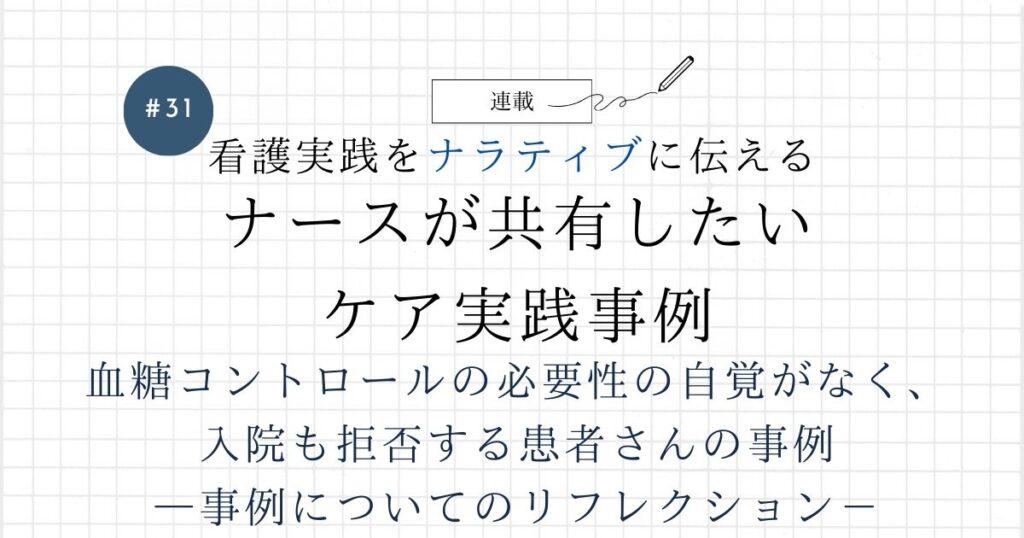事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は血糖コントロールの必要性の自覚がなく、入院も拒否する患者さんの事例を振り返りながら、別角度から、ナースの“思い”について分析します。
今回の事例:【第29回】入院治療を拒否する糖尿病患者への看護介入
〈目次〉
患者さんのことをよく見て、決めつけず解釈をしつづける
患者さん・家族の回復していく力を信じて、効果的に治療ができるように働きかける
事例についてのリフレクション
患者さんのことをよく見て、決めつけず解釈をしつづける
永渕さんは、Aさんのことをよく見ています。“うつろな表情”であるとか、“眠ってしまいそうな”と自分が見て意識に挙がった感じかたを表現しています。
そして、顔だけではなく、手先、髪の毛までも一瞬にして視覚で捉えて、「長く伸びて汚れていて乱れているけれども、気にする様子がないようだ」と解釈を加えています。患者さんの発する言葉よりも前に、“全身”と“部分”とをよく見て捉えているのです。
そして、自分の中に湧きあがったものを大切にして、その解釈をたよりに、「入院での治療は無理」と語るAさんと夫にかかわって、患者さんへの理解を深めていきます。
これは、目の前にいる患者さんについて、病状に伴う体調や自分の身体に対する関心というものを一瞬にして捉えて、まずは暫定的に解釈をしているという、卓越した実践であろうと思います。永渕さんがこれらのことをできるのは、【第27回】内で記述されていたように、「病気の管理ではなく、患者さんの生活にケアの視点をもつことを大切に」されているからでしょう。
さらに、重要なのは、この最初の解釈を“決めつけ”にはしないということだと思います。つまり、髪の毛の手入れもままならない“セルフケア能力の低い人”という捉えかただけでケアを進めてはいないということです。
むしろ、永渕さんは、「なぜ、乱れているのを気にする様子がないのだろう?」という気がかりを抱いて、看護ケアを進めているというように私は読み解きました。
このように、暫定的な解釈と気がかりとをもちながら看護ケアを進め、解釈や気がかりを膨らませたり変容させたりということができると、その患者さんの“今に合った”看護ケアが実践できるのだろうと思いました。
患者さん・家族の回復していく力を信じて、効果的に治療ができるように働きかける
Aさんは、高血糖を改善するという医学的な課題があり、インスリン療法導入のために入院を勧められますが、意思をもって外来での治療を希望します。
この記事は会員限定記事です。