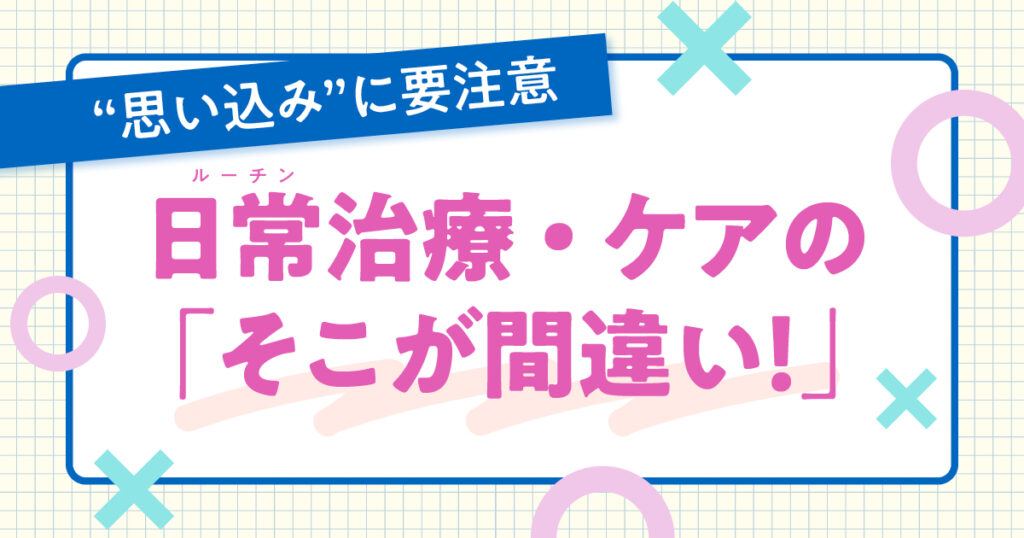術後疼痛には、機序の異なる鎮痛薬をあわせて使用することが大切です。今回は、NSAIDsの使い分けのポイントやアセトアミノフェン使用時の注意点を解説します。
NSAIDsの剤形ごとの使い分け
NSAIDsは副作用の軽減や即効性、効果の長時間持続といった目的で注射薬や坐薬などが開発されています。
1)静注薬:経口摂取ができない手術直後の患者に使用
唯一の静注薬であるフルルビプロフェン アキセチル(ロピオン®)は、血中濃度の上昇がすみやかで効果発現が最も早く、健常成人に 50mgを単回投与すると投与 6.7±1.7分後には最高血漿濃度に達します。経口薬のロキソプロフェンは、最高血漿濃度に達するまでの時間は30分(ロキソプロフェン)~50分(活性代謝物)となっており、このことからも静注薬の効き目が早いことがわかります。そのため、全身麻酔による手術直後で経口摂取ができない患者に用いるのがよいでしょう。
また、静注薬であれ経口薬であれ投与後に、除痛されることによってそれまで痛み刺激によって亢進していた交感神経や下垂体-副腎系の内分泌反応が減弱し、血圧や心拍数が低下することがあるので、バイタルサインや痛みを含めた患者の症状の変化には十分注意する必要があります。
ただし静注薬は、経口摂取ができない状態にしか基本は使用できません。
2)坐薬:意識状態が悪いときや吐気が強い、 座位を保持できない患者などに使用
坐薬は、直腸投与のため、胃腸粘膜への直接刺激を避けることが可能です。ただし血中に入ってからも作用するため、胃腸障害軽減に寄与しますが、重篤な消化管障害を抑えるエビデンスはありません。
また直腸から吸収された薬剤は肝臓での代謝を受けにくく、経口投与に比べ作用発現が早く、高齢者などで低体温ショックに注意する必要があります。
効果の強さに応じたNSAIDsの使い分け
NSAIDsには種類が多くありますが、化学構造によって分類され、効果の強さ、血中半減期の長さおよび副作用などにそれぞれ違いがあります。
この記事は会員限定記事です。