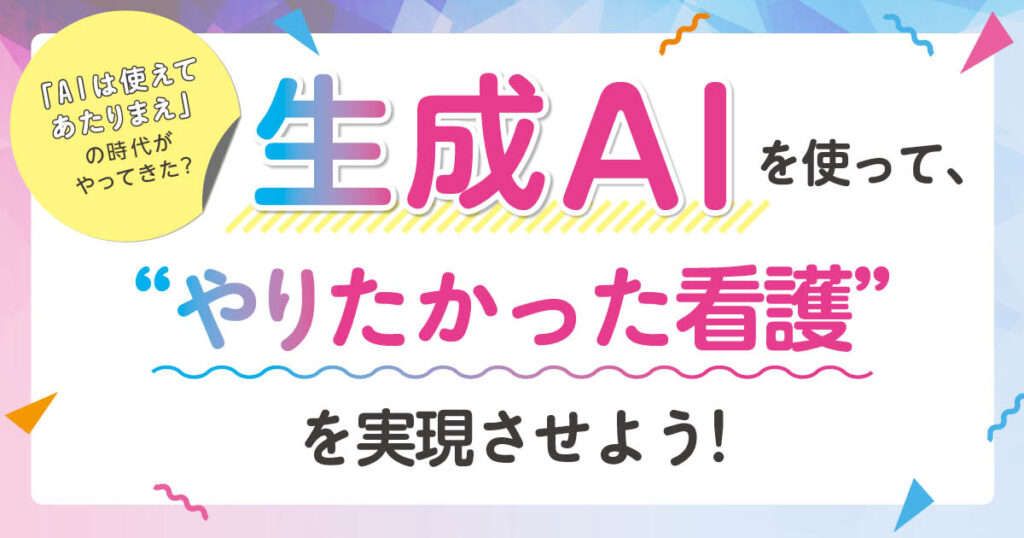看護師向けに、ChatGPTなど生成AIの種類や活用ポイント、使い方の注意点を簡単にまとめました。看護の現場で活用するために必要なことを紹介します。
「AIは使ってあたりまえ」の時代がやってきた?
昨今、「ChatGPT」や「Gemini」などの生成AI*についての話題が日常的に耳に入るようになってきました。本記事では、「じつは生成AIって具体的に何ができるのかわかっていない」「使い方が難しそうで触ったことがない……」という方向けに、入門のさらに入門として、生成AIについてのポイントと看護へのつなげ方を簡単に紹介します。
*【生成AI】学習したデータを活用して、新たなコンテンツを生成するAI技術。
Q 生成AIを使用したことはありますか?
※以下、2025年9月実施 エキスパートナースモニターアンケートより(n=57人)
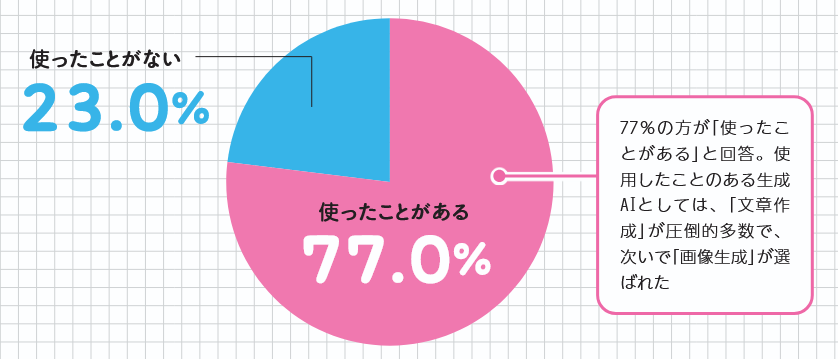
Q 生成AIを使用してみて、どのような印象でしたか?
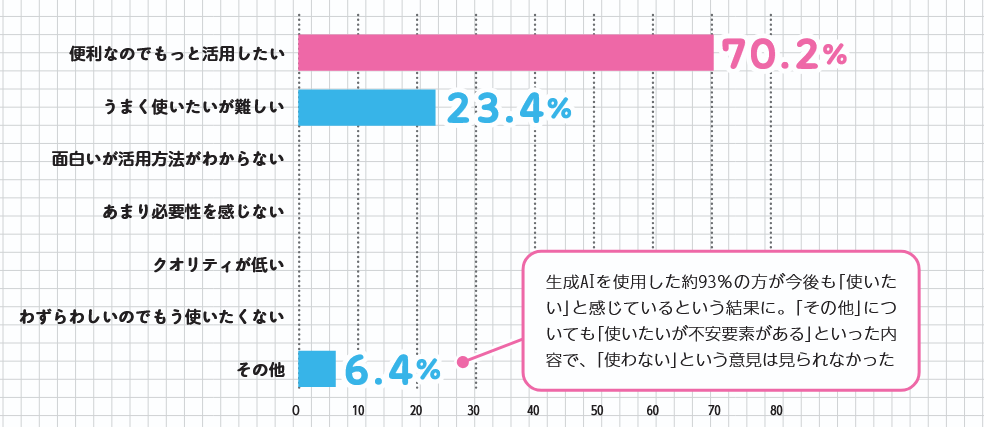
Q 生成AIについて、具体的にはどのように使用していますか?
業務で使った!
●ChatGPTに文章の要約をしてもらいます
●ChatGPTに、勉強会の資料のアウトラインをつくってもらいました
●資料やメール文書のたたき台をつくってもらっています
●問診の際に「AI問診」を利用していて、iPadを患者さんに渡して答えてもらっています
●論文やガイドラインを探してもらっています
●わからない病態を、わかりやすく解説してもらいたいときに活用しています
●会議の議事録を、きれいにまとめてもらっています
●勉強会のテーマや目的・目標を、生成AIとの対話を通して深めています
プライベートで使った!
●ChatGPTに献立を考えてもらったり、結婚式準備について情報収集したり、冠婚葬祭やふるさと納税についてのルールなど、わからないことを質問しています
●撮った写真を元にイラストを描いてもらったり、会話をしたり、子どもたちと一緒に楽しんでいます
●ある俳優の名前が出てこなくて作品名も出てこないときに、どんなドラマかやどんな印象の役だったかを伝えて、ChatGPTに答えてもらいました
●旅行のプランを立ててもらったり、おすすめのお店や観光スポットをまとめてもらったりしています
他にも…
●仕事に行きたくない日に行けるような気持ちに変えてもらったり、仕事で失敗したことを慰めてもらったりしています
●研究疑問を投げかけたり、ゼミのディスカッション形式の想定でAIから質問してもらったりしています
●子どもへのかかわり方を相談しています
●SNS画像やインスタ映えのために使用しています
*
以前はGoogleなどの検索エンジンで調べていたことも、今は生成AIに尋ねるようになってきた、という方も。ご意見のなかには、「今、何にでも生成AIを使ってしまうので、それはそれで問題に感じている」といったものもありました。
Q. まだ生成AIを使ったことがないのだけれど、何で、 いま使えるようになっておいたほうがいいの?
Answer
「あなたの仕事や可能性を大きく広げてくれる “新しいツール”になり得る」から!
業務中に「もっと効率よく仕事ができたら」「患者さんともっと向き合う時間がほしい」などと願うことも多いのではないでしょうか? 医療・看護の分野でも生成AIが、私たちの働き方をサポートする形で導入される可能性が十分にあります。“自分のしたい看護を叶えるため”に、「生成AIのうまい使い方」を今からしっかり学んでおきましょう。
生成AIってどんなものがあるの?
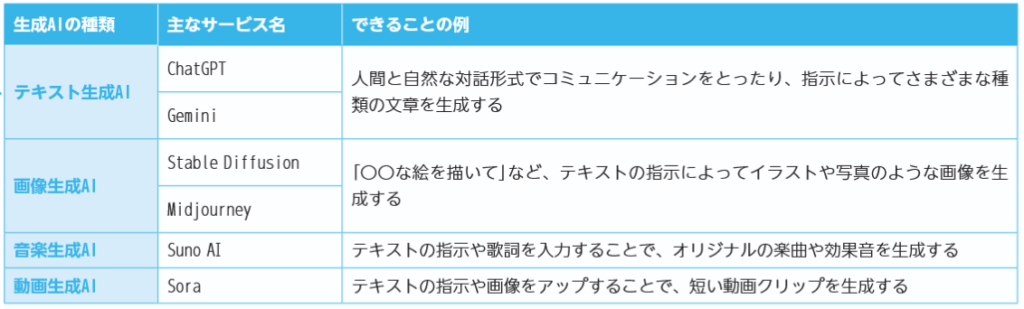
テキスト生成AIが得意なこと
●さまざまな種類(メール、報告書、詩など)の文章作成
●企画や問題解決のアイデア出し
●論文や報告書の要約
●海外文献などの翻訳
●資料等の情報整理
●専門用語をわかりやすい文章へ書き換え など
*「最終的な内容の責任は自分がもつ」という意識で、生成した文章の内容の確認が必要
テキスト生成AIが苦手なこと
●正確性・専門性が求められる文書を1からつくる(丸投げする)
●専門性のある文書の要約の際に、重要な情報をもれなく拾いきる
●バイアスをもたず、公平な視点で情報を収集・生成する(学習元により、多く存在する情報に偏って生成してしまう)
●倫理観などの反映 など
よく問題視されている“ハルシネーション”って何?
「ハルシネーション」とは、生成AIがあたかも真実であるかのように「事実に基づかない情報」や「もっともらしい嘘」を平然と語ってしまう現象のことを指します。AIは膨大な量のデータのパターンを学習することで、最も「それらしい」と思われる単語をつなぎ合わせて応答を生成しています。“事実かどうか”を人間のように理解・判断しているわけではないことに、理解が必要です。
はじめての生成AI、使い方のポイントは?
その① AIは「新人看護師」と同じと思って接しよう
●曖昧な指示が苦手
●間違いを言うこともある
●あなたの指示でアウトプットが変わる
その② AIとの会話のキャッチボールを楽しもう
●間違いを恐れず、いろいろ話しかけるところからスタート
その③ AIに役割を与えてみよう
●AIを「〇〇のプロ」に任命し、その視点から質の高い応答をしてもらう
その④「対話」で深堀りしよう
●遠慮なく、具体的に追加注文をしていく
その⑤ 慣れてきたら「仕事」を手伝ってもらう
●定型的な作業や、アイデア出しはAIの得意分野
その⑥ 忘れないでほしい! 3つの「注意点」
●ファクトチェックを必ず行う
●個人情報は絶対に入力しない
●最後は「自分の言葉」で仕上げる
*「もう生成AIを使っている」という人にも、その⑥のポイントは、忘れずに心にとめておいてほしい内容
結論:生成AIをうまく使うためには「的確な指示」や「内容の事実確認」が必要!
「的確な指示」として、「そのまま使えるプロンプト」300点を掲載!
看護の現場で「うまく使うため」に重要な“注意点”も具体的に示しています
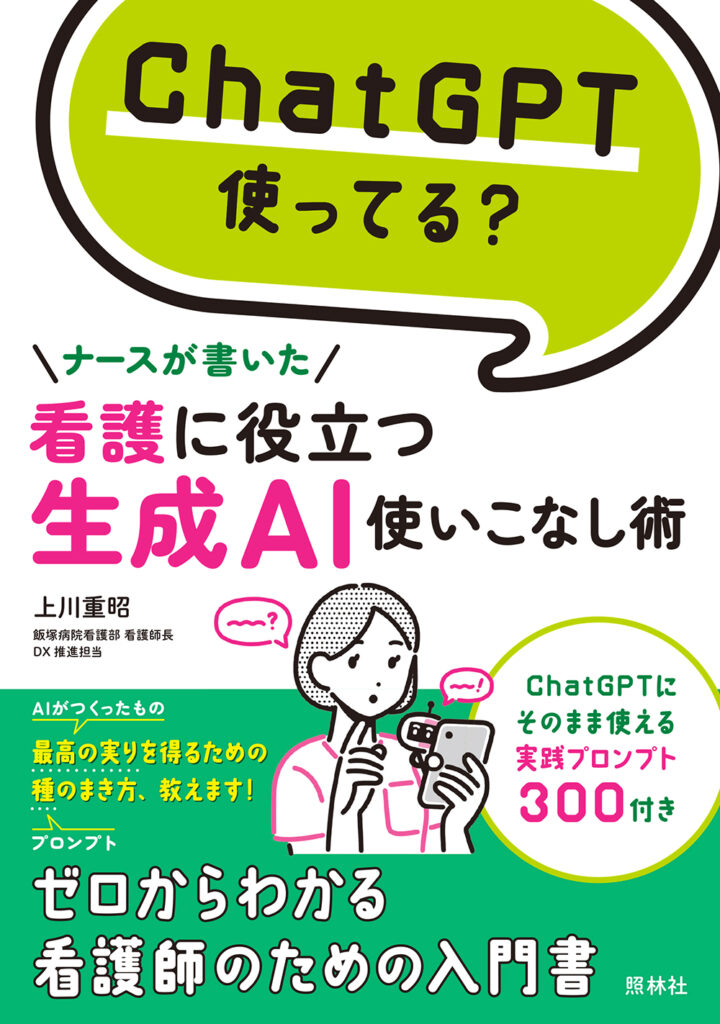
ChatGPT使ってる?
ナースが書いた 看護に役立つ生成AI使いこなし術
上川重昭 著
照林社
A5判、定価:1,980円(本体1,800円+税)
※10月24日発売
今回の記事の詳しい内容だけでなく、「AIと生成AIって何が違うの?」「いまの看護の現場で使える活用法」など、ChatGPTを中心とした基本の知識から実践までをこの1冊でサポートします。
著者
上川重昭
(飯塚病院看護部 看護師長 DX推進担当)
※当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。