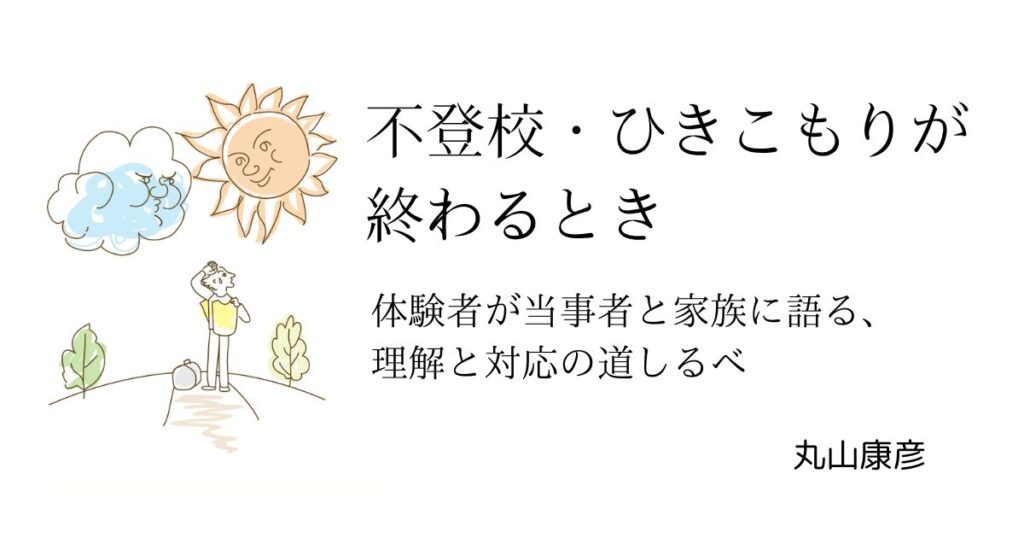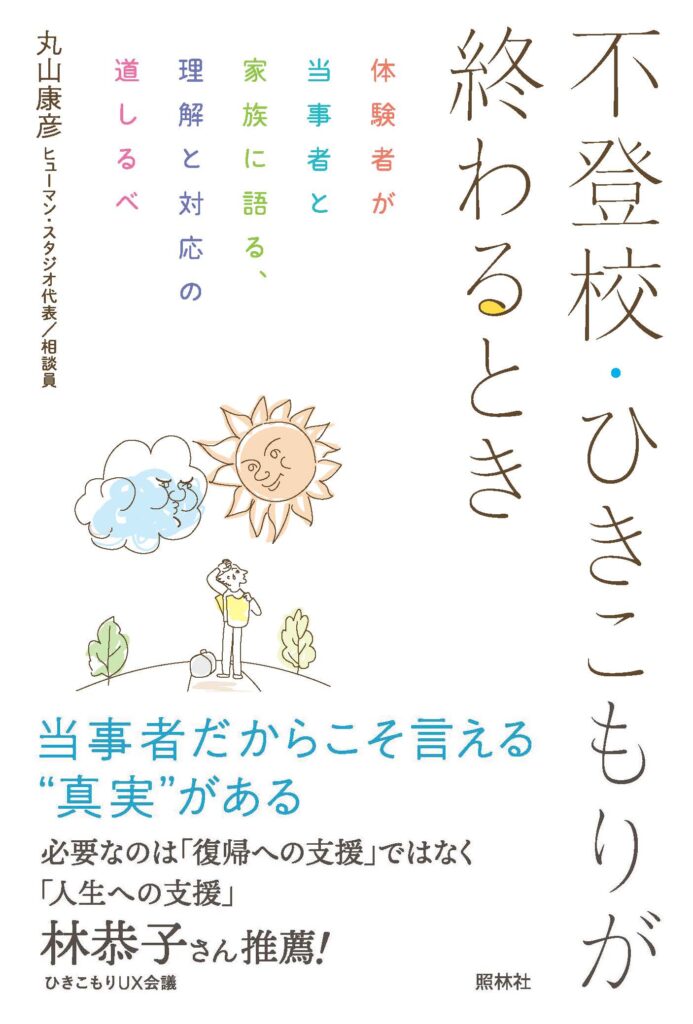自らが不登校・ひきこもりに悩んだ著者が、当事者と家族に語る道しるべとは?『不登校・ひきこもりが終わるとき』の試し読み記事を公開!序章として、当事者の願いや思いを受け止めることの大切さを語ります。
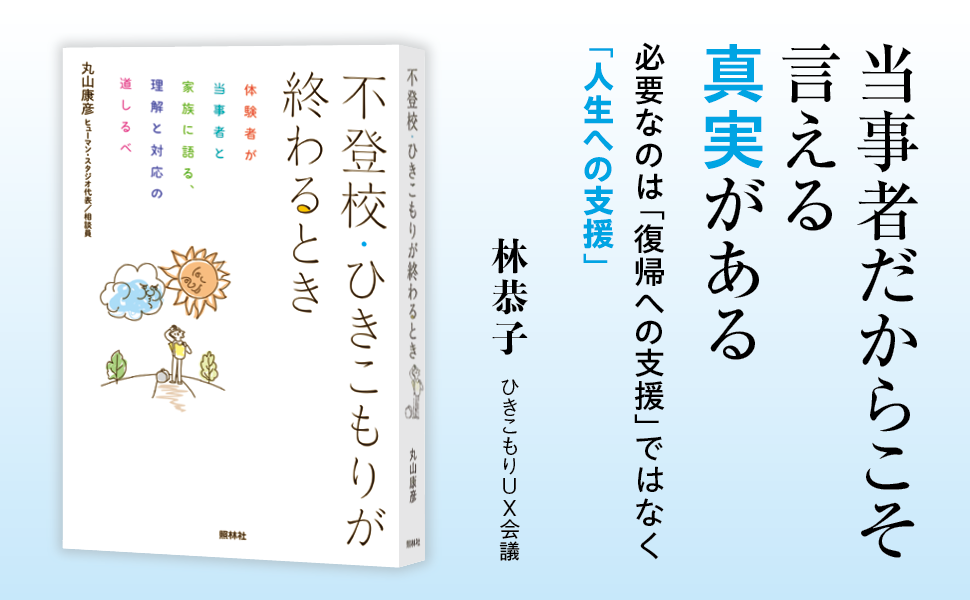
この記事は『不登校・ひきこもりが終わるとき』(照林社)の一部を再構成したものです。
当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。
春は、新しい年度の始まりです。不登校状態からの進級進学や留年などで新しく出発する人、ひきこもり状態からアルバイトや仕事を始める人、そのような目に見える進展がない人……など、それぞれの人生を歩まれていることと思います。
本人またはご家族からご相談を受けていて、結果的に本人が進級進学を果たしたケースのなかには、年明け前の時点では「今の状態では目標が高すぎる」として、目標を達せられなかったときの対応も周囲が想定していたケースもあります。
結局その必要がなくうまくいった、つまり、「無理しているからといって必ず挫折するとはかぎらない」というケースだと言えます。
もちろん、これで全面解決だと断定できるかどうかは誰にもわかりません。「ホームランを打ったが試合はまだ続いている」といったところでしょうか。いずれにしろ、大きな一歩を踏み出した本人の決意と努力に拍手を送り、前途に幸あらんことを祈っています。
私は10年以上にわたり、メルマガを通していろいろなことを書いてきましたが、そのすべてを貫いている論旨は「不登校やひきこもりの人への対応は、本人の願いや思いを前提に判断され実行されるべきである」ということに集約できます。
逆に言えば、対応は周囲の願い――多くは「学校/社会への復帰」――を前提に判断され実行されるべきではない、ということです。
「学校/社会への復帰」を前提に判断され実行されるべきではない
そのため私は「本人はこんなことを思い、あんなことを願っていますから、それに沿ってこういう対応をしてはどうでしょうか」と提案することになります。
こう申し上げると、「〝学校/社会に復帰しなくてもいい〞と無責任に煽っているのか?」と誤解されそうですが、そうではありません。
と申しますのも、不登校やひきこもりの人の多くは「学校になんか行くもんか」「社会に出ずにすむならそうしたい」どころか、往々にして「学校/社会に復帰したい」と願っているものだからです。
つまり、周囲が願わずともほかならぬ本人自身が「学校/社会に復帰したい」と願い、そしてそれを実現しようとするわけです。このことは「本人が無理な目標を設定している」と私が感じても、それをクリアする人がいる、という冒頭のお話からもおわかりいただけるでしょう。
「それだったら話は早い。本人と周囲の願いが一致しているのだから、学校/社会への復帰めざして一緒にがんばればいい」ということで話が終わりそうですが、事はそう簡単ではありません。
私が前提にすべきと考えている「本人の願いや思い」は、そこから先の話なのです。
なぜ学校/社会に復帰しても楽になれない人がいるのか?
「本人が復帰を望んでいるから復帰させてあげているのだ」――不登校の子の学校復帰やひきこもりの人の社会復帰を推進している教師や専門家や団体の方の、そんな発言や文章をよく見聞きします。
確かに、前述のとおり本人の多くは「学校/社会に復帰したい」と本気で言います。その言葉に嘘偽りはこれっぽっちもありません。
しかし、それなら本人たちはなぜ、担任の先生やクラスメートやメンタルフレンドの訪問を嫌がるのでしょうか。なぜフリースペースなど支援の場に行けないのでしょうか。なぜ就労支援を利用しようとしないのでしょうか。
そして何よりも、なぜ学校/社会に復帰しても楽になれない人が少なからずいるのでしょうか。
このように考えていくと「学校/社会に復帰したい」という、本人たちの「願い」の奥には、自分でも気づいていない「でも……」という「続き」があるとしか思えないのです。
先ほど私は「本人の願いや思い」と「周囲の願い」というふうに、本人には「願い」のほかに「思い」があることを示唆しました。
「でも」から始まる「続き」が、この「思い」に当たる部分です。
それは「でも復帰できない」という〝現状を訴えるもの〞だけではなく「でもまず自分を創り直したい」「でも周囲に合わせるのではなく自分に合った生き方がしたい」「でも導かれるのではなく自分の足で歩きたい」「でも学校/社会への違和感と折り合いがついてからにしたい」などといった、複雑な心境や深い欲求も含まれています。
「願い」と「思い」のどちらを否定しても、本人は楽にならない
ですから、それらをも包含した奥行きと深さのある「願いと思い」をすべて認めて受け止めることによって、本人は初めて楽になって元気を取り戻し、自分の主体的な意思で学校/社会とどう向き合っていくかを決めて実行することができるようになるのではないでしょうか。
それとも「思い」を認めずに「願い」だけで頭がいっぱいのまま、脇目も振らずまっしぐらに突き進んで復帰を果たしたほうが、その先の人生に深い納得と肯定感が得られるのでしょうか。
私は「願い」と「思い」のどちらを否定しても、本人は楽にならないように思います。したがって〝願いと思いの葛藤ロード〞を歩み続けて自分の生き方を見出したときに「自分の生き方に何が必要か」を自問した結果「学校だ」と判断すれば学校に復帰すればいいし「仕事だ」と判断すれば仕事に就けばいい、それでこそその先の人生に深い納得と肯定感が得られる、と考えるのです。
この「人生に深い納得と肯定感が得られる」ということを究極の目標に据えて相談援助業務にたずさわっていて見えてきたものを、これからお示ししていきます。お子さんの状況に合った提案を見つけてください。