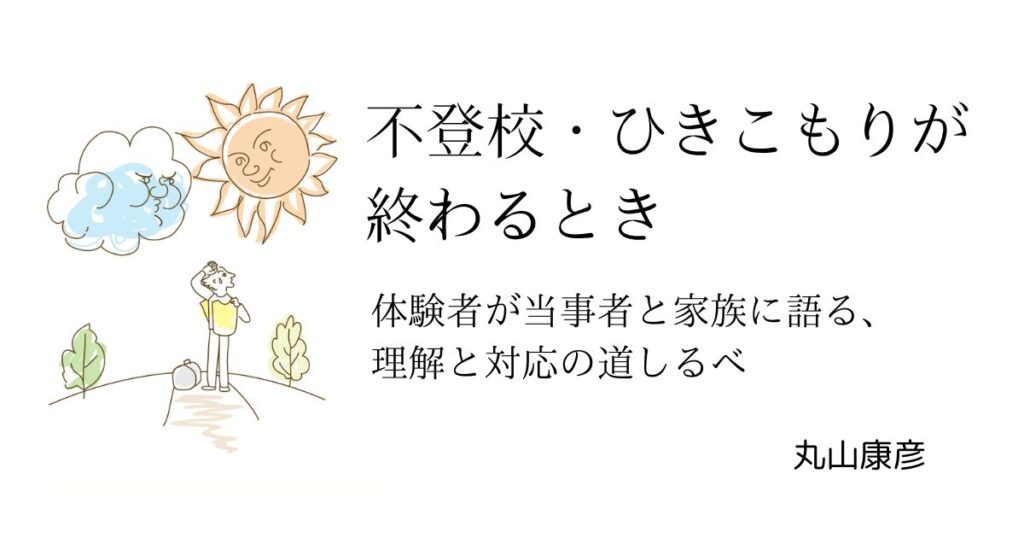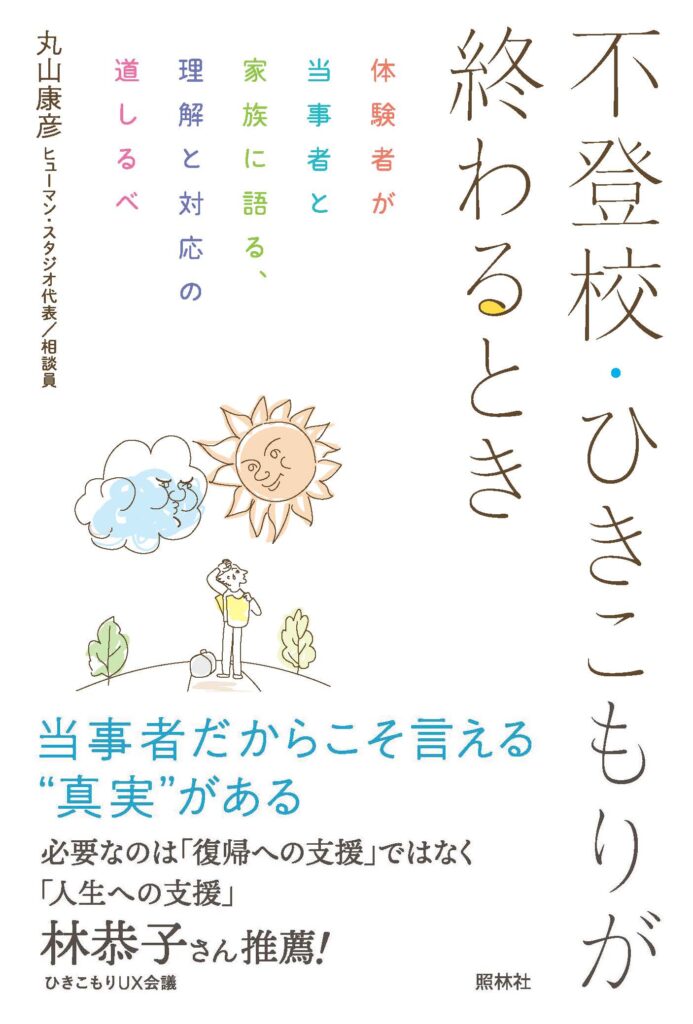書籍『不登校・ひきこもりが終わるとき』(丸山康彦 著、照林社)を再構成した全10回の連載です。不登校・ひきこもりの当事者体験のある著者だからこそ伝えられる「道しるべ」が詰まっています。
【第1回】はじめに
この本ができるまでの経緯や、そして読者の広がりがつづられています。
【第2回】序章――〝願い〞と〝思い〞を受け止める
「不登校やひきこもりの人への対応は、本人の願いや思いを前提に判断され実行されるべきである」と言う著者。「学校/社会に復帰したい」との願いの先にあるのが、本人の「思い」です。
【第3回】不登校・ひきこもりという“生きざま”にむきあう
不登校やひきこもりを「生き方」ではなく「生きざま」と表現。その意味とは?
【第4回】不登校・ひきこもりの理解に必要な人生観
“生きる道はいくつもある”。このときの「道」のイメージについて考えていきます。
【第5回】不登校・ひきこもりの理解に必要なこども観
子どものことがわからない――。そう悩む大人に向けて、CMやドラマのシーンを例として交えながら、アドバイスしています。
【第6回】不登校やひきこもりになる理由①踏破をめざしてトンネルを歩く
本人たちはどのような支援を望んでいる?「人生の歩みを続けている人たち」「その歩みが自分で動き出す力へとつながる人たち」への“後方支援”を紹介。
【第7回】不登校やひきこもりになる理由②「子育ての誤り」という誤解
不登校・ひきこもりの子どもを持つ人からよく聞かれるという「子育てが間違っていた」との言葉。それに対し著者は、不登校・ひきこもりは「自分で起こす行動」だと述べています。
【第8回】不登校やひきこもりになる理由➂心理メカニズムの観点から
心理的メカニズムの観点から、不登校・ひきこもりを解説。不登校になるにはどのようなきっかけがあるのかをみていきます。
【第9回】不登校やひきこもりになる理由④共通の心理状態とは?
不登校やひきこもりになると、共通の心理状態が生じるとのこと。ひとつは傷の深さ、疲れの深刻さ、もうひとつは当たり前のことに意識過剰になるという心理です。
【最終回】不登校やひきこもりになる理由⑤必要なのは治療や矯正ではなく“配慮”
不登校・ひきこもりに対する「何とかしたい」との思い。特別な目で、あるいは〝上から目線”で見て対応や支援を考えていないか、自分に問い直してみませんか。