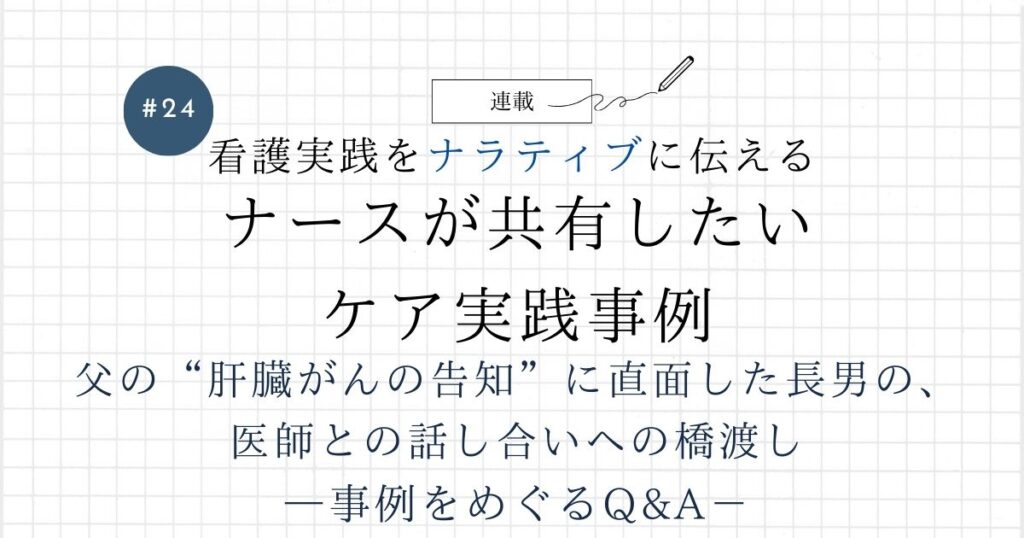事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は父の“肝臓がんの告知”に直面した長男の、医師との話し合いへの橋渡しをめぐるQ&Aを紹介します。
今回の事例:【第23回】肝臓がんの告知に直面した家族への意思決定支援
〈目次〉
この場面を紹介した理由は?
相談者の怒りにどう対応している?
告知の際、患者の認知力や理解力をどうアセスメントしている?
Aさん家族が在宅療養ができると考えたのはなぜ?
事例をめぐるQ&A
この場面を紹介した理由は?
梅田 どうしてこの場面を取り上げられたのでしょうか?
加藤 悪い知らせを受けたときの心理反応に、“怒り”があります。この怒りは、悪い事実に向き合うために必要な反応で、心の均衡を保つための自然な反応であると考えています。 この心理反応をふまえてAさんの反応の意味をとらえるように心がけた結果、Aさんは弟と一緒に父親に病気を伝え、父親とともに治療や今後の療養について話し合い選択できたため、印象に残っていました。
相談者の怒りにどう対応している?
梅田 がん相談支援センターでの相談を受けるとき、怒りの表出があると対応にとまどわれると思いますが、このケースに限らず、どのように対応されているのでしょうか?
加藤 私自身、怒りの反応が顕著に現れると、とまどいや不安、あせりを感じます。しかし、そのような自分の感情を否定せず、自分1人で抱え込まず、誰かに気持ちを聴いてもらうようにしています。そのようにして、そのときどきの自分の感情を受け止めるように心がけています。
そして、相談者の語りを促し、怒りの背景にあるできごとや状況、病状理解などを把握し、動揺する気持ちに理解していることを言葉で伝え、受け止めていることが伝わるように心がけています。
告知の際、患者の認知力や理解力をどうアセスメントしている?
梅田 がん医療の現場では一般的に告知をすることがあたりまえになってきました。しかし、特に高齢者など、認知力の低下や、難聴や視力低下などで理解力が低下していて、伝えられた内容の解釈が混乱することもめずらしくないと思いますが、どのように対応しておられますか?
加藤 医師との面談時に、表情や言動を観察しながら、認知力や理解力をアセスメントしています。
この記事は会員限定記事です。