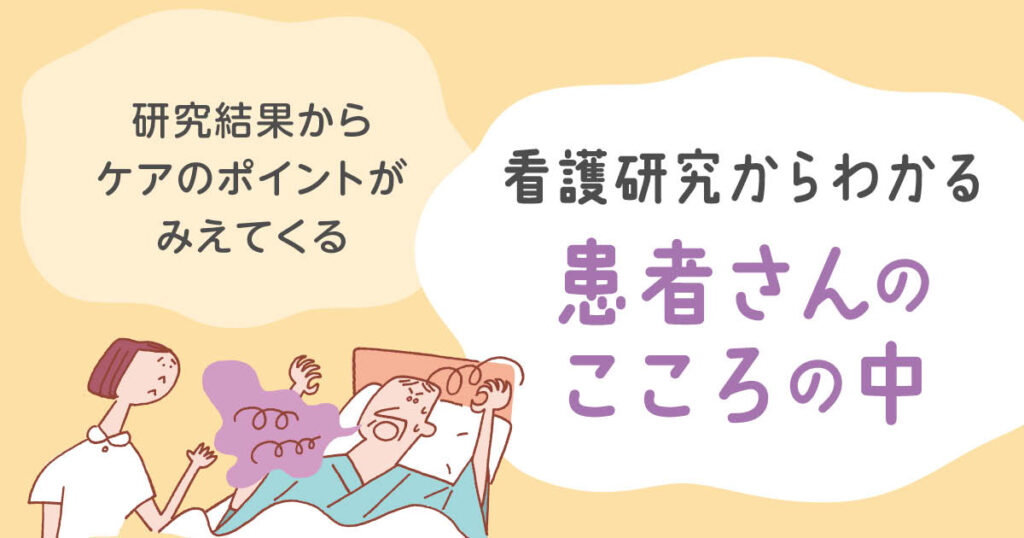患者さんの体験・心理についての「研究」を原著者に紹介してもらい、臨床で活用したいこころのケアを探ります。今回は、回復過程における脳卒中患者さんの心理についての研究です。
脳卒中発症からどのように回復する?何が影響する?

脳卒中は突然の発症であることが多く、心身の諸機能にさまざまな障害をもたらします。特に片麻痺を中心とする運動機能障害は、それまで不自由のなかった日常生活動作(actives of daily living、ADL)を突然阻害するため、その人の人生を根底から揺るがすことになります。
そのため、患者さんは、発症からの回復過程において人生の再構築が必要となり、これを支援することが重要です。
これまでの研究1-3では、障害受容はいずれもショックから始まり落ち込みを経て適応に至るプロセスとされます。しかし、リハビリテーションとの関係が不明瞭なことや死の過程と回復過程を同様に捉えたことが妥当でなく、中枢神経障害を対象とした研究でないことなども指摘されてきました。
そこで本研究4,5では、患者さんの体験を分析すると同時に、客観的にADLを測定し、回復過程における体験の変化と、それに影響を及ぼす要因を明らかにするための研究を行いました。
なお、本研究における「回復」とは、身体面や心理面のみではなく、それらを包括した全体的な概念(患者さんが障害に意味を見出すことなども含む)を示しています。
本研究は、以下の倫理的配慮のもとに実施されたものです。
●本研究は、研究倫理審査委員会の承認を受けて行っています。
●対象者には文書で研究目的・方法・参加の自由・拒否や途中辞退の自由・個人情報の保護などを説明し、同意をいただいて実施しました。
●面接実施時には、症状の発現の有無や心理的変化の有無に常に注意を払いながら行いました。
研究の方法
疑問(調べたこと)
●脳卒中患者さんはどのような回復過程をたどり、何に影響を受けている?
研究対象
●74歳以下の初発の脳卒中で緊急入院した患者さん 12名
●発症5日以内に、運動機能評価法(ブルンストロームステージ)*1において「下肢StageⅢ以下」、機能的自立度評価法(FIM)*2において126 点中「79点以下」
研究方法
●発症直後の急性期から発症後約6か月まで、経時的にインタビュー
●同時にFIM測定を実施
*1【ブルンストロームステージ】Brunnstrom stage。片麻痺の運動機能の評価法で、上肢・下肢・手指ごとに評価ステージⅠ~Ⅵに分類される(Ⅵに近づくほど回復)。下肢StageⅢとは、座位や立位で股・膝・足関節の同時屈曲が可能な状態。
*2【機能的自立度評価法】functional independence measure。セルフケア6項目、排泄コントロール2項目、移乗3項目、移動2項目、コミュニケーション2項目、社会的認知3項目の計18項目について、各1点~7点でADLを評価する方法(低いほど、自立度も低下)。
発見1:脳卒中患者さんの回復過程と影響する要因
1)患者さんが体験する「5つの局面」がある
この記事は会員限定記事です。