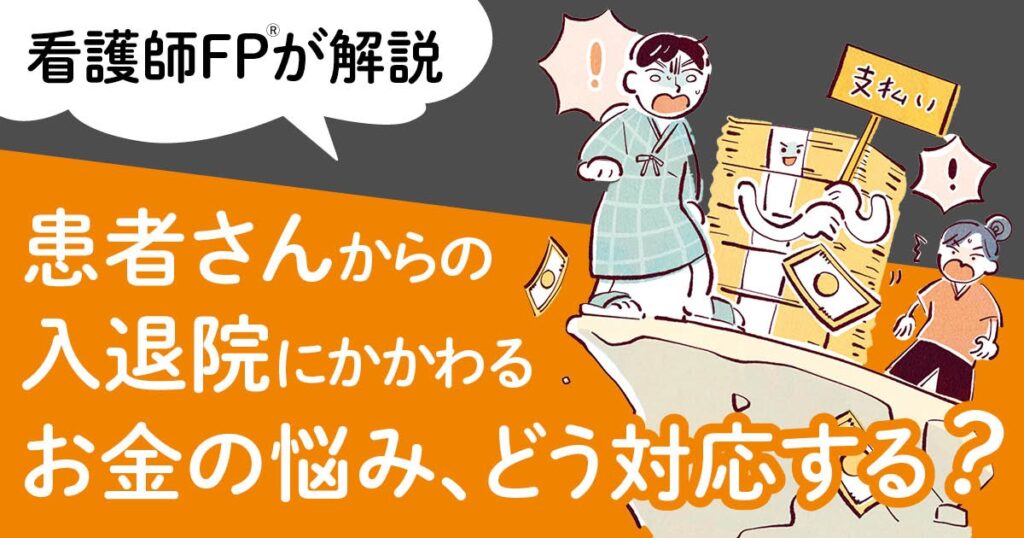病院での治療や介護サービスの費用について患者さんから相談されたら、看護師はどう答えればよいのでしょうか。看護師FPⓇが詳しく解説します。

患者さん
入院するときに仕事を辞めてしまったから、退院後の収入源がないんです…

看護師
退職時の状況によっては、健康保険の傷病手当金が利用できる可能性がありますよ!
退職後も健康保険の傷病手当金を利用できるかを確認しよう
退職のしかたや社会保険の加入の状況によっては、退職後にも継続して健康保険の傷病手当金を利用できる場合があります。
ただ、要件など注意するべき点が多くあります。そのため、患者さんに自身が加入している健康保険会社に確認してもらうか、MSWや社会保険の専門家である社会保険労務士(社労士)に確認できるよう、連携できるとよいですね。医療機関によっては、社労士が派遣で来ているところもあります。
健康保険の説明は「言い切らない」ことが大切
看護師が行う説明で注意しておきたいのが、利用できる・できないを断定せずに「利用できる可能性」に留めておくことです。健康保険の説明は複雑であり、説明不足で受け取れなかったというトラブルも散見されているため、断定せず確認先に誘導していくのが望ましいでしょう。
収入が途絶えてしまうことで、治療の継続だけでなく衣食住が脅かされる可能性もあります。入院時に行う社会面のヒアリングで確認している職業内容からも、収入が途絶えそうかの予測が可能です。早期に予測し、MSWや社労士へと連携していけることが望ましいでしょう。
おさえておきたい傷病手当金のポイント
ここでは傷病手当金について、おさえておきたいポイントを説明します。まず、健康保険組合によって内容が異なる場合があります。中小企業の従業員の方が多く加入している「全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)」をもとに説明します。なお、患者さんが加入している健康保険は本人の健康保険証から確認することができます。
まず、傷病手当金がどのようなものか、図1・図2に示します¹。
この記事は会員限定記事です。