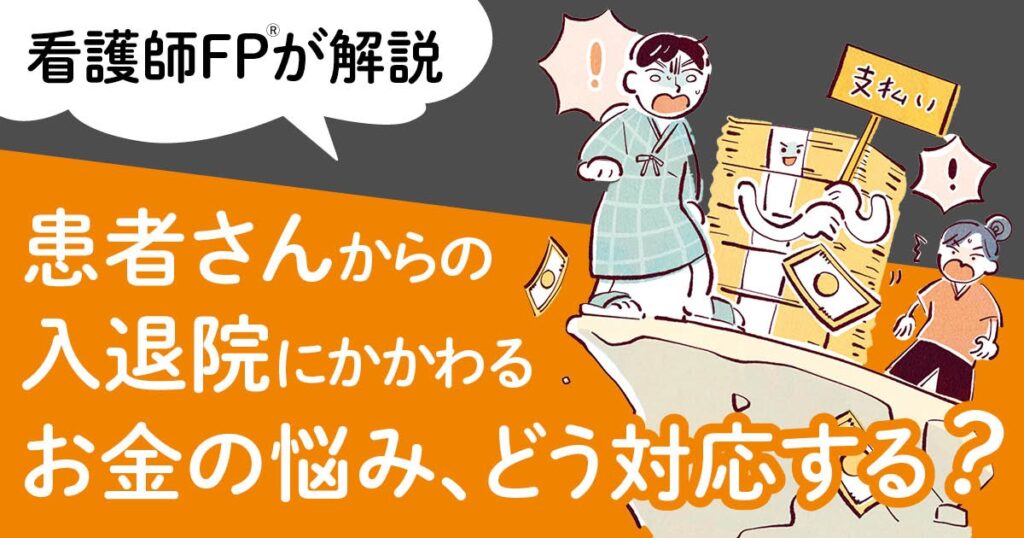治療に伴う家計の悩みを患者さんから相談されたら、看護師はどう答えればよいのでしょうか。看護師FPⓇが詳しく解説します。

患者さん
抗がん薬の治療費が毎月かかるので、住宅ローンが支払えるか不安です

看護師
打ち明けていただき、ありがとうございます。これからのお金のことで不安があるのですね。夜は眠れていますか?
お金の不安がどのくらい治療に影響を与えている?
住宅ローンなどの不安に答えていくには専門的な知識が必要となるため、今後の治療スケジュールと家計状況をふまえて専門のFPに相談してもらうことをおすすめします。
患者さんにとって一番身近な看護師が行える支援としては、患者さんや家族が住宅ローンをはじめ、どのくらいお金の不安を抱えているのか、その不安が治療に影響を及ぼしているのかどうかの把握と、心理面のケアがあります。
ここ数年、医療現場でも注目されてきている「がん治療に伴う経済毒性」を理解することで、心理面のケアにつなげられるのではないでしょうか。
近年問題になっている「経済毒性」とは?
がん治療は年々進歩しており、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬の登場によって予後が大きく改善されたことは喜ばしいことです。一方で、新規の薬剤は一般的に高額です。治療の長期化に伴い、日本ではいま、高額療養費制度があったとしても毎月生じる経済的な負担が問題となっています。
このように、がん治療に伴う経済的な負担がライフスタイルに影響を及ぼすことを「経済毒性(Financial Toxicity)」として、身体的な治療関連毒性と同様に扱う考え方が提唱されています。
経済毒性は一般に支出、資産・収入、不安感の3つの要素から成り立つとされています。
1.支出の増加
継続してかかる医療費が生活維持費に上乗せされるため、支出の増加となります。「生活費や住居費、教育費と一緒に、医療費をどう支払い続けていくか」という悩みを抱えていることがあるため、「高額療養費制度があるから大丈夫」とは言い切れないのです。
2.資産・収入の減少
がんの影響や治療の副作用などによって働けない場合は、公的医療保険の傷病手当金や年金制度の障害年金などの利用が可能な場合があります。また、ここ10年ほどでがん治療と仕事の両立支援が進んでいます。
この記事は会員限定記事です。