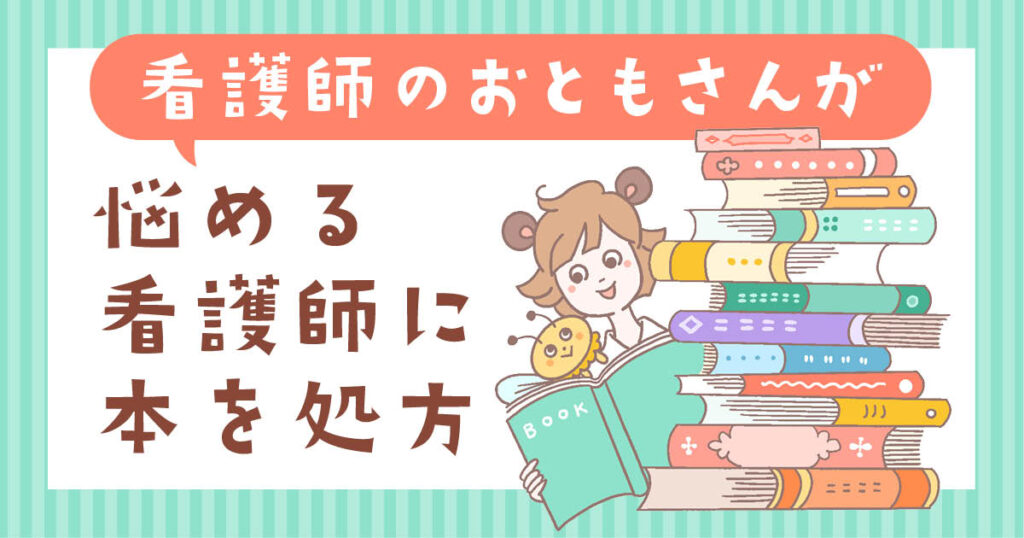本が大好きな看護師のおともさんが、“あなた”に寄り添った本を紹介するブックセラピー企画。看護師さんのさまざまなお悩みに合わせて、相談者にぴったりな書籍を教えてくれます。今回は「プリセプターとして教えることに悩んでいる」というお悩みです。
看護師のおともかんごしのおとも
救急外来部門・シミュレーションセンターで主任を務める看護師。実家も今の家も、本だけで丸々1部屋を使ってしまっているほどの本好き。@99emergencycall
看護師3年目になるKさん
はじめてプリセプターになりました。疾患や治療のことはどうにか勉強できますが、プリセプティとの相性が心配です。あまり勉強しない子だったらどうサポートすればいいのか、何を考えているかわからない子だったらどう接すればいいのか……。プリセプターの研修内容だけではまだぼんやりしていて、自分に務まるか不安です。これを機会に教育について学びたいと思っているので、おすすめの本を教えてください。
看護師が“教える”の原点を学ぶ本
白石 同様のお悩みがシニアプリセプターの方からもありました。プリセプターのように、はじめて教える立場になる人に向けた本を教えてほしいです。
看護師のおとも
ここは僕も興味・関心が強い分野なのでたくさん紹介したい本があります。さて、本棚から探してきますね……(ガサゴソ)。何度も個人的に紹介している本ですが、まず読んでほしいのは『教えることの基本となるもの 「看護」と「教育」の同形性』です。これは本当に看護師が教育を語る上でのバイブルのような存在。僕も事あるごとに読み返しているので、もうボロボロです。タイトルは難しそうですが、厚さは200ページもないぐらいで読みやすいんです。
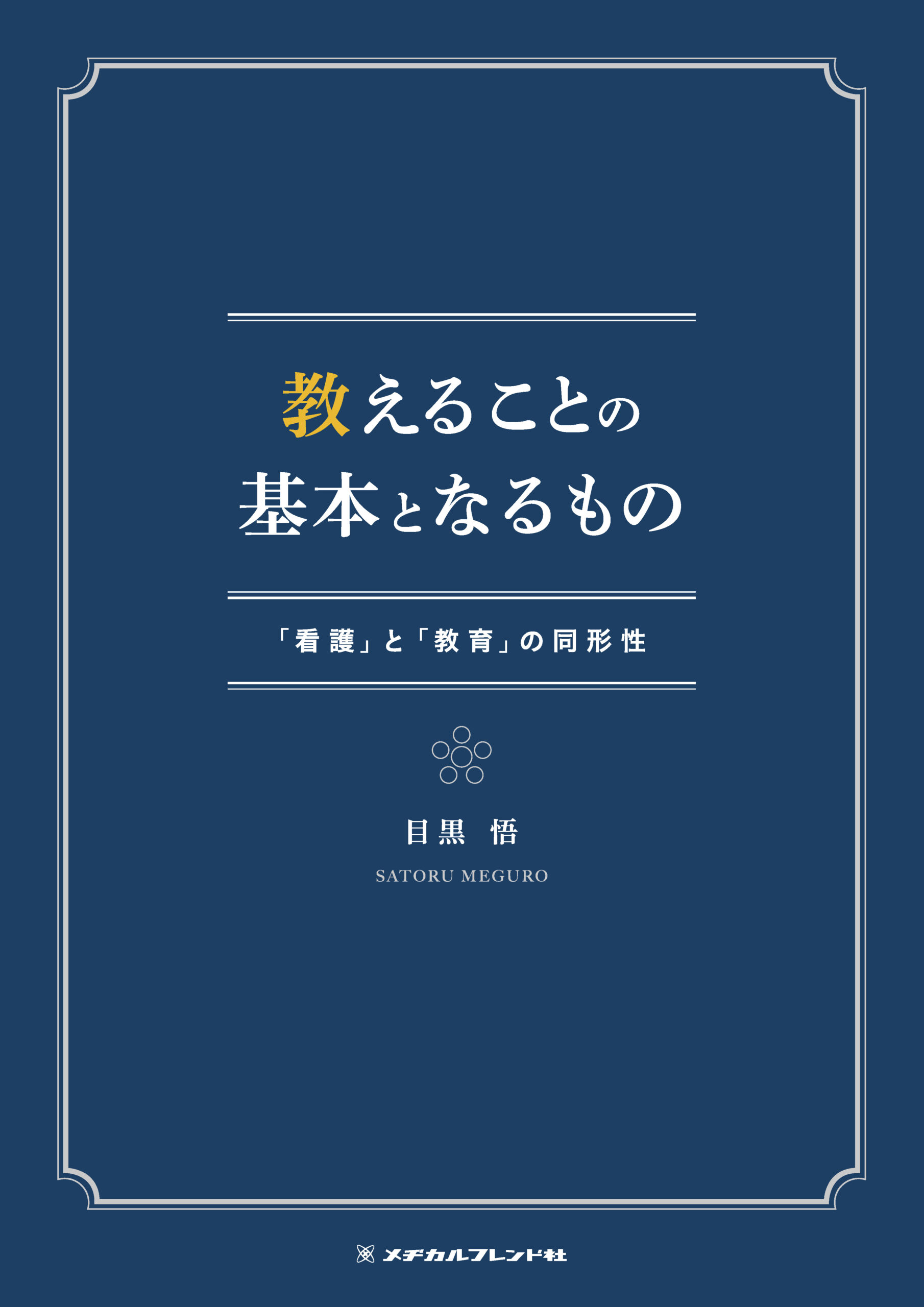
教えることの基本となるもの 「看護」と「教育」の同形性
目黒悟 著
メヂカルフレンド社
A5判
2,200円(税込)
白石 たしかに、思ったより薄いですね。
看護師のおとも
看護師って、看護の勉強はしていても、教育に関することは学んでいない人が多いので、「自分がされたように教えてしまう」という傾向がよくも悪くもあるんですよ。だから、やさしく教えられた人はやさしく教えるし、厳しくされた人は厳しくしてしまう……。この本のよいところは、教育に関することを看護バージョンに変換してくれること。
例えば「学習者にも個別性がありますよ」と、患者さんのニードと同じように学習者のニードも考えることの大切さを教えてくれます。あとは、教わる人から自分がどう見えているのか、意識するポイントにも触れていますね。2016年に初版が出たときに読んで、とても役立った思い出深い1冊です。
白石 話を聞いていると、教育の基本でありながら、患者さんとのかかわり方という看護の基本も振り返ることができそうですね。
看護師のおとも
そうなんです。患者さんが1人ひとり違うからこそ個別性を学ぶのと同じように、新人さんや学生さんにも個別性があるからそれを考えようね、と書かれています。新人さんやスタッフと一緒に成長しましょうということも書いてあるんです。
さらに、読みやすくて実践的なのが『マンガでわかる看護の教育 はじめてのプリセプター,OJT』。著者はアメリカに留学し、コロンビア大学で成人教育学を学んで帰ってきた看護師さんなんです。
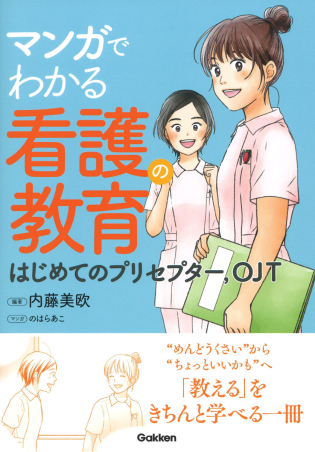
マンガでわかる看護の教育 はじめてのプリセプター,OJT
内藤美欧 編著
Gakken
A5判
2,640円 (税込)
看護師のおとも
最初に漫画が数ページあってから解説に入るスタイルで、「来年度からプリセプターを任された! 教えるって大変かも……」というプロローグから始まっています。1年間、時系列に沿って話が進むんですよ。
白石 1年通して読んでいけるんですね。
看護師のおとも
春はプリセプティと対面する際の注意点、夏には面談方法やインシデント対応、秋には新人間の差が出てきたときのアプローチなど、1年が全12話で進みます。最後は経験から学びを引き出す経験学習やリフレクションも扱っています。アサーティブコミュニケーションや思考発話(※)、心理的安全性といった最近のトピックも紹介され、先回りして考えるきっかけになります。2024年の春に出版されたばかりの新しい本です。
※アサーティブコミュニケーション:自分と相手を尊重しながらお互いの意見を伝え合うコミュニケーション方法。
※思考発話:課題を実行しながら、何に気づき、どう考えて行動しているのかを声に出して説明すること。
白石 章の合間には、振り返りができるようなメモ書きがついているんですね。
看護師のおとも
そうなんです。漫画で解説されているからといって、侮ってはいけません。中身は相当しっかりしていて、英語論文もどんどん引用されています。経験者が読んでも「なるほど、ここにこういう根拠があったのか」と思えるような内容です。
現場で役立つ、リアルな指導場面から学ぶ本
看護師のおとも
次に紹介したいのは、『看護現場で「教える」人のための本 教える側と教わる側のミスマッチを防ぐために』です。教える側が困る場面を13ケース紹介しています。「何がわからないかわからず混乱している」「同じミスを繰り返す」「課題が重すぎてつぶれそう」など、よくある指導の悩みを扱っています。
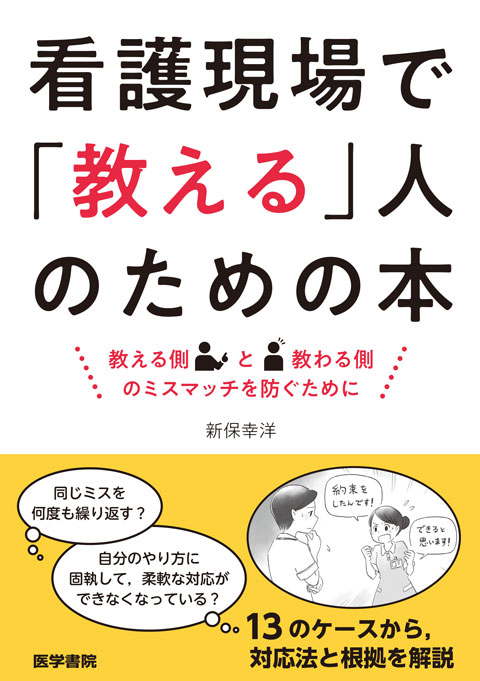
看護現場で「教える」人のための本 教える側と教わる側のミスマッチを防ぐために
新保幸洋 著
医学書院
A5判
2,420円(税込)
看護師のおとも
各事例は看護師同士の会話劇から始まり、イラスト付きで想像しやすく、登場人物の詳細情報も満載。その場面で何に注目すべきか、指導者が伝えたかったことや検討すべき点を解説しています。
白石 なるほど。会話の中でどこに齟齬が生じているのかをピックアップしているんですね。
看護師のおとも
そうです。看護師ならおなじみのプロセスレコードの指導者・新人版のようなものですね。「同じミスを繰り返す新人」のケースでは、先輩の「朝確認したこと、できてないよね」に新人が「すみません、他のことが重なって」と答え、「できないんだったら呼んでよね」と追及されて「すみません」と謝るばかりの会話から分析していきます。文献や研究から理論を紹介しながら、教育理論やフィードバック方法、コミュニケーション方法を解説しています。理論だけでなく実践的で、理解しやすい1冊です。
白石 先輩の言葉、思わず言ってしまいそうな内容ですね……。
看護師のおとも
「なんで言ってくれないの」と思ってしまうことはありますよね。この本を読んでいると「そもそもそれを言える空気だったのか」とも思いますし。
同じく事例で紹介してくれる本としてはこちらも。『先輩ナースが後輩指導で「悩みがちなこと」47』は、47項目の指導者の悩みをQ&A形式で解説しています。
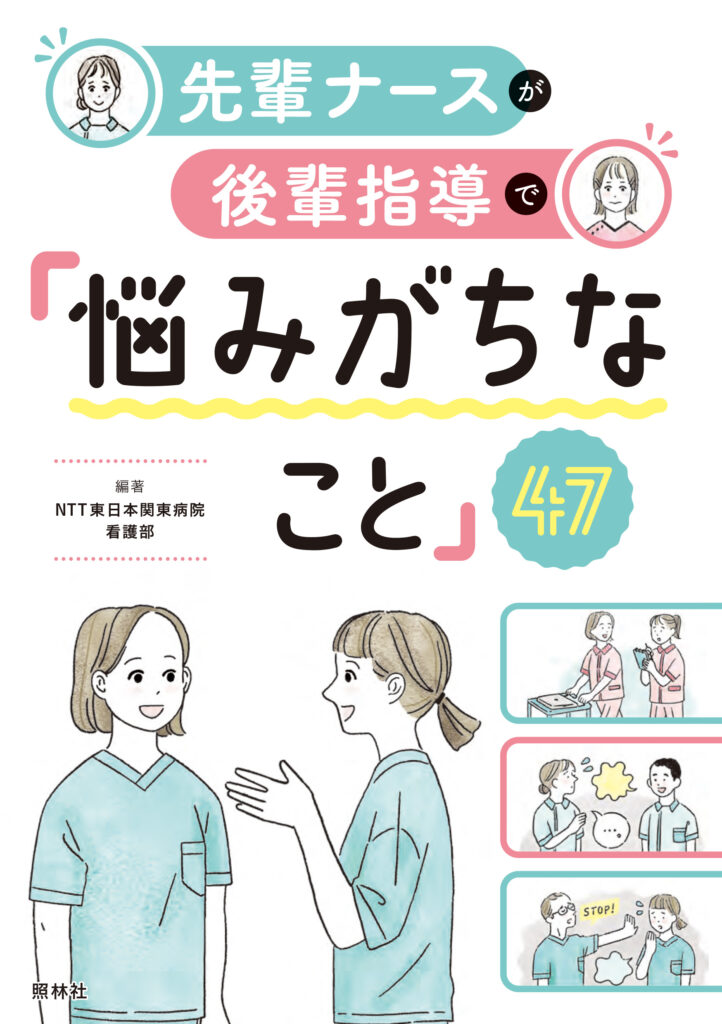
先輩ナースが後輩指導で「悩みがちなこと」47
NTT東日本関東病院 看護部 編著
照林社
A5判
2,530円(税込)
看護師のおとも
例えば、「積極的になってほしい」という先輩の悩みに対して「失敗すると患者や医師に迷惑をかけてしまうから怖い」という後輩の思いを紹介し、「こうすればうまくいく」「これは避けたい」と具体的なアドバイスが書かれています。「なんでも『1人でできます!』とやろうとして失敗する」「自分が教えたやり方ではなく他の先輩のやり方で実践されて微妙な気分」といった意外な悩みや、「教育係以外の先輩が非協力的で困る」という横のつながり、さらに労務管理や健康管理についても触れていますね。
白石 すごく細かく紹介されていますね。特に新人や後輩の視点はめちゃくちゃリアルな感じ。実際に新人さんにいろいろヒアリングしてつくられたような内容ですね。
看護師のおとも
編著はNTT東日本関東病院の看護部。実際の現場の声をもとに作成された実用的な1冊です。あと個人的に気になったのが、最後のほうに「後輩を叱るときにやってはいけないこと」というページがあって、「おまけ」って書いてあるんですけど、これおまけでいいのかなと……(笑)。絶対NGなことが載っているので、最初にあってもいいんじゃないかなって思うくらい。
白石 本当だ。でも、こういう本をわざわざ読む層向けだから、あまり押し付けない、肩ひじ張りすぎないようにということで、おまけにしたのかもしれないですね……。
看護師のおとも
そうかもしれない。最後のページだけでもまずは読んでほしいレベルですね。
最後に、職場に置いてある本でもう1冊紹介したいものがありまして。『対人コミュニケーション入門』という、もともとライフサポート社から出ていた本。人と人がかかわるときの基本がしっかり書かれた読みやすい本です!
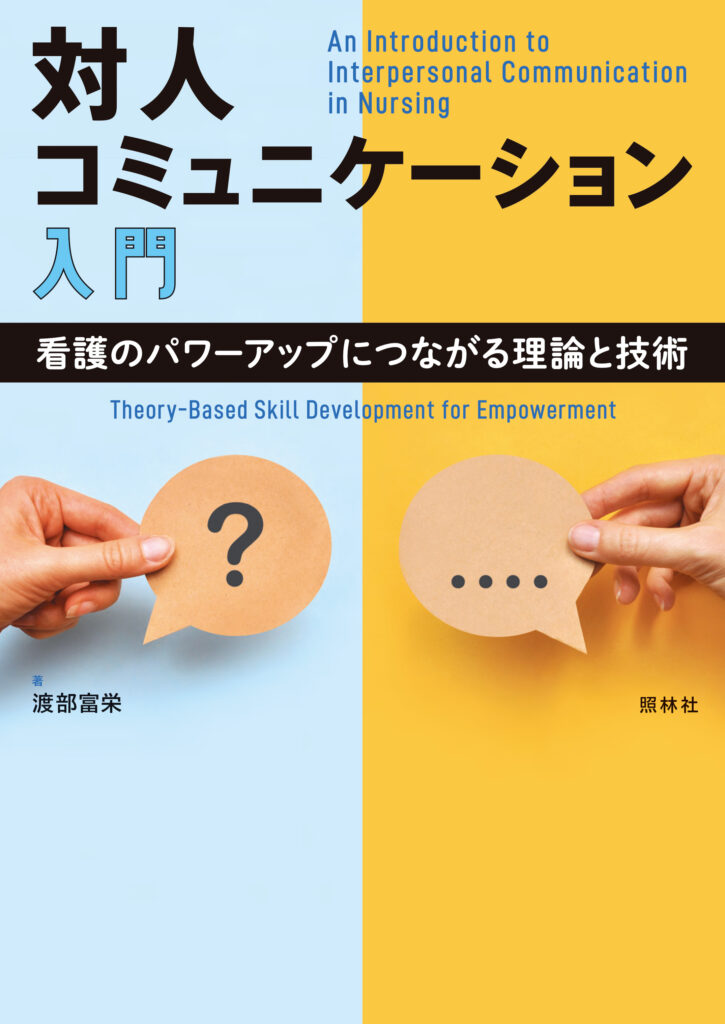
対人コミュニケーション入門
渡部富栄 著
照林社
B5判
2,860円(税込)
今回、看護師のおともさんが紹介してくれた本
『マンガでわかる看護の教育 はじめてのプリセプター,OJT』
『看護現場で「教える」人のための本 教える側と教わる側のミスマッチを防ぐために』
日々、患者さんに寄り添うあなたにも、やさしく寄り添うものがあってほしい。今回紹介した本たちが、そんなあなたの心の“おとも”になれることを願っています。
看護師のおともさんに、「悩みに合う本を教えてほしい」という方を募集中。
下記URLよりご応募ください。
※掲載の有無はエキスパートナース編集部で判断し、掲載有無の結果は事前にご連絡はいたしません。
https://questant.jp/q/book_therapy_otomo
当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。
そのほかの「悩める看護師に本を処方」の記事はこちら