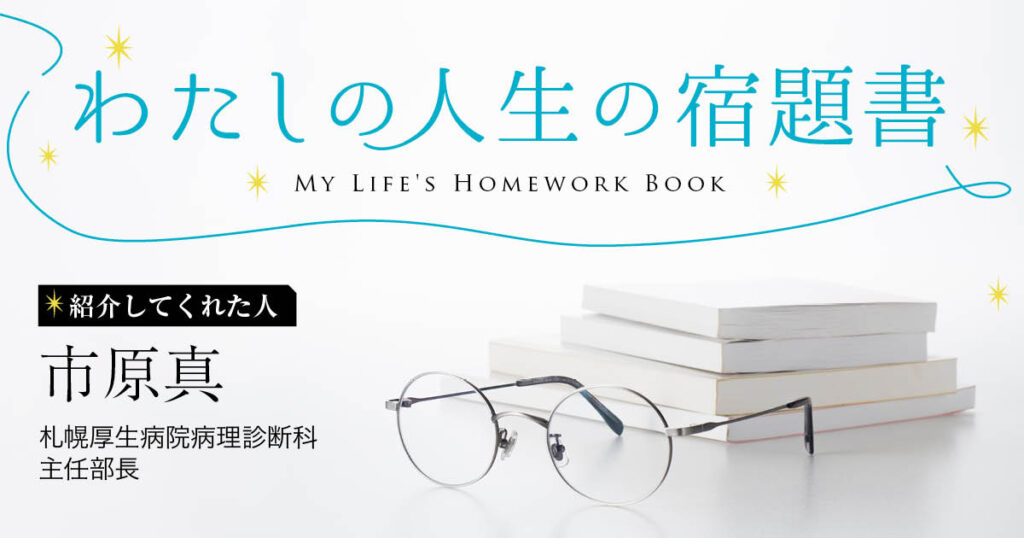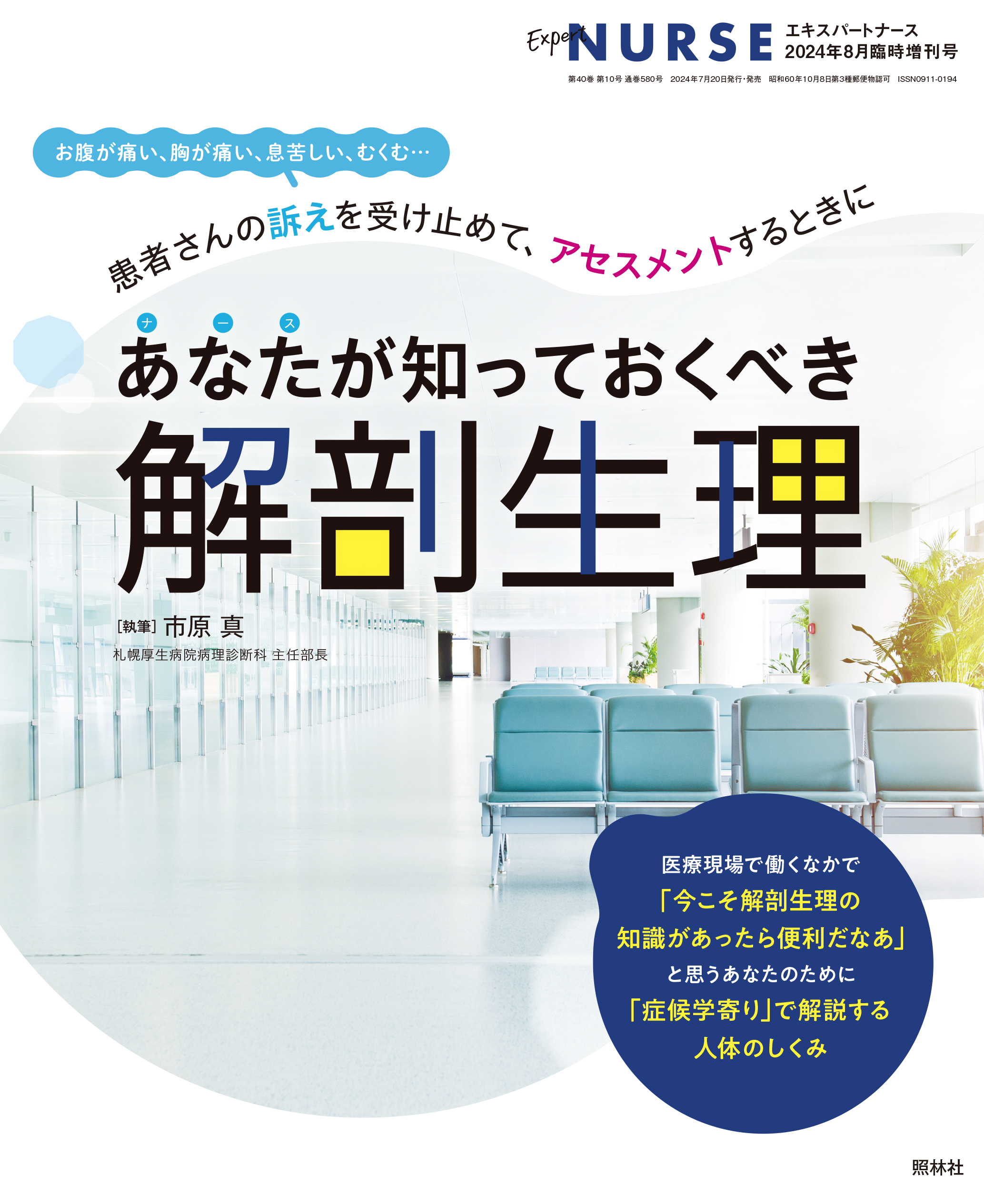気になるあの人が「残りの人生でぜひ読んでみたい」「もう一度読み返しておきたい」と心に刻んだ本をご紹介。病理医ヤンデル先生こと、市原真先生が選ぶ「人生の宿題書」とは?
*
人生の旅路で出合う本は、ときに道しるべとなり、ときに心を癒す力をもっています。
このシリーズでは、気になるあの人の「残りの人生でぜひ読んでみたい」「もう一度読み返しておきたい」と心に刻んだ、かけがえのない一冊をご紹介します。
それは、新たな視点を与えてくれるものかもしれませんし、過去に戻りながら自分を見つめ直す鍵となるかもしれません。
あなたにとっての「宿題書」は何ですか?
人生を豊かにする読書の旅へ、一緒に出かけましょう。
市原真先生の「人生の宿題書」
『多としての身体-医療実践における存在論《人類の転回》』
アネマリー・モル著、浜田明範、田口陽子訳、水声社、2016年
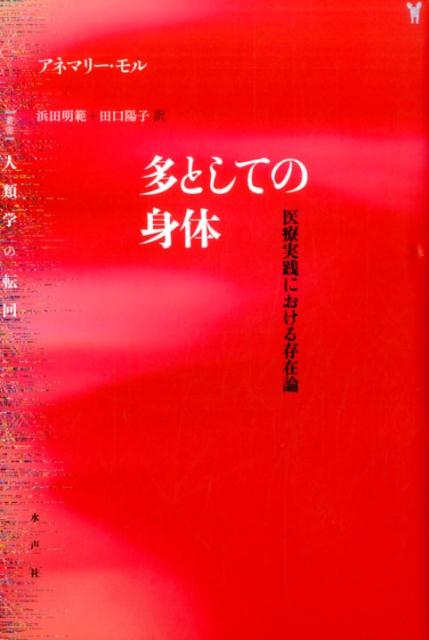
『芝公園六角堂跡 狂える藤澤清造の残影』
西村賢太著、文春文庫、2020年
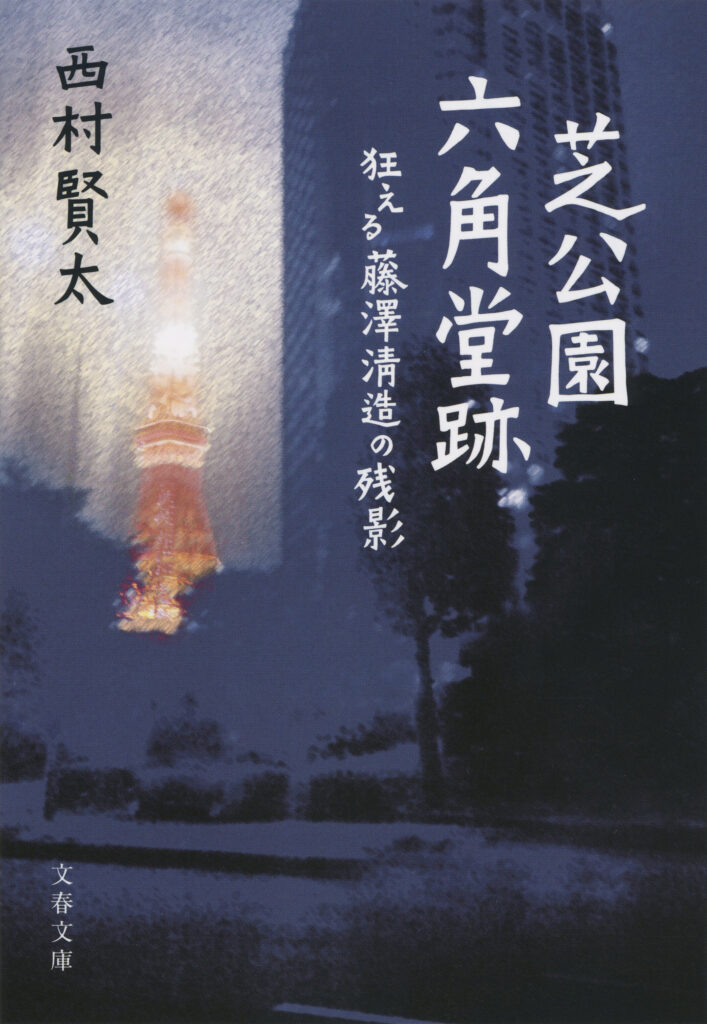
自分の体験のためだけに本を読めれば、一番いいと思うのだけれど、私は俗っぽくて、「これを読んだことがあると言えばカッコいいだろう、自慢できるだろう」という欲望によって本を読む。あの哲学書も、あの長編小説も、そういう理由で読んだ。うわついたまま、よそ行きの顔で。もちろん内容なんて覚えていない。もったいない。
そんな虚構の日々に手にした一冊、アネマリー・モル『多としての身体』(水声社)。読んでいるうちにだんだん、「これは読み飛ばしてはいけない本だ」という気持ちにさせられた。医療の現場において、「私が何をどのようにみるか」ではなく、「私にとって何がどのようにあるか」を考える。病理医である私の思考は認識論とか記号学に向かいがちなのだが、そこをゆさぶってくる本。カッコつけるための読書から卒業できたら、もう一度読みたい。
それともう一冊、西村賢太『芝公園六角堂跡』(文春文庫)。ある書評家が、西村賢太の死後、賢太、賢太と馴れ馴れしく連呼しているのを見て、なんだか冷めてしまって、購入のタイミングを逃した。「カッコ悪い人が読めと言ったから読まない」という理屈であった。そろそろ読みたい。
初出:『別冊エキスパートナースプラス』(2025年、照林社)