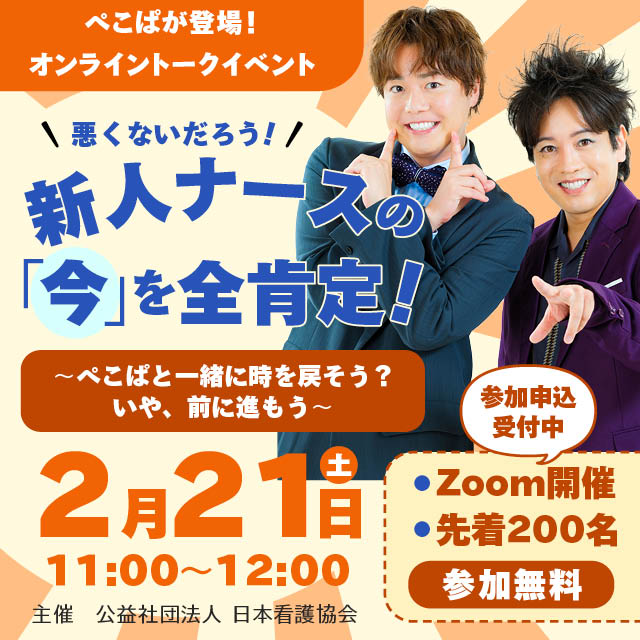日本看護協会会長の秋山智弥氏と看護師で参議院議員の石田昌宏氏の特別対談をお届けします。業務の増加や人手不足といった構造的変化を乗り越え、看護のやりがいを取り戻すためにできることとは?

秋山智弥あきやま ともや
日本看護協会 会長
1992年東京大学医学部附属病院に就職後、京都大学医学部附属病院病院長補佐・看護部長、岩手医科大学看護学部特任教授などを歴任。2025年より日本看護協会 会長に就任。

石田昌宏いしだ まさひろ
参議院議員
聖路加国際病院、東京武蔵野病院にて看護師として勤務。衆議院議員秘書を経て、1995年より公益社団法人日本看護協会に勤務、1998年政策企画室長。2005年日本看護連盟幹事長。2013年7月参議院選挙比例代表(全国区)にて初当選。参議院厚生労働委員長等を歴任。現在3期目。
「忙しすぎてベッドサイドに行けない」「記録ばかりに追われ、患者さんと向き合う時間がない」「本来の看護ができているのか」――。多くの看護師が日々感じるこのような思いは、決して個人の努力不足から生まれたものではないはずです。医療安全の徹底による業務手順の標準化、診療報酬制度に伴う記録の増加、医療提供体制の機能分化、そして医療現場における人員不足など、現場を取り巻く構造的な変化が、看護師の「やりがい」を削ぎ落とし「不全感」につながっている一面もあります。
しかし、こうした不全感を抱くことの裏には、まだまだこうありたいという看護への強い想いがあるといえます。日本看護協会会長の秋山智弥氏と看護師で参議院議員の石田昌宏氏に、不全感を希望へと変えるために何ができるのかをうかがいました。
やりがいを取り戻すためのヒントは、じつは現場のなかにこそあります。いままさに、悩みや迷いを抱えながら医療現場に立つ、すべての看護師に向けた提案とエールにあふれた対談です。
現場の看護師が感じる「不全感」や「疲弊感」の背景にあるものは?
―最近、現場の看護師からは「ベッドサイドに行けない」「記録や診療報酬対応に縛られている」という声を聞きます。看護師が感じる「不全感」や「疲弊感」についてどのようにお考えですか?
石田 仕事の「不全感」はたしかにあると思います。自分の1日の時間をコントロールできていない感覚が強いのではないでしょうか。その背景には、記録や安全管理など「やらねばならない」業務が増えていることがあると思います。ベッドサイドで患者さんと会話し、観察から判断を積み重ね、手を差し伸べる時間のほうが看護の醍醐味なのに、そこが削られてしまう。記録は特に「証拠づくり」として強調されがちで、「何のために書くのか」が納得できないままでは仕事に対する不全感が残るでしょう。
秋山 仕事に対する「疲弊感」は、人員不足や超過勤務など物理的要因が大きいと思います。一方、「不全感」は「あるべき看護像」と現実のギャップから生じます。逆に言えば、不全感を抱いている限り理想像が残っている証拠。だからこそ希望もあると私は思います。
「不全感」の原因につながる医療安全の徹底と医療提供体制の機能分化
秋山 2000年以降、医療安全を背景に「標準化」が一気に進みました。以前は看護師が創意工夫し、限られた資源をやり繰りしてケアをしていた。しかし、医療事故を契機に「標準から逸脱した手順は禁止」となり、創意工夫の余地は消えた。記録も自由に書けず、責任追及を恐れて形式化しました。これが不全感を強めた大きな要因だと思います。
石田 現在の医療提供体制は、急性期・回復期・慢性期・在宅と、機能分化が進んでいます。医療資源の制約がある以上、一定の機能分化は避けられません。問題は、分化に対応した看護提供体制が整っていないことです。急性期では入退院が極端に短く、患者さんと信頼関係を築く時間がない。術前から寛解までゆっくりかかわれた時代とは大きく違います。
秋山 その結果、急性期では「患者をつないでいくときに十分なケアができない」という不全感が強まります。これを補うには、急性期の看護師が外来や在宅とも連携し、ケアを一本の線につなぐ必要があると思います。
「不全感」を解消するヒントは、1人の看護師がさまざまな役割を担うこと
石田 COVID-19が流行する前に、新潟県・佐渡島にある佐渡総合病院に行ったことがあります。島で事実上、唯一の急性期病院で、人手不足や人口減少で看護師ももうこれ以上は増やせないとみんな疲れ切っている感じだったのですが、COVID-19の流行が落ち着いた後にもう一度行ったら、全然雰囲気が違いました。同じナースたちなのに、顔つきが明るい。
背景には、人を増やせないから「1人の看護師がさまざま役割を担う」ように体制を切り替えたことがあったのです。一定年数以上の看護師を再教育して、外来もオペも精神科もできるようにした。だから、急に「外来に行って」とか「今日はオペに入って」とかフレキシブルに動けるようにしたんですね。
病棟の中だけでなく、外来で患者さんと接してから入院を受け持ったり、退院後にまた外来で会ったりするから、「この人の生活のなかにはこういう課題があるんだ」と実感できる。そうなると「もっと地域に出て直接、訪問看護をしたい」って声まで出てきたそうです。
そうせざるを得なかった背景があったとはいえ、結果的にナースたちの不全感を解消していたんです。本来の看護の面白さ、やりがいを取り戻せた。これはどこの病院でも応用できる話だと思います。

高齢化が進むなか、 医療安全は国民全体での議論が必要
秋山 医療安全については、看護師や病院だけでなく国民全体で議論すべき課題だと思います。転倒は家庭や街中でも起こり得ることなのに、病院内で起こると過度に管理責任が問われます。もちろん予測可能な範囲での転倒予防は必要ですが、「転倒させないために寝かせきりにする」というのは本末転倒です。
特に急性期では多種多様なチューブが入っていたり、リスクが高い状況も多く、歩行させるかどうかは慎重なアセスメントが必要です。ただし、抑制するのではなく、車椅子など他の手段も含めて「患者さんが動きたい」という思いに応える工夫をすべきです。
この問題は看護師だけでは解決できません。本来、そのチューブや治療自体が必要なのか、そもそも高度急性期治療をどこまで行うべきなのか――入院前の段階から医療従事者全体で議論すべきです。しかし現状では、そこに看護師が十分にかかわれていません。
高齢化が進むなか、認知症なども含めて転倒リスクは増えています。だからこそ、「どこまで治療をすべきか・しないべきか」「自宅でどういう生活を送るのがその人にとって望ましいのか」といったことを、国民全体で話し合い、合意形成していく必要があると思います。
「患者中心」ではなく「患者思い中心」の医療へ
石田 国民全体で話し合うことと同時に、「患者中心」ではなく「患者思い中心」の医療にしていくことが重要だと考えています。患者さん自身を真ん中に置くのではなく、その人が「入院で何をしたいのか」「どう生きたいのか」という思いを中心にすえる。その思いをかなえるために、専門職だけでなく患者さん本人や家族もチームの一員として主体的にかかわる――そうした「思い中心のチーム医療」が必要です。
患者や家族もケアを提供する側だと認識できれば、エラーが起きても責め合うのではなく、一緒に改善していく発想に変わります。私たちは単なるサービス業ではなく、共に目標を達成するチームだという感覚を社会に広げることが大切です。
看護師は何をする人?―「見守り・手当て・声かけ」の3つが看護の中心
―社会全体で医療についての議論をしていくなかで、「看護とは何か」「看護師とはどんなことをするのか」ということについても、問われていきそうです。
秋山 看護師の軸は、医師をはじめ他職種がスポットでかかわるのとは異なり、“点と点をつなぐ”ようにずっとかかわり続けることだと考えています。患者さんを常に連続した線で見ていく。診療の補助も療養上の世話も一連の流れのなかに含まれます。そこが看護の一番の特徴だと思います。
しかし、本来大切な「見守り」が現場でできにくくなってきており、それが不全感につながっているのではないでしょうか。処置や点滴といった診療の補助が増える一方で、療養上の世話を行って、患者さんの変化を連続的に追っていくことが後回しになりがちです。
看護の醍醐味は、患者さん1人ひとりの「ベースライン」を理解し、「そろそろトイレの時間だな」「痛み止めが切れてきそうだな」と先読みして先手を打つこと。そういうことができるのは、持続的にモニターしているからなんです。でも、その時間が急性期を中心に減ってきている。だからこそ、人員配置をもっと手厚くしなければならないと考えています。
私は「見守り・手当て・声かけ」の3つが看護の中心だと考えています。「寄り添う」ということは、これらすべてのなかに含まれます。この3つがそろってこそ患者さんへの寄り添いになるし、逆に欠けてくると看護師自身の不全感につながると思います。
看護師がいるから何も起こらない。「著変なし」という言葉の裏側にある看護
秋山 看護師の「見守り」の成果は、「著変なし」と看護記録に記されることに現れています。「著変なし」という4文字は、無数の観察に支えられているものなのです。
排泄物を片づけながら消化器の状態を見たり、食事の食べ残しを自分の目で確認して栄養状態をアセスメントしたり、入浴や着替えのときに皮膚やむくみを観察したり。生活援助の1つひとつが大切な観察の機会ですよね。
看護補助者に任せきりにしてしまうと、そうした観察が抜け落ちて、異常が患者さんの自覚症状として出てくるまで気づけないこともある。患者さんが「苦しい」「痛い」と言う段階では、もうかなり悪化してしまっていることもあります。
看護師がきちんとかかわっているからこそ「著変なし」で済んでいる。逆に言えば、看護の機能がはたらいていないと合併症や褥瘡の発生、在院日数の延長、身体拘束率の増加につながります。患者さんに「何も起きなかった」という結果をもたらすこと自体が、看護の大きな成果なんです。
石田 「寄り添い」というのは、結局は相手に「関心」をもつことです。患者の思いや方向に自分のベクトルを合わせられるかどうか。関心の深さが看護の質を決め、得られる情報量を左右します。ケアは「Take care」の言葉どおり、“気にかけること”。ここが看護の根本だと思います。
タスクシフトとAIとの向き合い方
―看護師の「見守り」は重要ですが、タスクシフト・タスクシェアは確実に進んでいます。
秋山 療養上の世話には、やはり看護師にしかできない部分があります。ですから、例えばこれまで看護師2人で担っていた業務を、看護師1人と看護補助者1人のペアにして進める。その際、観察やアセスメントは必ず看護師が行い、看護補助者にはどの部分を任せられるのか、その判断まで含めて看護師が責任をもつことが重要だと考えています。
石田 技術をどう活用するかという点も大事だと思います。ITやAIを活かせば、これまで看護師1人が1人の患者しか見られなかったのを、複数同時に見守ることも可能になるかもしれません。
秋山 ただし、AIに頼りすぎるのはリスクがあります。AIは看護師が入力したデータを基に評価しているにすぎません。もし看護師がアセスメントを手放してしまえば、AIはAIの出した結果を参照する“自己循環”に陥り、評価がゆがむ危険性が出てくるでしょう。未知の症例や新しい治療への対応も、AIには限界があります。
石田 だからこそ、AIを活用しながら、その評価をさらに深掘りしていくのが看護師の役割だと思います。標準化は安全性の向上に不可欠ですが、その枠から外れた「逸脱」の場面にどう対応するかが、人間にしかできない重要な仕事です。AIや標準化に任せられる部分を任せ、浮いた時間をイレギュラーへの対応に振り向けることで、看護の質をさらに高めていけるはずです。
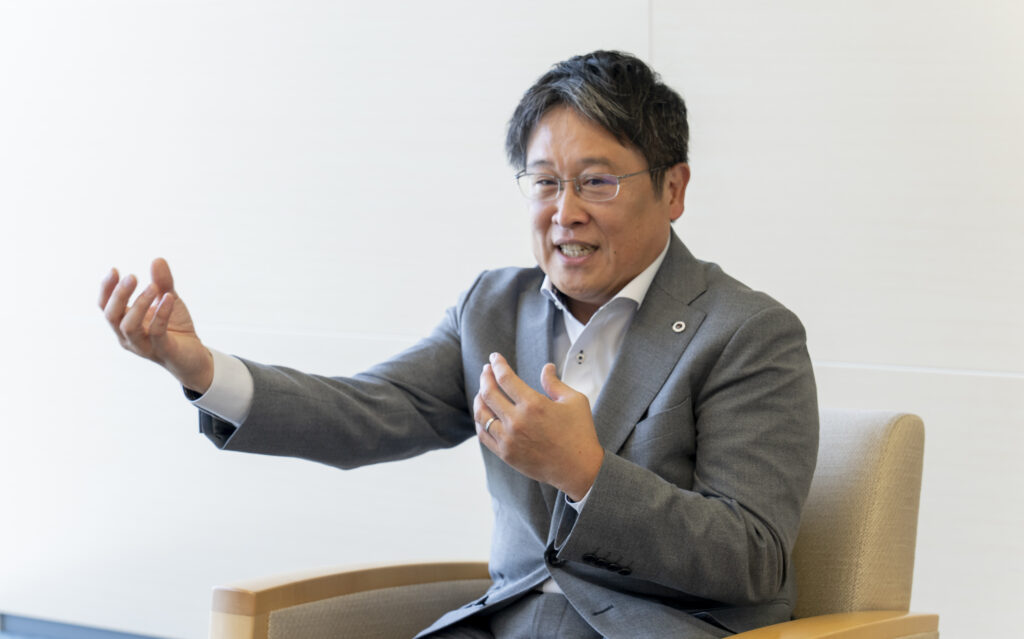
AIに振り回されないために重要なのが、 症例検討とカンファレンス
石田 AIに振り回されないためにも、やはり症例検討や深いカンファレンスが欠かせません。現場には多くのカンファレンスがありますが、情報共有で終わっていることが多い。「なぜ」を突き詰め、徹底的に議論する場が必要です。月に1度でもよいので、患者さんを1人取り上げて、2時間でも3時間でもとことん話し合う。それを繰り返すだけでも現場の見方は変わっていきます。
時間がないとよく言われますが、やり方次第でつくれる時間はあると思います。1時間を区切ってスタッフごとに「ベッドサイドで必ず患者と向き合う時間」と決めているところもありました。業務を圧縮してでも、濃密な時間をつくる。そのメリハリが不全感を減らす鍵になると思います。
秋山 新人教育でも同じです。患者を一定期間継続して受け持ち、ケースレポートを書き、発表する機会をつくる。それを通じてベースラインをつかむ力や、チームに伝える力が養われます。多職種とのカンファレンスも不可欠で、異なる専門性の視点を知ることで、自分の考えに限界をつくらずに済む。これは大学教育から取り入れていくべき学際的な学びだと思います。
看護は、自分自身も成長できる、すばらしい仕事
―最後に読者に向けてのメッセージをお願いします。
秋山 看護師としての経験から言えることは、この仕事はすばらしいということです。患者さんにケアを提供するだけでなく、その過程で自分自身も多くを学び、成長できます。1人ひとり違う苦しみやつらさを完全に理解することはできませんが、寄り添うなかで少しでも患者さんの負担を軽くできれば、それが看護師自身の糧にもなるのです。
ただし感情労働であるがゆえに、患者さんの苦しみを背負い込みすぎるとバーンアウトにつながります。だからこそ、言葉にしたり、カンファレンスで語り合ったりして昇華することが必要です。そうして鍛えられた看護力は、次の患者さんによりよいケアを届ける力になります。不全感を抱くこと自体が、看護師が関心をもち、寄り添っている証。それを力に変えるために、仲間と語り合う機会を増やしてほしいと思います。
石田 私も同感です。看護は患者さんを幸せにするだけでなく、看護師自身が成長を続けられる仕事です。そのことを実感できる環境を整えることが、私たちの役割だと思っています。急には変わらなくても、数年後に「昔よりもよくなった」と感じられるよう、環境づくりを進めていきたいと思います。
初出:『エキスパートナース』2025年12月号(照林社)
※当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。