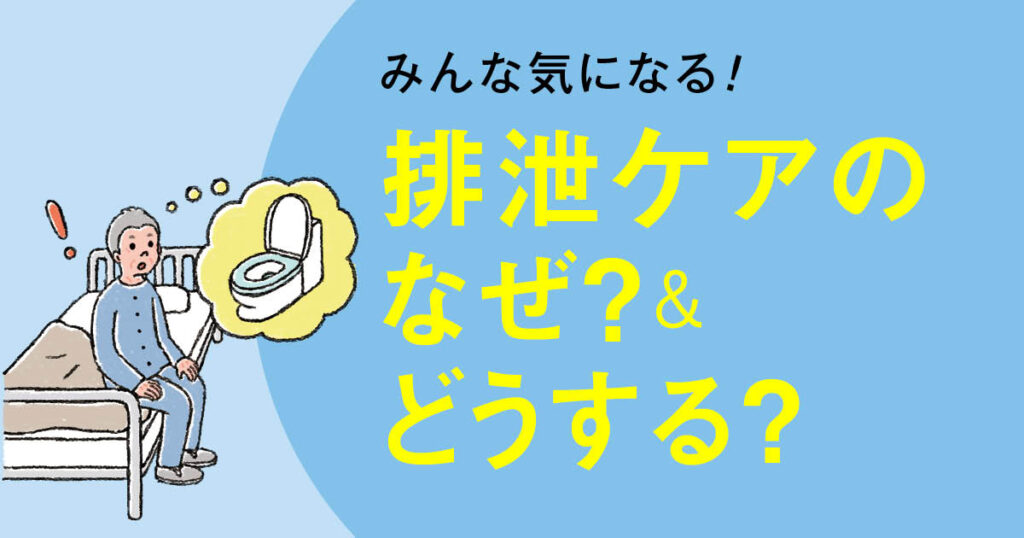便秘の患者さんに対してX線画像を撮る理由とは?ハウストラ形成、大蠕動など便秘のアセスメントに必要な便生成の基礎知識に着目しながら解説します!
便秘でX線画像を撮る理由とは?
●腹部単純X線撮影により、便やガスの量・形態・存在部位を確認できる。
●便の貯留パターンと画像の特徴をおさえておこう。
便秘症を有する患者さんに対して診察する際の補助診断の1つとして、筆者は腹部単純X線撮影(以下、腹単)を愛用してきました。本稿では、この検査によって実際に何がわかるのかということを、解剖や生理学的基礎知識をふまえて解説します。
画像で大腸内の便・ガスの量・形態・存在部位を確認
大腸は、腹腔内に存在する結腸と骨盤内に存在する直腸からなります。腹部単純X線撮影検査(腹単)では、大腸内の便・ガスを観察し、量や形態および存在部位を評価します。
便・ガスの量のみかた
量は面積(横径のみで代用)から判断します。部位による横径差がないものは拡張しているといえ、横径6.5cm以上の病的拡張は巨大結腸や巨大直腸1といえます。
便の形態のみかた
腹単で認める便の形態には、有形便と無形便があります。有形便として、コロコロ状(兎糞状)、平坦状、塊状、大きな糞石があり、無形便には不整形、壁付着性があります。 腸管内に便が充満する場合には有形、無形のそれぞれがあります。
便の存在部位のみかた
便の存在部位の評価には、盲腸-上行結腸-横行結腸-下行結腸-S状結腸-直腸(図1)と解剖区分ごとについて行ったり、経口マーカーに対して行われるように右(上行結腸-横行結腸近位)、左(横行結腸遠位-下行結腸)、中央(S状結腸)、骨盤(直腸)と画像を4分割して行う場合があります。
図1 大腸の構造とハウストラ

筆者は後述するように直腸や下行結腸を重視することから、解剖区分を推測して観察するようにしています。
便秘のアセスメントに必要な便生成の基礎知識
結腸運動(ハウストラ形成)とは?
回盲弁を通過して上行結腸に便が移入した際は、便はまだ流動体です。上行結腸から横行結腸までは分節運動、蠕動、逆蠕動により、ゆっくりと 8~15時間かけて進みます。
分節運動は、ハウストラ(結腸膨起、腸管の収縮と隣接部の袋状に広がった状態、図1)として観察されます。内容物が行ったり来たりして、水分の吸収が行われるなかで便が形成されていきます。
大蠕動
連鎖した蠕動により、横行結腸からS状結腸まで一気に便が移送します。大蠕動は、1~3回/日生じ、10~30分間続きます。
一番起こりやすいのは朝食後1時間以内です。
胃に食物が入り、胃壁が拡張するとその感覚刺激が壁外系の交感神経(椎前神経節)に伝達され、その作用を止めさせます2。それにより、便が横行結腸から下行結腸へ移動しやすくなり、連鎖した蠕動を引き起こすのです。これを胃結腸反射と呼びます(図2)。
腸管蠕動は独立した壁内神経系のはたらきによるものですが、自律神経系の影響を強く受けているのです。
図2 排便時の直腸のしくみ

大腸を支配する自律神経
大腸を支配する自律神経についてもう少し詳しく説明しましょう(図3)。
図3 大腸を支配する交感神経と副交感神経

副交感神経としては横行結腸までは第X脳神経の迷走神経が支配し、摂食─ 消化と関連をもつ機能を司っています。下行結腸 ・S状結腸 ・ 直腸は骨盤内臓神経(S2-S4)系が支配し、排便との関連をもつ機能を司っています。骨盤神経は直腸を密に支配し、一部は上行してS状結腸 ・ 下行結腸を支配しています。
交感神経系は横行結腸までは大・小内臓神経 – 腹腔神経節(T5-T11)由来であり、下行結腸、S状結腸、直腸は腰内臓神経-下腸間膜動脈神経節(L1-L3)3由来です。
交感神経は腸管の支配動脈に伴走し、大腸全域を一様に支配しています。下行結腸に限っては、副交感神経の支配様式が疎であることから交感神経の支配が優位と考えられています。交感神経が優位とされる日中やストレス時は、横行結腸から下行結腸への便移送は抑止されています。交感神経の役割を、脊椎生物の生態様式からみてみます。
脊椎生物は、上位捕食者から襲われ逃避するときや、逆に獲物を襲い捕食するときは、交感神経系が優位になります。この際、腸管への血流を乏しくし、大腸の運動は抑制されますが、反対に心臓 ・ 肺 ・ 骨格筋への血液は増加することで運動機能を高めることになります。トリが飛び立つ前の脱糞やヒトが朝食摂取後に排便することは、身を軽くし、日中活動(交感神経優位)を行うのに有利にはたらくと思われます。
大腸の便貯留機能
結腸(特に盲腸)には内容物(便)を受け入れた際に、腸管(筋)が弛緩し、内圧を上昇させない受容性弛緩4や、直腸のように便が入ると一時的に内圧が上昇し、その後に管壁が弛緩して正常圧に戻る適応性弛緩4がみられます。
この機能があるために、便秘症が慢性化した場合は腸管が拡張し、さらに巨大化することになります。下行結腸は貯留能よりも通過腸としての側面が強く、健常人では腸管径が細く、便貯留がみられません。したがって、下行結腸に便が存在すると便秘症を疑い、拡張を認めると便秘症と診断できるのです。
便秘症でX線画像を撮影するときの姿勢は?
腹部単純X線撮影検査¥の撮影の種類には、立位と臥位があります。前者はイレウスに対して、便秘症に対しては後者が勧められます。しかも、横隔膜よりも骨盤を含むKUB(kidney ureter bladder:腎尿管膀胱部) 5 単純撮影に準じ、骨盤骨の全体が収まるものがよいといえます。
その理由は、直腸の評価が立位では圧縮されてわかりにくくなりますが、臥位では広がって描出されるからです。
腹単での便は実質性の灰色に見える
腹部単純X線撮影検査では便自体は実質性で灰色に見え、臓器と鑑別できませんが、含まれるガスが黒く存在し微細状顆粒5 として見えます。また、三日月状のガスが存在するときは、傍にある塊状便が間接的に同定できます。 ガスが多量の場合は、壁に便が付着した状態のときはすりガラス状に描出され、ガスのみのときは腸管自体の形態が明瞭に描出されます。
便の貯留のパターンは?
便秘が主訴の腹単において、みられる便の貯留は7パターンあります(図4)。下行結腸に便の貯留(④・⑥・➆)が多ければ、慢性便秘症を疑います。
図4 便の貯留パターン

①直腸性便秘症
直腸(➂・④・➆)に便が貯留すると、直腸性便秘症(『慢性便秘症診療ガイドライン 2017』6による排便困難型、図5)を疑いますが、健常者であっても排便前には便が貯留しているので、常に撮影時が排便前か後かは配慮する必要があります。
図5 直腸性便秘症(図4パターン➂)

②弛緩性便秘
この記事は会員限定記事です。