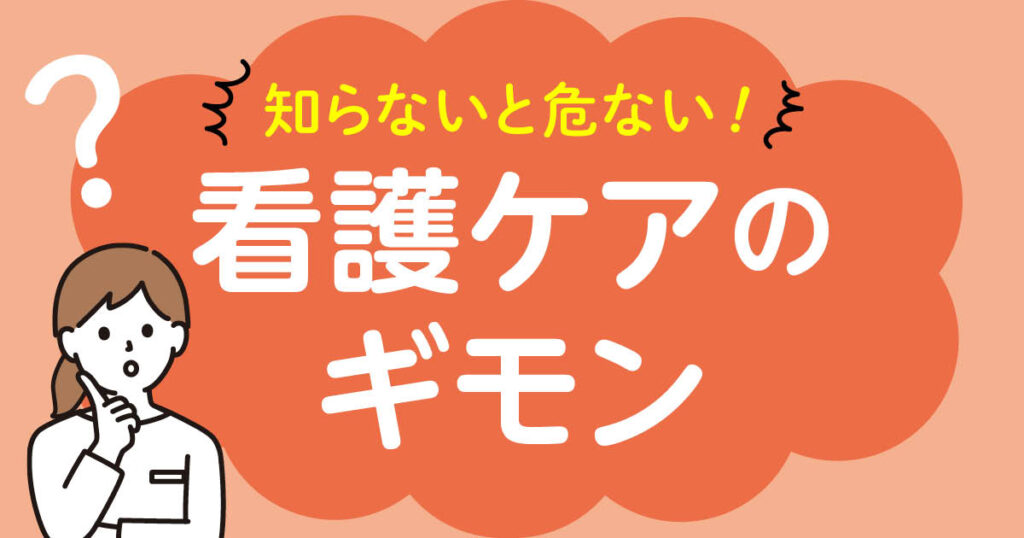抗菌薬の薬物血中濃度測定(TDM)の目的とは?測定値の注意点は?看護師が知っておきたいTDMのポイントを詳しく解説します。
Q. 抗菌薬の薬物血中濃度測定(TDM)のポイントは?
ひとこと回答
正しい測定値を出すために、採血タイミングを遵守し、投与・採血時刻を正確に伝えることが必須です。
目的は、薬物投与時の効果と副作用のチェック
一般的に、TDMは“薬物治療モニタリング”と呼ばれ、臨床薬物動態学の観点から、血中の薬物濃度を測定して治療方針を決め、薬物の治療効果や副作用を確認しながら適切な薬物投与を行う手法です1。
TDMが必要な薬物として、抗菌薬が挙げられます。特にアミノグリコシド系抗菌薬(ゲンタマイシンやアルベカシンなど)やグリコペプチド系抗菌薬(バンコマイシンやテイコプラニン)は、血中濃度と治療効果・副作用発現が相関し、有効域と中毒域が近く副作用を起こしやすいため、TDMが行われています。
正しいタイミングでの実施が検査のカギ
薬物血中濃度測定時は、「投与」と「採血」のタイミングが重要です。例えばバンコマイシンは、通常、1日2回、60分以上かけて投与し(red neck症候群*1等の副作用を避けるため)、血中濃度が一定のレベルに保たれている定常状態の時期である投与4~5回(3~4日目)の点滴投与の30分前(トラフ値)と投与終了後と1~2時間後(ピーク値)に採血を行います(図1)。
この記事は会員限定記事です。