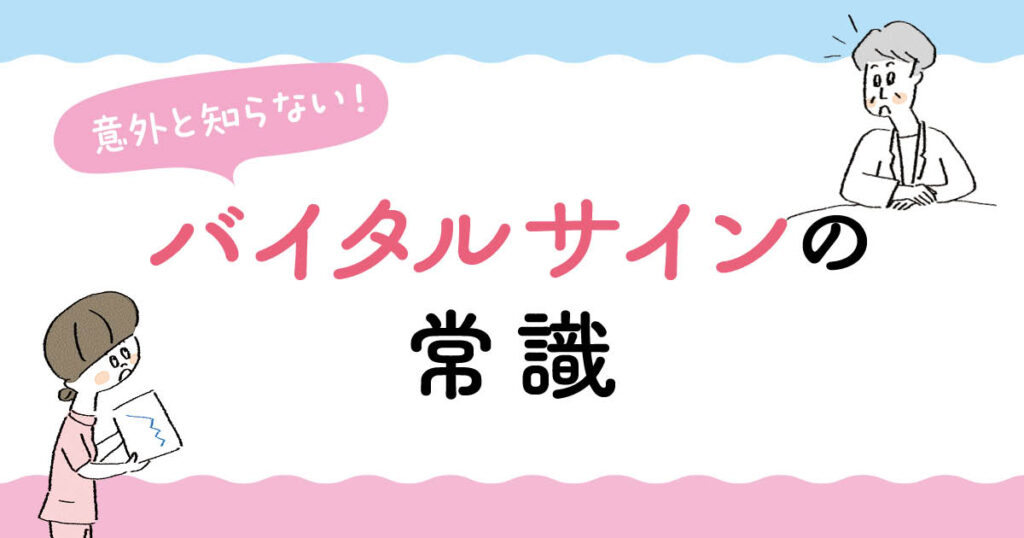バイタルサイン数値の“測定手技”や“判断の根拠”をわかりやすく紹介する全16回の連載。「深部体温測定時の注意点」「呼吸数を1分間実測するのはなぜ?」など、知りたいポイントが満載です。
【第1回】深部体温測定時の注意点
〈目次〉
●深部体温を測定時の注意点は?
①体温計の感温部を腋窩中央のくぼみに正確に当たるようにする
②上腕と体幹を密着させることで腋窩を閉ざした状態を維持する
③汗の気化熱に注意する
④外気温が低い環境で腋窩が解放された状態が長く続いた場合、密着時間をつくってから測定する
●高齢者、子供の深部体温測定時の注意点は?
【第2回】発熱時のクーリングの有効性
〈目次〉
●体温調節のしくみ
・発熱のメカニズムとは?
●発熱時のクーリングの目的
●発熱時のクーリングによるリスク
●発熱時のクーリングが有効な場合とは?
【第3回】解熱の必要性を判断するポイントは?
〈目次〉
●体温の個人差に関する研究の結果は?
●発熱による身体への負担
●“解熱したこと”を確認できるポイントは1~2日
【第4回】脈拍測定から血圧を推測するには?
〈目次〉
●心機能や血流の異常を示す脈が測定できないときは?
●脈拍から血圧を推測するには?
・脈の触れる“強さ”からの推測
・急変時に触知するべき脈の部位
【第5回】モニター心電図の心拍数と実測の脈拍数が異なる原因は?
〈目次〉
●モニター心電図の心拍数と実測の脈拍値に違いが出る理由は?
●患者自身の心拍数と脈拍数に違いが出る例
・心室細動(Vf)が起こった場合
・心機能の低下により脈拍欠損が起こった場合
●モニターの問題で心拍数と脈拍数に違いが出る例
【第6回】頻呼吸の回数は?呼吸数を1分間実測するのはなぜ?
〈目次〉
●頻呼吸と徐呼吸の呼吸数は?
●呼吸数を1分間実測する理由は?
●ただしい呼吸数だけで病態を予測するのは難しい
【第7回】呼吸数を1分間うまく実測するには?
〈目次〉
●呼吸数を1分間実測するときの注意点
●呼吸状態を観察するポイント
【第8回】中枢の異常が呼吸数低下の原因に
〈目次〉
●呼吸数低下の原因とは?
●呼吸が保たれるメカニズム
【第9回】死戦期呼吸とは?『JRC蘇生ガイドライン2020』での対応
〈目次〉
●死線期呼吸は心停止後数分間に生じる
●呼吸の確認は10秒以内に
【第10回】血圧の下げすぎに注意!降圧管理目標の現在のエビデンス
〈目次〉
●高血圧患者の人数
●『高血圧治療ガイドライン2019』における降圧目標
●生活習慣の見直しを行うことの重要性は変わらない
【第11回】電子血圧計の測定値の注意点
〈目次〉
●自動血圧計が普及してきた背景とは?
●自動血圧計の正確性の検証が必要
●不整脈患者への自動血圧計の使用は要注意
【第12回】乳がん術後、シャント肢、麻痺の場合、血圧測定の血圧測定はどうする?
〈目次〉
●シャント肢の場合の血圧測定の注意点は?
●乳がん術後の血圧測定の方法は?
●麻痺がある場合の血圧測定の注意点は?
●両側乳がんの術後の場合の血圧測定はどうする?
【第13回】血圧調整の影響因子と変動の範囲
〈目次〉
●血圧調整の影響因子は?
●収縮期血圧の変動幅の正常範囲は?
●血圧測定の正しい方法は?
【第14回】血圧の24時間モニタリング測定の必要性と注意点
〈目次〉
・24時間モニタリングの必要性
・24時間モニタリング時の観察・注意点
・カフ装着部位の皮膚の観察
・24時間モニタリングの再検討
【第15回】バイタルサイン測定の頻度の決め方
〈目次〉
●バイタルサインを測定する頻度は?
●早期警告スコアリングシステム「NEWS」とは?
・重篤患者を発見するためのシステム
・呼吸数では「8回/分以下」「25回/分以上」で“1時間に1回以上の観察”
・モニタリングが必要な患者さんの判断にも役立つ
【最終回】終末期のバイタルサイン変化
〈目次〉
・終末期のバイタルサイン変化に関するさまざまな研究
・「呼吸」と「意識レベル」が重要と考えられる