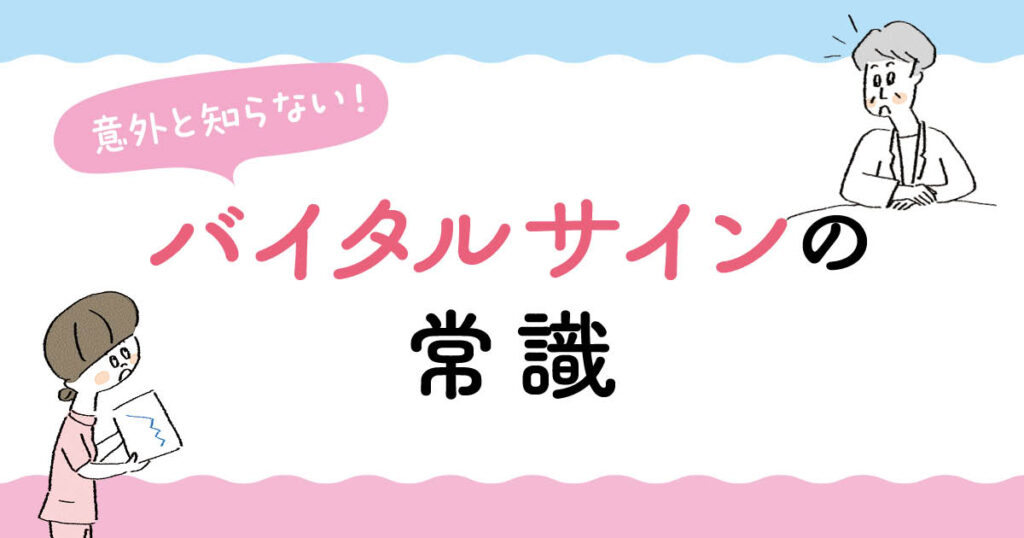熱が続く場合、解熱が必要かどうか判断するポイントを紹介。体温の個人差や発熱による身体への負担などについても解説します。
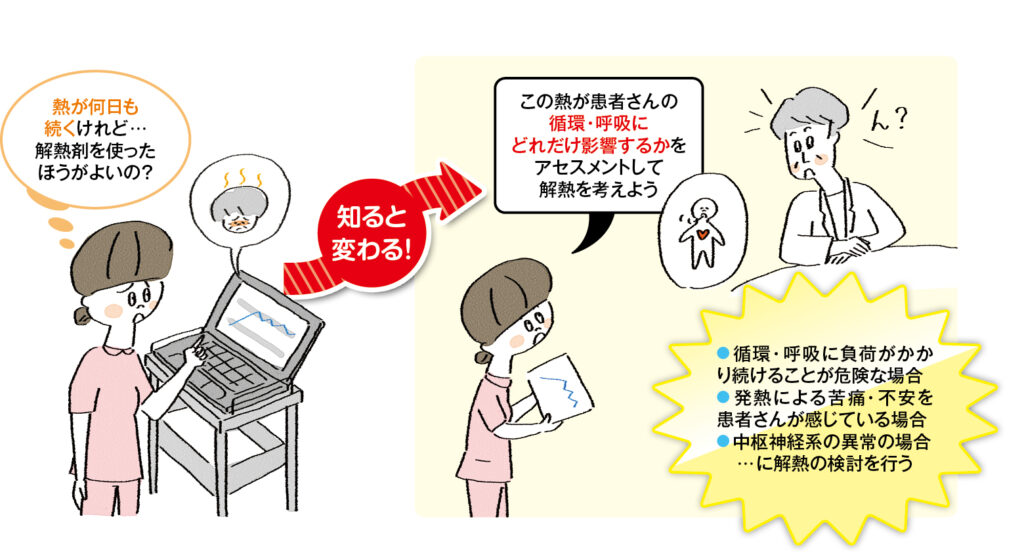
体温の個人差に関する研究の結果は?
小学4年生~高校3年生の健康な男子を対象に起床時の口腔温*を測定した研究1では、「小学生」は35.30 ~ 37.40℃の間に分布し、平均値が36.36℃(標準偏差0.33℃)、最頻値36.4℃でした。
「中学生」は35.45~37.14℃で、平均値は36.28℃(標準偏差0.23℃)、最頻値は36.2℃で、「高校生」は、35.40~36.72℃の間に分布し、平均値は36.25℃(標準偏差0.3℃)、最頻値は36.3℃でした。
また、小学3~5年生220名を対象とした日内変動の調査2では、日内変動について女子の体温をみると、起床時3.5%であった37.0℃以上の“高体温傾向群”が、帰りの会の時間(15:25)には56.9%になっていました。
これらの研究は小児を対象とした結果ですが、体温の日内リズムの振幅は7歳を過ぎると成人の値と有意差はないという報告があります3。
これらのことから、安静時の体温、日内変動ともに、ふだんの体温には個人差が大きいことがわかります。一般的に、ふだんの体温との差が1℃以上高い場合がその人にとっての有熱状態と定義されていますが、発熱状態と判断するには、ふだんの体温に加え、体温の変動状態にも注意する必要があります。
*口腔温は一般的に腋窩より0.5℃高い。
発熱による身体への負担とは?
一般的に体温が1℃上昇すると、脈拍数は8回/分程度増加し、代謝も13%程度増加します。酸素消費量も増え、呼吸も増加します。発熱はそれだけで患者さんに大きな負担をかけます。
そこで、心臓や呼吸機能に障害のある、または負荷がかかり続けることが危険だと判断される患者さんの場合、また、身体的な苦痛や不安を患者さんが感じている場合、心拍数や呼吸数を低下させ、これらの負担を軽減する目的で解熱する必要があります。
ほかにも、中枢神経系の異常等で、体温が41℃を超え細胞に障害を起こす可能性がある場合は解熱が必要です。
しかし、発熱は身体の防衛反応の1つであることや、解熱処置自体が患者さんの身体に負担をかけることを考えると、解熱処置には慎重な判断が必要です。
解熱の経過を確認するポイントは?
この記事は会員限定記事です。