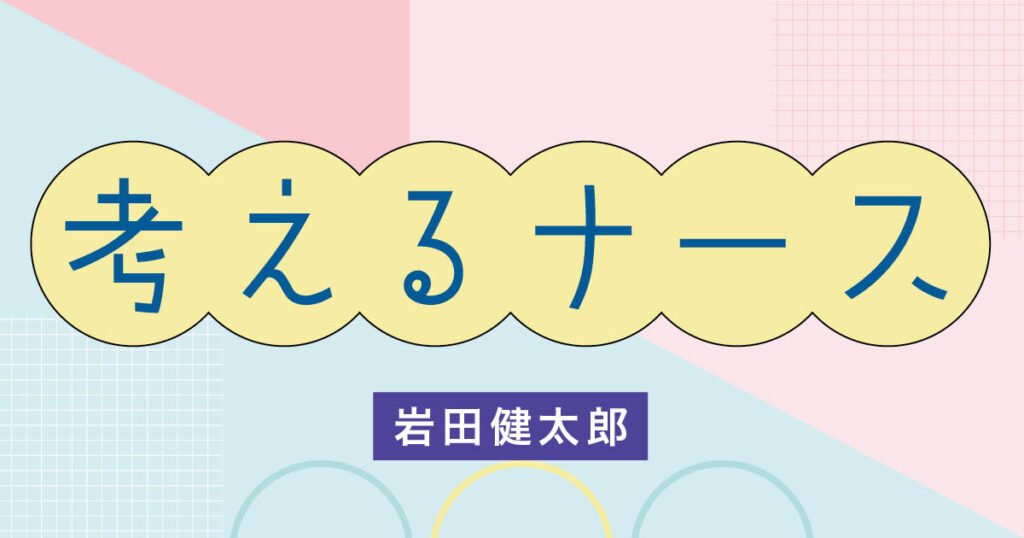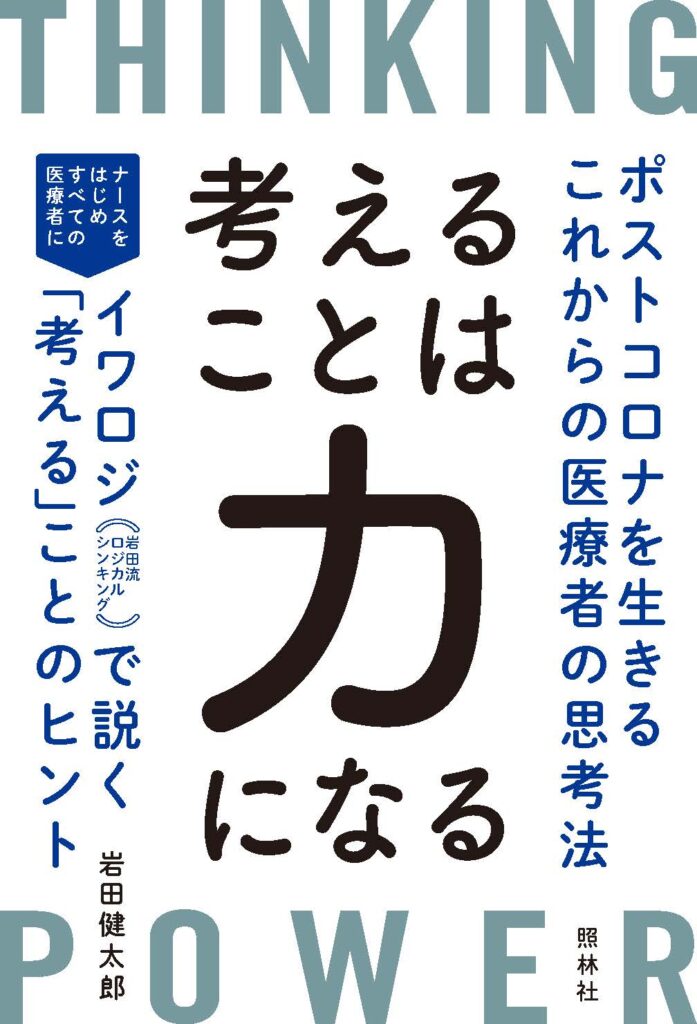岩田健太郎先生が「イワロジ(岩田流ロジカルシンキング)」で説く、「考える」ことのヒントとは。同じ目標に向かう、同じ医療者として語る、ナースへのメッセージを紹介します。
看護の世界もタコツボです
「はじめまして」
岩田健太郎と申します。神戸大学医学部附属病院に勤務する内科医で、主に感染症あたりをやっています(「あたり」というのは、いろいろなことに手を出しているからで、本書もその派生物なのです)。
日本は昔から他領域には口を出さない縦割り社会で、医療の世界は特にそうです。昔の政治学者、丸山眞男はこれを指して「タコツボ」と呼んでいました。タコツボの中は外からは見えない、タコツボの中のことはタコツボ内の人たちだけで決めていくって感じです。
当事者の皆さんがどう感じているかは存じませんが、外から見ていると看護の世界もタコツボです。「なんで医者があたしたちに口出しすんの?」とブチ切れそうになっているような気がしますが、二言目には「これは看護マターです(だから医者のあんたは口出さないで)」と言われます。被害妄想でしょうか。
確かに、「他人」に口を出すのは時にマナー違反ですし、面倒臭いことでもありますし、勇気も要ります。
けれども、考えてみてください。皆さんにとってぼくは「あかの他人」でしょうか。もちろん、捉え方によっては他人といえましょう。でも、大きなくくりで「医療者」というカテゴリーで見ればぼくらは同業者であり、医療機関という同じ組織で働いているのです。仲間同士が職場の改善のためにコミュニケーションをとるのは、むしろ当然なのではないでしょうか。
ある人と別の人を「仲間」とみなすか、「他人」とみなすか。そこには絶対的な真理や科学的な基準は存在しません。あるのはぼくらの「みなし」だけです。要するに、ぼくらが仲間同士と認め合えば仲間なのであり、「あかの他人」と考えれば、そうなるのです。
ある対象に名前をつける、その名前のつけ方は恣意的である
ある対象に名前をつける、その名前のつけ方は恣意的である。これが構造主義の考え方です。言語学者のフェルディナン・ド・ソシュールが創始者だといわれています。じつはソシュールではないという説もあります。そんなささいな問題はどっちでもよいという説もあります。
構造主義では、ある名前(フランス語ではシニフィアンといいます。フランス語でシニフィアンとかいうと、なんとなくかっこよくなってトレビアンじゃないですか?)が対象としているもの(こっちはシニフィエといいます)の組み合わせは「恣意的である」としました。
例えば、「犬」というシニフィアンはワンワン鳴いているあの動物、シニフィエとコンビになっているんです。カタカナでシニフィアンとかシニフィエとか書くとそんな難しい言葉はシランワンとなりそうですが、フランス語のsignifier(意味する)という動詞の現在分詞signifiant と過去分詞のsignifié のことなんです。英語のサイン(sign)も同じ語源からきていますね。「意味している」がシニフィアンで、「意味されてる」がシニフィエ、ってこと。トレビア~ン。
じゃ、その何が「恣意的」なのかって話ですが、そもそも「恣意的」とは何か。
恣意的、を英語ではarbitrary といいますが、「気まぐれな、勝手な、自由気ままな」みたいなことを意味しています。
「恣意的」と「意図的」(わざと)は意味が違う、とエライ先生はよくおっしゃいます。確かに、「意図的な犯罪」とは言いますが、「恣意的な犯罪」とは言えません。けれど、「恣意的」は気まぐれ、思いつき、というだけでなく「都合のよいように」という意味にも使います。このときには「わざと」という感じもでてきます。
なので、「恣意的」というシニフィアンが指す対象(シニフィエ)と、「意図的」というシニフィアンが指すシニフィエはオーバーラップしてるところもあるんちゃうかな、というのがイワタの見解。エライ先生にはチクらないでね。
ま、だんだん「ブチ切れ」モードだったのが、「わけわかんない」モードに転じつつある読者もおいでかもしれませんが、そのへんはすっ飛ばして読み進めてください。必ず結論に行きますから。ちゃんと布石は打ってますから。
繰り返しますが、構造主義ではシニフィアンと相応するシニフィエの関係は「恣意的」に決められます。例えば、「青」という日本語のシニフィアンが指す対象は、時に「緑色」の交通信号を含んじゃったりしますね。英語だと「green signal」ですから、英語圏の人はあれを「青色」とはみなしていません。青の英訳はblue ですが、青とblue では対象としているシニフィエに若干のずれがあるのです。皆さんの緑の黒髪(死語?)もけっしてアメリカ人が想定するgreen ではないわけで、まあ、そういうことなんです。少しイメージできました?
虹の色は何色か?
ぼくらの医療・医学は自然科学の領域に属します(厳密には属することが多いです)。自然科学は分類、分割が大好きです。ものごとを分割して、それに名前をつけていくんですが、ここでも分割する「科学的基準」や「真理」はなくて、構造主義的恣意性に、特に根拠なく決められているんですね。
虹の色は何色でしょう?
と聞くと、皆さん「7色」と答えます。でも、あれが「7」である科学的根拠や真理はありません。あれを8色と呼んだっていいですし、144色と呼んだって間違いではありません。線引きをどこにするかはわれわれの自由、恣意性に基づいているのです。
病気の診断もそうですね。随時血糖値200mg/dL以上を糖尿病の診断基準(の一部)にしていますが、あれが199であってはダメな科学的真理はありません。203であってはいけないという真理もありません。「ま、きりがいいところで200ってことにしとこうや」とエライ先生たちがシャンシャンで決めたんです。随時血糖値が201の人と、199の人は、糖尿病をもっている病人とそうでない人、という「別物」と扱うか。あるいは「同じような人」と扱うか。それを決めるのも恣意性のなす業です。
そういえば、ぼくは医療・医学を自然科学に属すると言いましたが、それだって恣意性のなせる業で、医療・医学の多くの領域はむしろ社会科学に属するものともいえます。ていうか、そもそも自然科学とか社会科学って分け方すら恣意的な決めつけにすぎないんです(間違いという意味ではないことに注意しましょう)。
ということで、医者であるぼくとナースであるあなたが「別の職種、あかの他人」と認識するか、「同じ医療者」と認識するかも恣意的な問題にすぎません。どちらが正しい、間違っているではないんです。
ただ、「同じ医療者」と認識したほうが、都合がよいとぼくは思います。だって、ぼくらの目標は同じ「患者さんの健康としあわせ」なのですから。立っている場所は違うかもしれませんが、目指しているところは同じです。同じであるべきです。医者とナースが別々の目標に向かって仕事していたら、患者さんに健康としあわせがやってくる可能性はきわめて低くなるでしょう。
チーム医療は単なる分業ではない
民俗学者の折口信夫はものごとを分割する性向を「別化性能」、同じようにまとめあげる性向を「類化性能」と呼びました。どちらかというと、医療者は別化性能が強く、細かく細かく分類、分割していくことを好みがちです。昨今、ますます進んでいる専門分化がその象徴です。
しかし、「まあ、医者もナースも医療者ってくくりで言えば、同じじゃね?」という類化性能も時に発動させたほうが便利なこともあります。
その先にあるのが「チーム医療」です。チーム医療は単なる分業ではありません。異なる職能の人たちが集まり、「同じ目標」に向かい、「同じ医療者」として患者さんとその周辺に尽くす姿をいいます。少なくともぼくはそうだと思っています。そのとき、「ぼくは医者、あなたはナース」みたいなタコツボ根性を丸出しにしていては、なかなか同じ方向は向けないのではないでしょうか。「ぼ~くたち~地球人♪」とおおらかな類化性能を発動させたほうが、チーム医療は成功する可能性が高いとぼくは思っています(この歌がわかる世代とチンプンカンプンな世代を分割するかどうかも、恣意性のなせる業です)。
長々とした与太話が続きました。「何が言いたいのか、いいかげんに結論を言え!」と忙しいあなたには叱られそうです。じゃ、結論を言います。要するに「ぼくの話をちょっと聞いてください」ってことです。
本書では主に「ロジカルに考えること」について話していきます。ロジカルに考えるとオトクなことがいっぱいあります。本書を読んで、大いにトクをしてください。
※この記事は『考えることは力になる』(岩田健太郎著、照林社、2021年)を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。