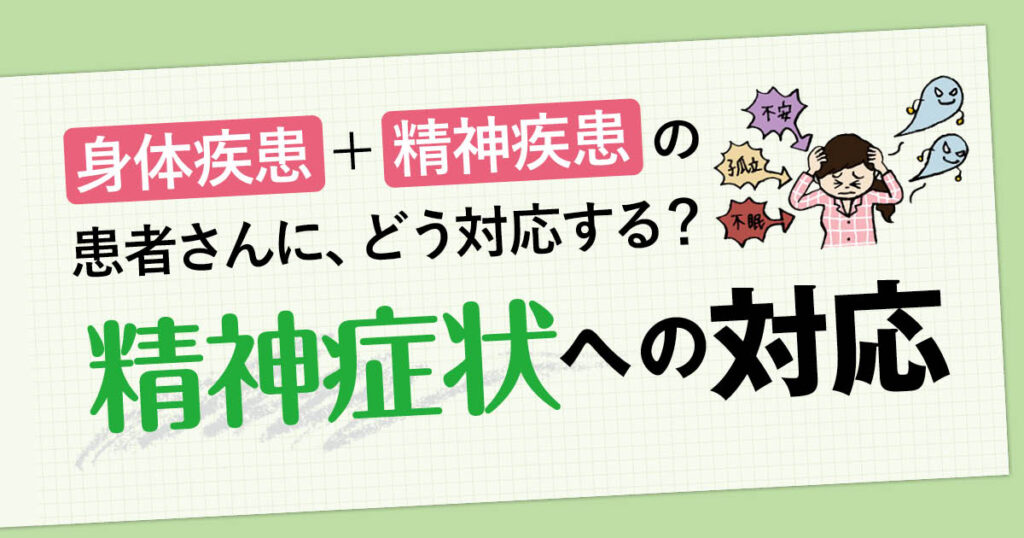一般病棟でもよく出合う精神疾患「不安症」「強迫症」について、薬剤治療の進み方、経過観察とアセスメント、対応のポイントをまとめました。ナースコールが多い場合の事例も紹介しています。
疾患の基礎知識
不安症
こころが抱えられなくなったつらいできごとの主な表現形が“不安”であり、その不安にとらわれてしまい、思考がかたくなになるものです。代表的な障害は次の通りです。
パニック症
●動悸や息苦しさがいきなりやって来て「死ぬんじゃないか?」という恐怖が頭をよぎる
●恐怖を生じた場面を恐れて、発作の再開が不安になり、活動範囲が狭まる
全般性不安症
●色んなことがわけもなく不安になり、どうしようもなくなる
社交不安症
●人前での不安や恐怖が強すぎて、社会生活に障害が出る
強迫症
強迫症は“曖昧さに耐えられない”ものです。典型的なものは「~かもしれない」という強迫観念が頭の中に侵入してきて、究極の“かもしれない運転”になっています。
「トイレのドアノブに手が触れてしまった。バイキンが付いたかもしれない…」や「ガスの元栓を最後まで締めたっけ? ちょっと中途半端だったかもしれない…」などが頭の中を占めます。白黒はっきりさせないと気が済まなくなり、その観念を打ち消すため何度も手を洗う、確認する、といった強迫行為を行います。
でも100%はないので、そのわずかな曖昧さが気になり、「かもしれない」となりまた繰り返し…になってしまいます。
薬剤治療の進み方
いずれも薬剤は抗うつ薬を使います。ベンゾジアゼピン系の抗不安薬を使うこともありますが、
依存形成や耐性が問題になります。
経過観察とアセスメントのポイント
不安の患者さんは見ていて落ち着かない感じがしますし、やはり眠れずにいることも多いです。
そのような様子を確認したら、“気になることがあるか”を聞いてみます。
さらに、不安にはうつ病も合併しやすいので、不安を見たら抑うつの確認も忘れずに。
この記事は会員限定記事です。