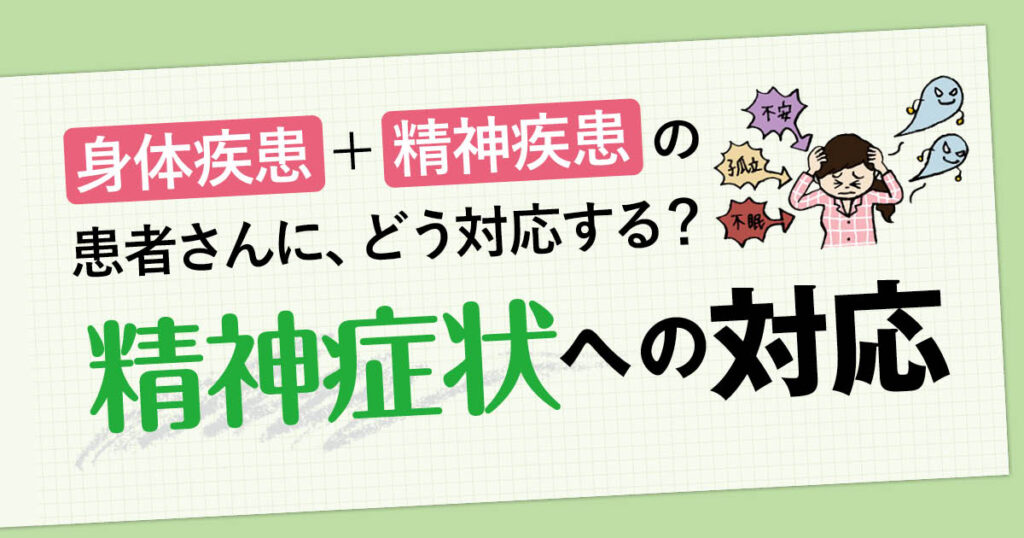一般病棟でもよく出合う精神疾患「パーソナリティ症」について、薬剤治療の進み方、経過観察とアセスメント、対応のポイントをまとめました。自傷などの行動化があった場合、看護師にできることも紹介します。
パーソナリティ症の基礎知識
パーソナリティ症はいろんな種類がありますが、共通するのは“つらい感情を感情として抱えられず、言葉でなく行動で表現してしまうこと”です。悲しみや不安を、リストカットや行きずりの性交渉や薬物依存などで表します。
こういったことを“行動化”と言いますが、そのようにしか人生の苦しみに対処できないんだなという理解が必要。
看護で困る代表格のボーダーラインパーソナリティ症(borderline personality disorder、BPD)の患者さんは、感覚が繊細な人たちで、他人の何気ない発言や行動を深読みして対人関係に難をきたします。わかってくれる人を探し求め、すがって傷ついて……の繰り返し。結果的に医療者を振り回すことになります。
ただ、パーソナリティ症という診断をつけることは、慎重にすべきであるのは言うに及びません。
薬剤治療の進み方
薬剤治療は難しいですが、抗うつ薬(特にSSRIやSNRI)やベンゾジアゼピン系は、衝動性を増すため推奨されません。気分安定薬と少量の抗精神病薬が用いられます。
経過観察とアセスメントのポイント
特にBPDの患者さんは“不安定のなかに安定している”と言われます。ちょっとしたことで感情が定まらなくなるのだという認識をもち、変化があっても、こちらが「どうしよう!」とあわてふためかないことが第一歩。
対応のポイント
後述しますが、不安定な患者さんに対しては、医療者が安定した態度で接するのが大原則です。
また、BPDの患者さんの特徴を知らないと、治療チーム内でケンカが勃発しバラバラになってしまいます。方針を統一するためにもこまめなカンファレンスが必要でしょう。
この記事は会員限定記事です。