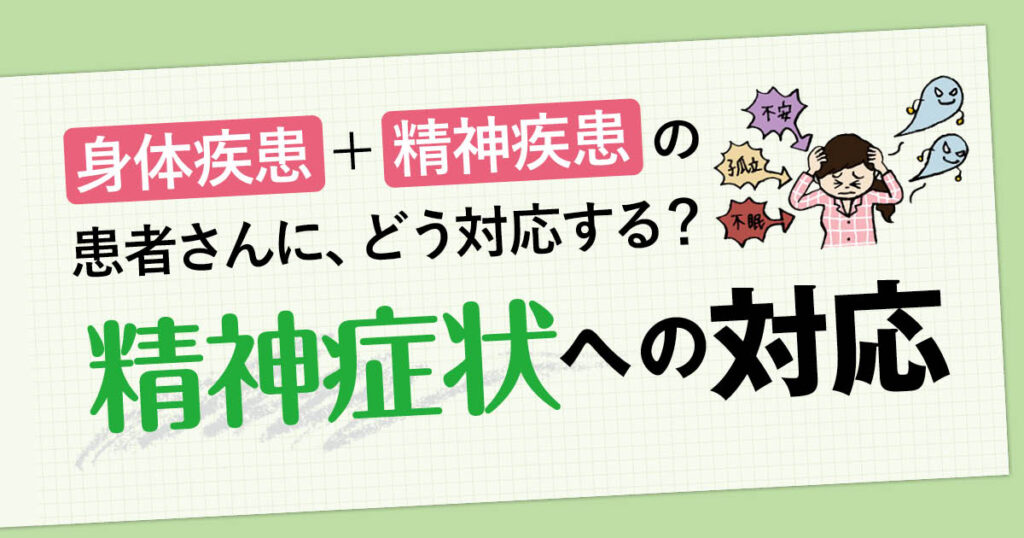一般病棟でもよく出合う精神疾患「摂食症」について、薬剤治療の進み方、経過観察とアセスメント、対応のポイントをまとめました。患者さんが食事を拒否し、栄養面の管理がうまくできない場合の対策についても紹介しています。
摂食症の基礎知識
社会生活の中で自分のやり方が通用しなくなり、谷底に突き落とされた感覚にさらされ、そのときにしがみつくのが“やせること”になる人たちがいます。食べなければ体重は減りますし、それは数字で明確に出ます。すなわち、自分のやり方が通用するのが、体重を減らすことになります。
しかし、コントロールできるはずの体重にいつの間にか縛られてしまい、摂食症に陥っていくのです。これは「神経性やせ症」と「神経性過食症」が二大巨頭。臨床で特に頭を悩ませるのは前者で、太ることへの恐怖からどんどんやせ、骨と皮だけになっても自分の身体がやせているとは確信をもって認識できなくなります(表面上は「やせてると思う」と言うことはありますが)。
神経性やせ症はさらに「摂食制限型」と「過食排出型」に分かれます。自分で吐いたり、 下剤や利尿剤を使って出したりするのは過食排出型になります。
薬剤治療の進み方
ここでは神経性やせ症を取り上げます。本症は薬剤治療も難しいですが、食欲増進という副作用を利用してオランザピン(抗精神病薬の1つ)を用いることがあります。とは言え、QT延長などに注意を。
経過観察とアセスメントのポイント
診察を行って身体に触れることから始めます。触覚で、自らのやせを感じてもらいましょう。患者さんは食べたものを無理に吐くことがあるため、吐きダコ(手を口に突っ込んで吐くため、歯の当たる手の甲に“タコ”ができる)や食後にトイレに行く(隠れて吐く)、耳下腺の腫れ、う歯、採血でのアミラーゼ上昇などが見られます。
そして、低栄養から浮腫になり、これを患者さんは「太っちゃった」と思うこともあります。
検査値も大きく乱れることが多く、明らかな意識障害でなくてもいつもより少し疎通性の悪さが見られたら、血糖値を含めて早めの採血を。また、血液検査ではPやMgやビタミンB1(欠乏はウェルニッケ脳症になります)はルーチンで測ることが少ないため、摂食症患者さんでは忘れないように。
対応のポイント
触覚を利用した診察で少しずつやせに気づいてもらいます。そこから「食べたい気持ちと食べたくない気持ちは何%ずつ?」と聞いてみて「90%食べたくない」とか「99%食べたくない」と返事をされても、10%でも 1%でも食べたい気持ちがあるのだということを評価していきます。
この記事は会員限定記事です。