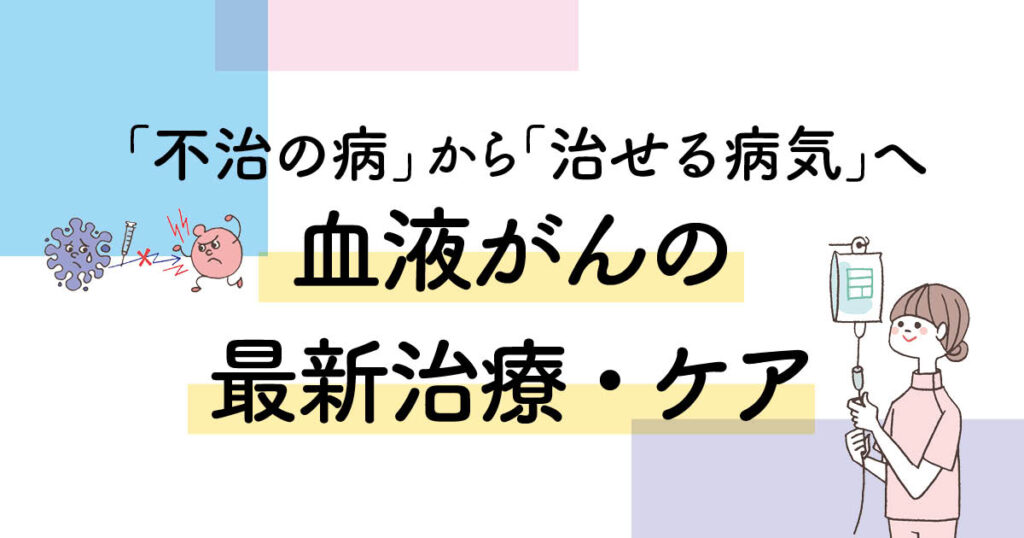白血病や悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など、血液がんの最新の治療・ケアについて解説。今回は、血液がん患者の食事を取り上げます。食思不振対応食など、病院食における栄養面や嗜好性に配慮した工夫を紹介します。
ひとくちに「病院食」といっても施設によって内容はさまざま
病院食も治療とともに日々進歩していますが、自宅や外食と異なり、病院食は「治療の一環」としての機能があることから、一定のルールが存在します。
1つは、エネルギーやタンパク質、塩分などの栄養素の組成・使用する食材の種類や量で、もう1つは、一度に大量の食事を調理するにあたっての食中毒予防のための衛生管理です。この2つのルールのうえに病院食は運営されています。
病院食には「普通食(常食や軟菜食)」と、治療の側面が強く栄養指示に対して厳格な「糖尿病食」や「減塩食」「潰瘍食」などの「治療食」があります。治療食の種類や指示内容は施設ごとで異なるため、一言で「糖尿病食」といっても施設が変わるとまったく別物となります。
また、普通食でも特殊な形態や栄養補助目的の付加食がついていることもあります。そのため、他施設から転院してきた患者さんの場合、指示の内容の確認が必要です。 血液がん治療の食事は、基礎疾患として糖尿病や高血圧、消化管の通過障害などがあれば、それに見合った治療食が適応されますが、そうでなければ「普通食」が選択されます。
食思不振時にも摂取できる「食思不振対応食」が整備されつつある
普通食は選択メニューがあるなど自由度が高いですが、治療食は普通食よりも指示栄養量などが厳格なため、普通食に対して嗜好性の面でやや劣ることがあります。
十分な経口摂取が可能な場合は問題ありませんが、悪心や味覚異常、食思不振などの症状が出現し、食事摂取量が減少しているときは、10割摂取で栄養指示を満たすように設計されている治療食では、その効果が十分に発揮できないことがあります。
近年はこういった症状や患者さんの嗜好性に配慮した内容に特化した食事を、食種としてあらかじめ用意している施設が増えてきています。
当院でも、食思不振対応食というカテゴリーで患者さんからのニーズの高い食事を食種として用意しています(表1)。
この記事は会員限定記事です。