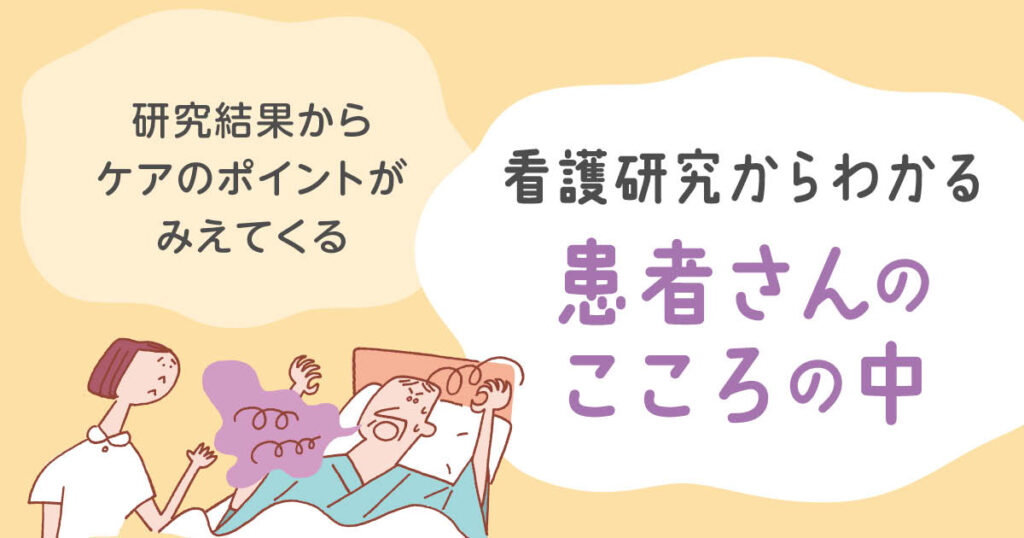患者さんの体験・心理についての「研究」を原著者に紹介してもらい、臨床で活用したいこころのケアを探ります。今回は喉頭全摘出の患者さんの心理についての研究です。
喉頭全摘出術後の失声は患者さんにどう影響する?

喉頭がんの患者さんは、喉頭全摘出術により発声機能の喪失や、呼吸路変更に伴う永久気管孔の造設、さらに嚥下障害や味覚・嗅覚障害など、さまざまな器質的・機能的変化を余儀なくされます。
また、コミュニーションの主体である「声」を失うことで対人関係が阻害され、抑うつや引きこもりなどを引き起こす場合もあり、心身ともに危機的状況にあります。
看護学領域では、一般的にボディイメージは自己概念の構成概念と位置づけられ、「人が心のなかで捉えている身体像であり、自分の身体に関係するあらゆる知覚や経験によって形成され、相互作用のなかで絶えず修正され変化してゆく観念である」と考えられています1。喉頭がんでは喉頭全摘出により、このボディイメージが大きく変化します。
そのため、喉頭全摘出患者さんが、危機的状況を克服し早期に社会復帰するためには、心理に応じた看護支援が必要です。
そこで、本研究2では、喉頭全摘出術前後および退院後を通して、喉頭全摘出後の失声や永久気管孔造設による身体的変化、機能障害を伴うボディイメージの変化における心理を明らかにしたうえで、看護支援を検討しました。
本研究は、以下の倫理的配慮のもとに実施されたものです。
●本研究は、研究倫理審査委員会の承認を受けて行っています。
●対象者に研究の主旨や目的・方法・参加/拒否/途中辞退の自由の保障・個人情報の保護などを説明し、署名による同意をいただいて実施しました。
●面接は、対象者の心理的状態や術後の経過を考慮し、つねに心身の状態や変化に注意を払いながら実施しました。
研究の方法
疑問(調べたこと)
●喉頭全摘出術前後および退院後の患者さんは、失声や身体的変化をどのように捉えている?
研究対象
●喉頭全摘出患者さん4名(50~70 歳代の男性)
研究方法
●術前後の機能障害や身体的変化に対する心理について尋ねた。「喉頭全摘出術前」「術後2週間」「退院後1か月」の計3回、半構造化面接法*を実施(術後は筆談)
●分析は、現象学的分析を参考にして実施
*【半構造化面接法】ある程度の質問項目をあらかじめ決めておくが、対話の流れに応じ、表現や順序を変更して質問する面接法。
発見1:“喉頭全摘出術前”の機能障害・変化に伴う患者心理
失声の重大さを認識しつつ、術後の生活に対して意欲的に取り組む準備を行う
患者さんは術後の永久気管孔造設に伴う身体的変化への不安を抱きながらも、失声への悲しみやあきらめのなかで、コミュニケーション手段の基本である声を失う意味の大きさを認識していました。
そして、電動式人工喉頭や筆談、カード作成などの新たなコミュニケーション手段に対する関心へと気持ちの切り替えをしていました。 このことから、患者さんは術前に不安を抱えているものの、失声後の生活に対して意欲もあることがわかりました。
“喉頭全摘出術前”のボディイメージの変化における患者さんの体験・心理
・身体的変化と、声を失うというあきらめを感じている
・術後の生活について、生きがいを探すなど、前向きに考える
失声の受容に苦悩する
●無理とは思うけれど、声が出せればいいな
●声が出ない自分を社会が受け入れてくれるのか…
●声が出ないことを理解したつもりだが、実際になってみないとわからない
失声後のコミュニケーション方法を模索する
●これから会話や電話はどうすればいいの?
●どんな対処をしていけばいいの?
● 気持ちを伝える微妙なニュアンスを表現できない
新たなコミュニケーション方法の習得に対する意欲をもつ
●少しでも声を出したい
●言葉を書いたカードを作って準備しておこう
●食道発声の練習をして、相手に自分の気持ちを伝えたい
失声後の新たな生活に対する意欲をもつ
●何か生きがいを見つけてみよう
●声が出ないハンディキャップを克服しないと…
●カラオケができない。趣味を考えないと…
(文献2より引用、一部改変)
発見2:“喉頭全摘出術後”の機能障害・変化に伴う患者心理
この記事は会員限定記事です。