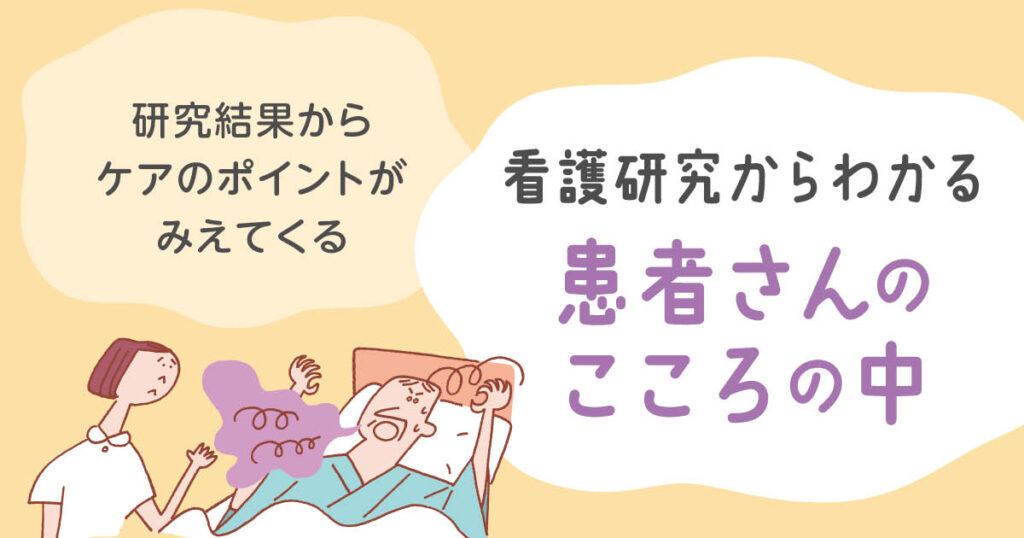患者さんの体験・心理についての「研究」を原著者に紹介してもらい、臨床で活用したいこころのケアを探ります。今回は、発症まもない頸髄損傷患者さんの心理についての研究です。
頸髄損傷患者さんは、突然の変化をどう感じている?

患者さんは、受傷直後から動けなくなることを予感している
頸髄損傷は、突然の事故などにより身体に不可逆的な障害を受ける疾患であり、多くの患者さんは一生続く障害とともに生きることを余儀なくされます。
発症まもない頸髄損傷患者さんへの看護の焦点は、生命の危機を回避するための呼吸・循環の管理、手術や点滴治療、頸部の安静による症状悪化の予防、苦痛の緩和など身体的安定を維持することに重点が置かれます。
また、身体的安定だけでなく、一瞬にして多くの身体機能を失う衝撃や不安を抱えた患者さんの気持ちを理解して支援することも重要です。
頸髄損傷の患者さんが、発症まもない苦痛の強い時期を乗り越え、安定した状態で今後の日常生活を送っていくためにも、看護師が患者さんの体験を知り、「生きようとする力」を支える看護ケアを行うことが重要です。
そこで、発症まもない頸髄損傷患者さんの体験と、「生きようとする力」を支える看護について検討しました。
本研究は以下の倫理的配慮をもとに実施されたものです。
●対象者には心身状態が安定したと判断された受傷後1か月以降に、口頭および文書で研究の目的、方法、参加の自由、辞退の自由、個人情報の保護などを説明し同意を得ました。
●日本看護協会が提示する『看護研究における倫理指針』(2005)の「看護者がケアの受け手を対象に行う際の倫理的配慮」に基づき職務の質が低下することがないように保障しました。
研究の方法
疑問(調べたこと)
●発症まもない頸髄損傷の患者さんは、どのような体験をしている?
●体験のなかでも「生きようとする力」はどのようにして引き出される、あるいは失われる?
●「生きようとする力」に看護ケアはどのように影響している?
研究対象
●不慮の事故により頸髄損傷となった男性患者さん5名。平均年齢 62.2歳(56~72歳)
●最も重症だった患者さんは第3~4頸髄の損傷で、搬送時より気管挿管・人工呼吸器を装着し、四肢は運動や知覚はなく完全麻痺の状態
●4名の患者さんは第4~7頸髄に損傷があり、上肢は自力で腕を水平に動かし顔まで手のひらを動かすことや指をわずかに曲げることができるが、下肢は完全麻痺で知覚もない状態
研究方法
●発症直後から研究者が看護師として看護ケアを行う
●患者さんの言動と提供した看護を記述してデータを得る参加観察
発見:絶望感を感じるものの、「生きようとする力」ももっている
受傷直後は生きている価値を見いだせず、「死にたい」と考える
5名の患者さんのうち4名の患者さんが、受傷後数日で「死にたい」との考えを口にしていました。笑顔はなくなり、なかには自殺を図った患者さんもいました。
日々の営みが可能となるのは身体があるからです。その身体の胸から下のすべての感覚と運動を一瞬のうちに失ってしまうことが、頸髄損傷患者さんの体験であると言えます。
人は何らかの役割を担って生きていますが、頸髄損傷患者さんは突然の四肢の麻痺によりそれらすべての役割を果たせず、それどころか自分が生きていることが、かえって家族などの大切にしてきた人に迷惑をかけることになると考えます。
どう生きていけるか見えず、生きている価値を見いだせない。自分の存在それ自体を否定したくなっても不思議ではありません。 しかし、死にたいと口にしていた4名の患者さんのうち3名が、「死なないでおこう」「生きていこう」との気持ちの変化がみられ、絶望感から立ち直りました。
「生きようとする力」を失わせる要因と引き出している要因がある
頸髄損傷の患者さんは受傷直後から自分自身の身体の変化に気づき、動けなくなることを予感します。そして、今後のことを考え絶望し、苦痛によって生きる気力をなくし、死を考えることもあります1。
しかし、多くの患者さんには、その絶望感に捕われた状況にとどまることなく、生きる力ほど前向きでなくても、死なないでおこうと考える「生きようとする力」が生まれていました。そこには、さまざまなきっかけや要因が関連していると考えられています2。
図1 発症まもない頸髄損傷患者さんの体験
この記事は会員限定記事です。