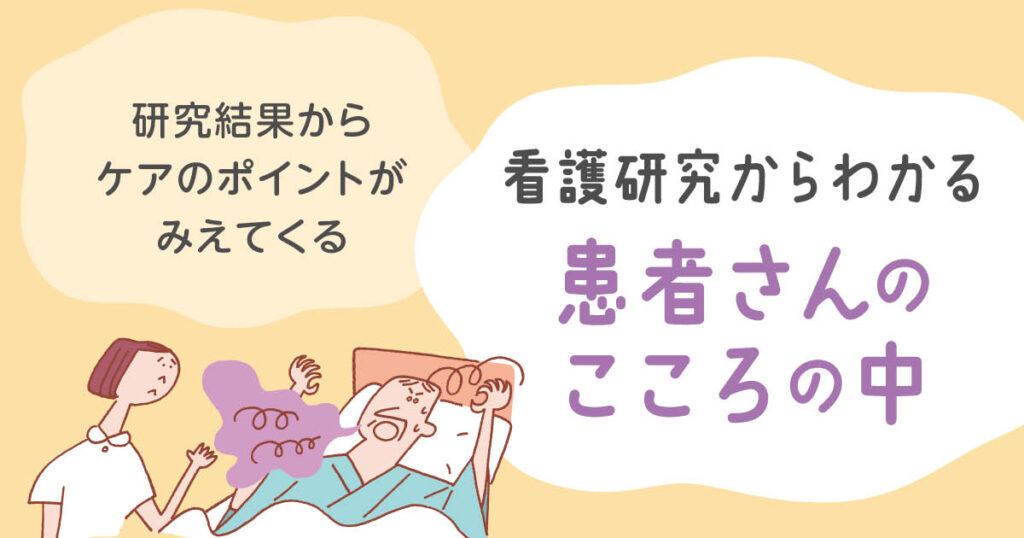発症まもない頸髄損傷患者さんは、絶望感を感じるものの、「生きようとする力」ももっていることがわかりました。その研究結果をもとに、「生きようとする力」を支援するためのケアを考えていきます。
前回の記事:発症初期の頸髄損傷患者の心理状態とは?【看護研究#29】
患者さんの「生きようとする力」を信じ、それを支える看護を行う
●看護師の観察やケアが苦痛となっている場合もあり、テクニカルスキル・内容・タイミングが最適になるように看護する
●日常生活のささいなことでも自分自身でできるように援助し、ふだんの生活に近づけるように看護する
●患者さんにとって精神的な支えとなる家族の思いが、患者さんに伝わるように支援する
発症まもない頸髄損傷患者さんの「生きようとする力」を支援するためには、「生きようとする力」に影響する要因を理解するとともに、失わせている要因である身体的苦痛を体位、ケア、薬剤などで軽減する看護が重要です(下記参照、文献1を参考に作成)。
「生きようとする力」を失わせている要因に対する看護
①障害の回復が困難であることの自覚
●発症まもない時期は、回復する可能性が少ないことは伝えなかった
●患者さんから動けるようになるか尋ねられたときは、「今は治療中なので、もう少し経過を見ましょう」と答えた
●患者さんが、回復する可能性は少ないことを理解しても、「治るかもしれない」と言われたときは「私もそうなってほしいと思う」と答えた
看護支援のポイント
●発症まもない時期で、死をも考えるときに回復が困難であることをそのまま伝えることはよい結果にならないことがある
●励ますために安易に「治りますよ」と言ってはいけない
●患者さんによって受け止め方や望みは違うので、そのつどどのように患者さんに説明するのがよいのか、チームで検討する
●患者さんの回復への希望は、単純に受容できていないと捉えるのではなく、支えとなっている希望である場合もあるので否定はしない
②身体的苦痛
●痛み・しびれについては、医師と薬剤の調整を行い、積極的に使用した
●患者さんによっては「触られるだけで痛い方」「マッサージすると軽減する方」「手浴が効果がある
方」「手袋がよい方」などさまざまで、それぞれの患者さんが効果があると言われた方法を実施した
●全身状態の観察、体位変換、清潔援助、呼吸器合併症予防の援助など、看護ケアの必要性の説明を行った
●苦痛が強いときは観察やケアを拒否されることもあったため、タイミングや方法を変更した
この記事は会員限定記事です。