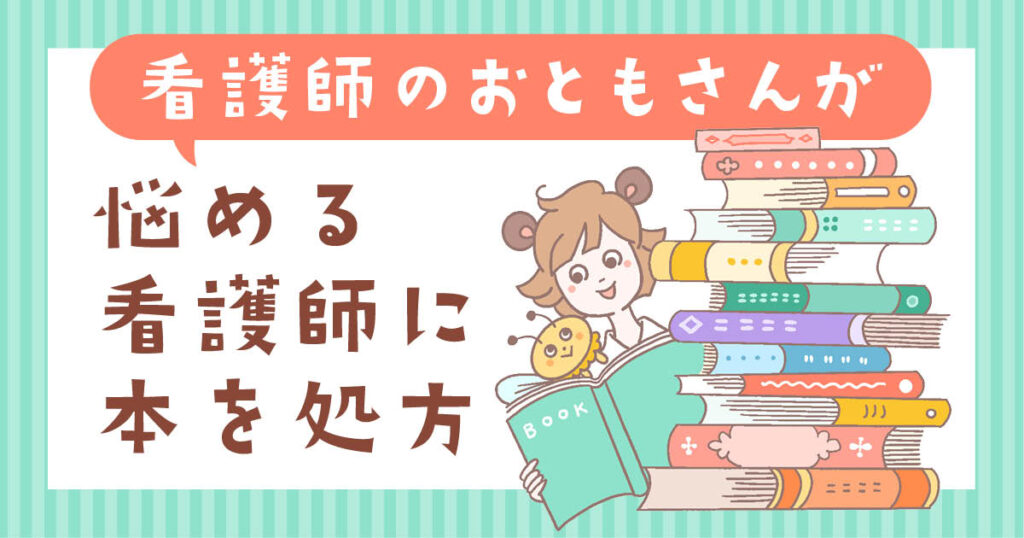本が大好きな看護師のおともさんが、“あなた”に寄り添った本を紹介するブックセラピー。「後輩への指導場面における振り返りやフィードバックを学びたい」という相談におすすめの、看護リフレクションや現場でのフィードバック方法が学べる本を紹介します。
看護師のおともかんごしのおとも
救急外来部門・シミュレーションセンターで主任を務める看護師。実家も今の家も、本だけで丸々1部屋を使ってしまっているほどの本好き。@99emergencycall
看護師6年目のYさん
後輩への指導場面での、振り返りやフィードバックの仕方を体系的に学びたいです。振り返り、フィードバックがすごくうまいなと思う先輩がいて見習いたいのですが、その先輩はかなり感覚的にやっているようで、自分が真似をしてもうまく落とし込むことができません。振り返りの技術を専門的に学びたいと思っています。
感覚的になりがちなフィードバックを体系的に学ぶには
白石 今回は振り返りやフィードバックの技術について学びたいという方からのお悩みですね。じょうずな先輩の真似をしても、なかなかうまくいかないとのこと。こういったスキルを体系的に学べる本はありますか?
看護師のおとも
じつは、振り返りやフィードバックを感覚的にやっている看護師は多いんですよね。でも、実際には体系的な方法論があるんです。フィードバックに関する本はいろいろありますが、とっつきやすいところでいくと……(本棚をガサゴソ)、まずこれをおすすめします。中原淳先生の『フィードバック入門 耳の痛いことを伝えて部下と職場を立て直す技術』。薄くてコンパクトです。
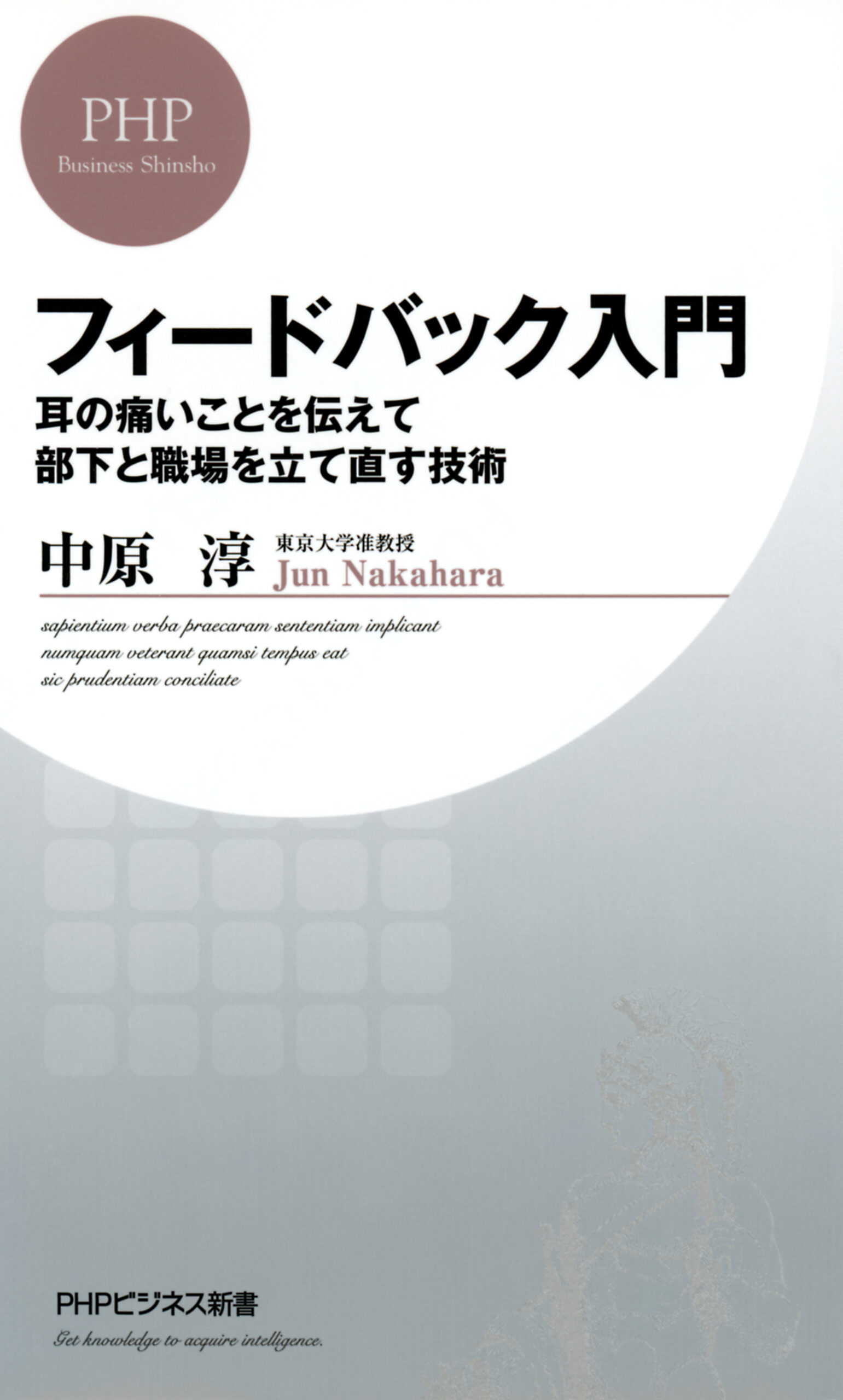
フィードバック入門 耳の痛いことを伝えて部下と職場を立て直す技術
中原淳 著
PHP研究所
新書判
1,210円(税込)
白石 新書サイズで読みやすそうですね。耳の痛いことを伝えて、というタイトルも気になります。
看護師のおとも
いわゆる振り返りをする、何かを伝えて改善しなければいけないというときのポイントがとてもわかりやすくまとまっています。2017年の本なので少し前のものですが、内容は今でも十分活用できます。よく陥りがちなのが、相手に指摘しづらい、言うべきことがあるけれど言えないという状況です。この本では、なぜそれができないのか、どうすれば部下を育てられるのかを解説しています。
白石 看護師向けではなく、一般的なビジネス書なんですね。看護現場にも応用できるんでしょうか。
看護師のおとも
そうですね、これは一般的なビジネス書なので「上司」「部下」という表現になっています。「上司」「部下」という認識がないと、そこに少し違和感を覚えるかもしれませんが、内容自体は十分に看護現場にも応用できます。
特に役立つのが、1on1での対話の方法。例えば、SBI(状況-行動-結果)という方法が紹介されています。フィードバックをするときに、単に「できなかった」「これはダメだった」と言うのではなく、相手がどういう状況だったのか、どういう背景があったのかをしっかり情報として集めて把握することが大切です。そのうえで、相手に「ここはできていなかったよ」「こうするといいよ」といったスタイルで伝えましょうという内容です。
白石 型のようなものがあるんですね。
看護師のおとも
簡単なフィードバック・振り返りの枠組みとしては、まずはちゃんと情報を集めること。次に相手との信頼関係を確保します。信頼関係のない人にいきなり「わー」と言われても「なんだこいつ」と思ってしまいますからね。
「こういうことがあった」と事実だけを通知したら、それに対して問題行動を振り返りながら、現状と実際の目標とのギャップを意識させます。そして、どうやって原因を直して、今後の計画を立てるか。最終的に期待を通知して「次もがんばってね」といった形で自己効力感を高めてコミットさせる。これが全フィードバックとしての枠組みで、最後に事後のフォローアップをする。このような流れがわかりやすく紹介されています。
白石 とても体系的でわかりやすいですね。具体的な対応例などもあるんですか。
看護師のおとも
はい、タイプ別・シチュエーション別のQ&Aもあって非常に実践的です。例えば、「指導するとすぐに激昂してしまう逆切れタイプにどう対応するか」「何を言っても黙り込んでしまうお地蔵さんタイプにどうするか」「言い訳ばかりしてくる人にどう対応するか」「根拠もなく『大丈夫です』と言うタイプにどうするか」など。これは“あるある”だろうなと感じます。どの業界も同じような悩みを抱えているんだなと思いますね。
フィードバックをさらに深く学ぶための発展版
看護師のおとも
この入門書の発展版と言っていいのか、同じく中原先生の『はじめてのリーダーのための実践!フィードバック 耳の痛いことを伝えて部下と職場を立て直す「全技術」』という本もあります。こちらは新書ではなく、入門書よりもボリュームがあります。僕は付箋がびだびだになるほど活用していますね。

はじめてのリーダーのための 実践!フィードバック
耳の痛いことを伝えて部下と職場を立て直す「全技術」
中原淳 著
PHP研究所
A5判
1,760円(税込)
白石 どのような違いがあるんですか。
看護師のおとも
入門書で書かれていた内容をより詳細に、ボリューミーにしたもので、約200ページあります。フィードバックを継続するための方法や事前準備などが詳しく書かれています。ただ、入門書とオーバーラップしている部分も多いので、入門書を読んで満足した方は必ずしも読む必要はないかもしれません。もっと知りたい、より深く掘り下げたいというときにはこちらを読むといいかなと思います。どちらか一方を持っていれば十分戦えると思います。
振り返りのステップとして重要なリフレクション
看護師のおとも
次に紹介するのは少し毛色が変わりますが、看護版として考えていただけるとわかりやすいかと思います。『看護の教育・実践にいかすリフレクション 豊かな看護を拓く鍵』です。
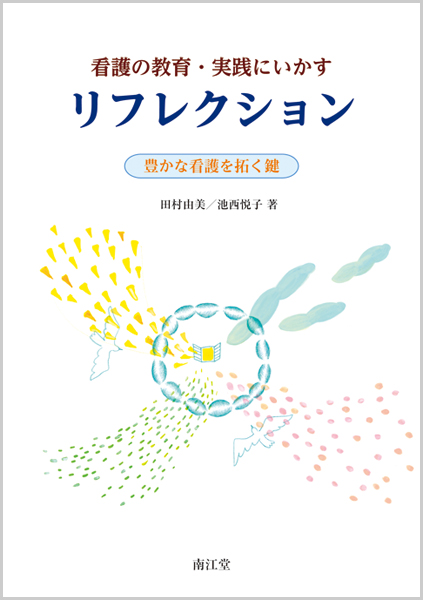
看護の教育・実践にいかすリフレクション 豊かな看護を拓く鍵
田村由美、池西悦子 著
南江堂
A5判
3,080円(税込)
白石 リフレクションですか。フィードバックとの違いがいまいちピンときていないんですよね。
看護師のおとも
振り返りをする際に、学習者にリフレクションをしてもらうことは非常に重要です。「ここがダメだったから次はここを直してほしい」と言ったとしても、本人がそれを理解して納得していなければ、効果は半減どころか反発を招いてしまうこともあります。
起きたこと、あるいは考えたことに対して、そもそもどう考えていたのか、どう判断したのか、どうなると思ったからその行動を起こしたのか、という内省を学習者にしてもらう。そういった「下準備」をしてもらうという意味でも、リフレクションは非常に重要なステップなんです。最近は、リフレクションを経験学習と合わせて推進している教育現場も多いですね。
白石 なるほど。後輩に「なぜそうしたの?」と問いかけることも大切なんですね。よく「答えをすぐに教えるのではなく、本人に考えさせることが大事」と言う人がいますよね。でもその問いかけの仕方をちゃんと理解しているのかなと。なぜそうするのかという理由や方法論を知らずに言っている可能性もあるな~と思っていたんです。
看護師のおとも
その通りです。適切な問いかけがあってはじめて、相手から答えを引き出せるんです。また、相手にある程度の知識があってこそ成り立つことでもあります。何も知識のない人に考えさせても時間の無駄なので、そういうときはきちんと答えを教えて「では次はこれを考えてみましょう」と進めた方がいいこともあります。
シミュレーション教育などでは、質問して相手が黙ってしまうときは、インストラクターがつくった場の空気が悪いとか、問いかけている質問の内容がずれている、あるいは相手に答えにくい質問をしているなど、インストラクター側に問題がある場合が多いんです。相手が答えられなかった時点で、僕の質問の仕方が悪かったと考えるようにしています。
質問の技術を磨く
白石 ここまでくると次に気になるのは、よい問いとは何か……みたいな話ですね。
看護師のおとも
そこで役立つのが『問いかけの作法』。どうやって適切に質問するかという内容の本です。よくビジネス書などでは『質問力』という表現が使われますが、ちょっとわかりにくいかなと感じています。この本では「問いかけの作法」として、相手から情報を引き出す方法が具体的に書かれています。
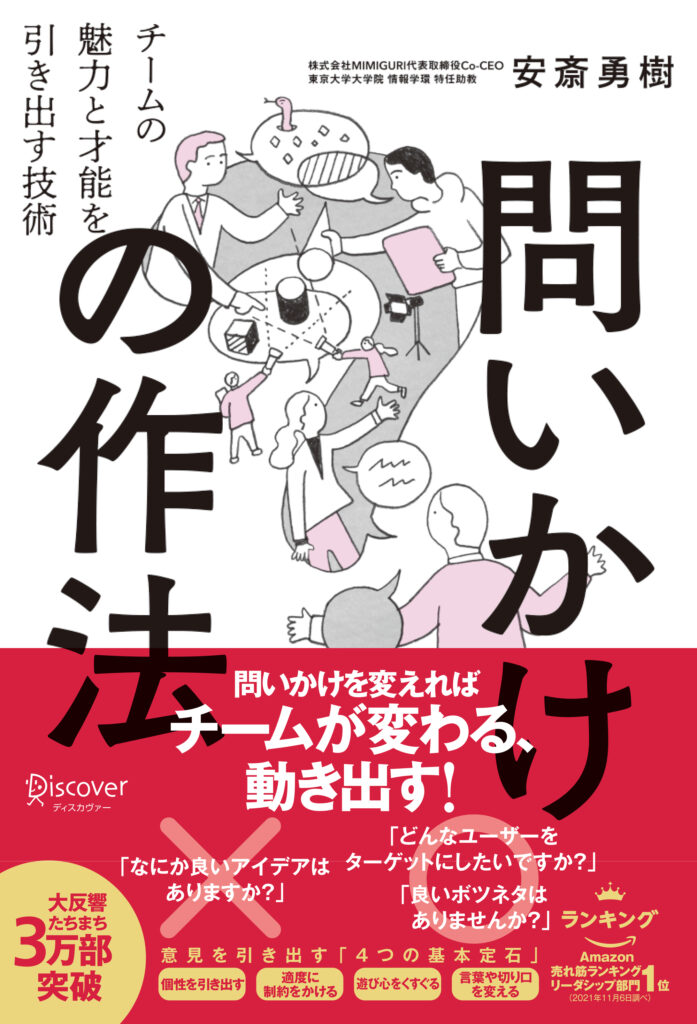
問いかけの作法
安斎勇樹 著
ディスカヴァー・トゥエンティワン
四六判
1,980円(税込)
看護師のおとも
こちらは中原先生(『フィードバック入門』の著者)の推薦の本で、チームビルディングの要素も含まれています。そもそも効果的に質問できているかという問いかけから始まり、適切な質問の仕方や相手の情報をちゃんと集めたうえで質問する方法などが紹介されています。
あともう1冊、『みんなのフィードバック大全』も挙げておきます。ビジネス書ですが、フィードバックの基本から方法論まで詳しく解説しています。多くの人はダメ出しばかりしがちですが、ポジティブなフィードバックも大切だと教えてくれる実践的な本です!
今回、看護師のおともさんが紹介してくれた本
『フィードバック入門 耳の痛いことを伝えて部下と職場を立て直す技術』
『はじめてのリーダーのための実践!フィードバック 耳の痛いことを伝えて部下と職場を立て直す「全技術」』
『看護の教育・実践にいかすリフレクション 豊かな看護を拓く鍵』
『問いかけの作法』
『みんなのフィードバック大全』(三村真宗 著、光文社、四六判、1,980円・税込)
日々、患者さんに寄り添うあなたにも、やさしく寄り添うものがあってほしい。今回紹介した本たちが、そんなあなたの心の“おとも”になれることを願っています。
看護師のおともさんに、「悩みに合う本を教えてほしい」という方を募集中。
下記URLよりご応募ください。
※掲載の有無はエキスパートナース編集部で判断し、掲載有無の結果は事前にご連絡はいたしません。
https://questant.jp/q/book_therapy_otomo
※当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。