若い女性看護師に対するセクハラ・パワハラ行為がみられる患者さん。スタッフを守るため、多職種でどのように協力していけばよいのかを考えていきます。
患者さんからハラスメントに該当する言動があったとき、とるべき行動は?
●60歳代後半、男性
●妻との2人暮らし。息子夫婦は遠方に在住。仕事は建築関係で、部長職に就いた後、定年退職。現在は非正規雇用で勤務。妻いわく、「本人はがんこな性格です。典型的な亭主関白ですね」とのこと。
●数年前より下肢の痛みやしびれがあり、腰椎脊柱管狭窄症の診断を受けた。しかし、もともと病院嫌いであり、手術を拒否。整骨院に通いながら薬物療法などを行い、様子を見ていた。
●今年に入ってからは仕事にも影響が出るようになり、家族の説得もあって手術目的にて入院。
●入院当初から「あの看護師さんは好みのタイプ、結婚しているのかな」「自分がもうちょっと若かったらアタックしていた」など、看護師の個人情報を詮索するような発言などがあった。しかし、病棟看護師は「冗談をよく言うちょっとやっかいなおじさん」と受け流していた。
●手術直後からは「痛いと言っているのに、なんで薬が使えないんだ!責任者を出せ!」「ナースコールを押したらすぐに来い!」などと、特に若い看護師に対して声を荒げる場面も見られるようになった。
●しかし、リハビリ時の男性スタッフや医師、男性看護師に対しては終始穏やかであり、「いつもありがとう」などと感謝の言葉をかける場面もあった。
●これらのことから担当医に状況報告をしたが、「もう数日で退院だから……」との返事。病棟では要注意患者として、若い女性スタッフのかかわりは極力避け、男性スタッフがメインとなってかかわることにした。
※事例は、メディッコメンバーの経験に基づいて設定した架空のものです。

喜多
きた
メディッコ代表。理学療法士、12年目。回復期リハビリテーション病院でリハビリスタッフたちをまとめつつ、病棟スタッフとの架け橋役として奮闘している。

みややん
みややん
言語聴覚士、11年目。在宅医療を提供する法人で訪問STとして勤務。平スタッフながら、いろいろな部署に顔を出して、自他の働きやすさを考えている。
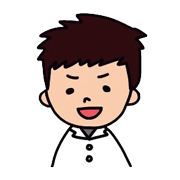
久原
くはら
臨床工学技士、13年目。総合病院にて子どもから大人、急性期から慢性期までの幅広い業務に従事している。
.jpg)
ふくっち
ふくっち
看護師、8年目。公認心理師。精神単科病院の認知症病棟に所属し、週に1日、心理室で心理師として働いている。

rosso
ロッソ
護師、16年目。脳卒中リハビリテーション看護認定看護師。急性期を経て、現在は回復期病棟の看護師。

猫兄貴
ねこあにき
薬剤師、8年目。がん基幹病院にて勤務。今年から治験部門で多職種と連携しつつ働いている。
メディッコメンバーの視点
喜多(理学療法士) こういうケースの患者さんは少なくないですよね。ただ、リハスタッフとしては「あの患者さん、対応が大変なんです!」といった言葉を看護師さんから聞くことはあっても、そういう姿を直接見ることがなくて、アドバイスや対応に悩むこともあります。看護師さんの悩みが多職種と共有されず、がまんを強要されるとつらいですよね……。
みややん(言語聴覚士) 確かに、こうしたハラスメントの悩みは共有されづらいですよね。言語聴覚士は個室の訓練室を使うことが多いのですが、似たような場面に出合ったことが何度かあります。冗談だと思って笑っていても、だんだんと内容がエスカレートしていったり、内容によっては人に相談しづらかったりします。「私の勘違いかも」と自分をごまかすことも正直、ありました。
久原(臨床工学技士) この事例は、セクハラもパワハラもある「ダブルパンチ」な状況なんですね。僕がたまたま遭遇したことがないだけか、これは架空の事例だとわかっていても、実際に似たようなことがあるとは正直驚きです。顔を合わせることが多いぶん、エスカレートしていくのか……。これが看護師の職場環境として「よくある事例」だとしたら、早急に職場全体として対策をする必要があると感じます。
ふくっち(看護師) 女性の看護師さんから、このような話は何度も聞いたことがありますし、実際にそのような態度の患者さんを見たり、かかわったりしたことがあります。
基本的には男性看護師が対応するようにしますが、例えば夜勤帯では看護師が少数になって、男性看護師が対応できない場合もありますからね……。女性看護師の不安やストレスは大きいと思います。
rosso(看護師) 特に若い女性看護師は、ターゲットになりやすい傾向にあると思います。
しかし、この患者さんの場合で考えてみると、重い腰をあげてようやく手術を受けたにもかかわらず、想像以上の痛みや入院生活だったのかもしれません。だからといってセクハラ・パワハラが許されるわけではないと思いますけどね。患者さんのバックグラウンド(生活背景)を理解しつつ、ハラスメントをスタッフ間で情報共有・対策できるようにしなければならない事例ですね。
猫兄貴(薬剤師) 医療者側は「患者さんも入院生活でいろいろとストレスがたまってそうだから……」とやさしく様子を見ることもありますが、度を超えてくるとそれでは済まない話になってくるから困りますよね。
病棟にいたころは、薬に関するクレームだったら薬剤師の自分が対応したり、配薬のタイミングで看護師さんと一緒に訪室したりしていました。
ただ、自分もいつも病棟にいられるわけではないですし、そうした患者さんの担当を常に男性看護師にするのも限度があるので難しいですよね。
理学療法士の視点からの解決策
喜多(理学療法士) 患者さんにかかわるスタッフみんなが状況を把握して、対応を検討するとよいですよね。
リハスタッフは患者さんの生活背景や趣味などを深く情報収集するので、ちょっとした怒りポイントや喜びポイントを知っているものです。それをほかのスタッフと共有することで対策につながるかもしれません。
例えば、「時間に厳格だから検査や入浴の時間はしっかり伝える」「マナーに厳しいから部屋のカーテンを開けるタイミングに気をつける」といった対応が功を奏することがあります。
また、看護師さんだけにナースコール対応のしわ寄せがいかないように、リハスタッフから患者さんに声をかけてもらうのもよいですね。例えば、「すぐにナースコールに対応できないこともあります。体がつらいときがあるのはわかりますが、その点はご了承いただけますと幸いです」と伝えたり、リハビリのついでに困りごとを聞いたりすると、適度にガス抜きができて理解してもらえることがあります。
担当リハスタッフからの声かけでうまくいかないときには、リハスタッフの上司や先輩から伝えてもらう、といった工夫も必要です。
言語聴覚士の視点からの解決策
みややん(言語聴覚士) そうですよね。看護師とリハスタッフで同じ患者さんを見ていても、見えてくる側面って異なることがありますよね。
私は、年齢が1つのポイントになると思うんです。例えば、このケースのように定年前後の世代であれば、部長職まで勤め上げたということを踏まえて、「これまでは仕事に打ち込んでいたけれど、今後のことに不安を感じている」「精神的に不安定になっている」ということも考えられます。病状や退院への目標以外にも、性格や年齢、価値観などを含めた生活背景をしっかりと情報共有する必要がありますね。「ちょっと怒りっぽいところがあるって家族さんが言ってたよ」なんていう情報は案外大切ですから、看護師さんには積極的に伝えるようにしています。
もちろん、「リハビリ中の様子はどうですか?」「夜勤帯ではじつは……」といった会話が、看護師とリハスタッフ間でもあたりまえにできれば、つらさを吐き出す機会になって心が救われることにもなりますよね。
久原(臨床工学技士) 患者さんの性格や生活背景を情報共有し、患者さんに合ったスタッフや対応をすることは必要ですよね。
また、「なぜハラスメントを起こすのか?」というところで、入院や手術の不安からくるストレスが原因の可能性もあるかもしれないので、そこを踏まえた対策を講じることも必要かもしれません。
臨床工学技士としてよいアドバイスかどうかわかりませんが、物(医療機器)のせいにしてしまう手もありじゃないでしょうか。「機械の設定に時間がかかります。精密機械(輸液ポンプ)で正しく操作しないと◯◯さんのためにならないんです」というふうに怒りの対象を人から物にそらすのも、一時的なしのぎにはなるかもしれません。
看護師の視点からの解決策①
ふくっち(看護師) 久原さんの「物(医療機器)のせいにしてしまう」という発想はなかったので、1つの手段としてよいですね。
また、このようなタイプの男性には、権威性が功を奏する場合もあるのではないかと思います。やはり医師や看護師長などから話をしてもらうことも大切ではないでしょうか。医師や看護師長などの権威ある人に話をされると、一時的に改善する場合があります。
ただ、権威性があるからこそ、正論を話しても患者さんは「怒られた」と解釈してしまい、その不満や屈辱感が認知の歪みとなり、さらに態度を悪くする場合もあります。つまり「一時的な改善」でしかない場合、逆に「怒られた」と思わせることで状況を悪くすることもあるということです。
なので、患者さんのパーソナリティやコミュニケーションの方法をスタッフ間で話し合っておく必要がありますね。臨床の場では、情報が多ければ多いほど、患者さんの個別性が見えてくると思います。
基本的には、女性看護師1人で対応せず、リハビリスタッフや看護補助者の方にも助けてもらうことで複数人でかかわりましょう。そして男性看護師は、同じ職種として女性看護師の不安をしっかり聞いて共感するのも大事だと思います。同じ職種だからこそ思いを理解し、共有できるのですから。
薬剤師の視点からの解決策
猫兄貴(薬剤師) 患者さんが、何に対してストレスを感じているか、また、何を望んでいてどういうギャップにストレスを感じているかを捉える必要がありますよね。ただ、それらすべてを医療スタッフが解決できるわけではないですし、もともと大した意味がない、生来の気質だったりする場合もあるので、根本的に解決できることはそう多くないと思います。
やはり、職員を守る責務がある管理職が明確に対応することは必須でしょう。ほかの方も言っているように、個人の話で終わらずに職場の問題として取り組めるように、病棟全体で共有していくことが必要です。
また、もし院内で緩和ケアチームが活動していれば相談してみてもいいかもしれません。緩和ケアチームは、がんの痛みがないと相談してはいけない、みたいな風潮があるかもしれませんが、決してそんなことはありません(もちろん院内のチームのキャパにもよりますが……)。
精神科の医師がチームに入っていることが多いので、そうした対応も得意なはずです。“全人的な苦痛”に対応するのが緩和ケアチームの役割ですから、患者さんがなにか強い不満を抱えていそうであれば、強い味方になってくれるかもしれません。
看護師の視点からの解決策②
rosso(看護師) 患者さんのバックグラウンドの聴取・共有はマストだと思います。入手した情報は職種によって異なるため、お互いに「これは知っているだろう」と思わずに共有することが大切です。特に看護師は24時間、患者さんを看ているため、夜間の様子やハラスメント状況を看護記録に残すことが一番の情報共有だと思います。
また自分がハラスメントを受けてしまった場合は、「仕方がない」「私の対応がいけなかった」と思わずに、上司に報告する勇気をもつことが再発予防になることを以前経験しました。今回は女性看護師が対象でしたが、ハラスメントはたくさんのケースが存在するため、いつ・誰が対象になるかわかりません。日頃からそのことを意識しておく必要があると思いました。
*
看護師は上司や同僚以外にもさまざまな職種や患者さん、家族とかかわるため、ハラスメントを受けやすい職種です。また、起きたトラブルを看護師個人の問題にされることもあり、ハラスメントとしてとりあげにくい実情もあります。
今回、「それぞれの職種が解決に向けてできること」でも出てきたように、看護師だけではなく、組織として対策を考えていくことが求められるでしょう。ハラスメントを未然に防ぎ、実際に起こってしまった場合にも早期に対応ができるよう、体制を整える必要があると思います。
今回の事例のまとめ
●自分1人で抱え込まないようにする。また、看護師だけでなく他職種にヘルプを出すことも方法の1つ。
●日ごろから「ハラスメントかも?」と思ったことは、看護記録に残して情報共有する。
●患者さんの置かれている状況や、これまでの背景も情報収集・共有する。
●関係部署全体で情報を共有し、医療安全・緩和ケアなどの院内チームの協力をあおいで対策をとる。
この記事は『エキスパートナース』2020年12月号連載を再構成したものです。
当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。
以上の解決方法・対処例は、ケースをもとにメディッコメンバーが話し合った一例です。実際の現場では、主治医の指示のもと、それぞれの職種とこまめに連携をとり、進めていってください。






