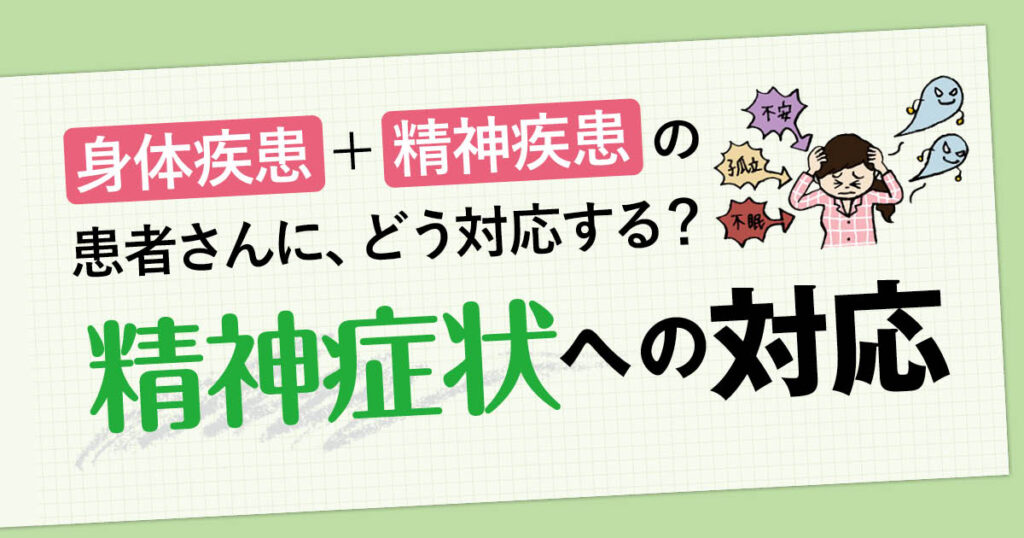精神疾患の患者さんに暴力が現れるのはどのようなとき?暴力が生まれることを防ぐポイントや、対応方法を紹介します。
暴力の原因は“ゆとり”のなさ
暴力は“ゆとりのなさ”から生じてきます。背景として、精神疾患であれば“恐怖感”が多いかと思います。それは病状の不安定さが影響しているため、落ち着かなさがあったり、不眠がずっと続いていたり
口調がきつくなってきたりという、ゆとりのなさを確認しておきましょう。
恐怖以外では、患者さんと医療者との気持ちのすれ違いから暴力が生まれることが多いですね。
こちらの感情を入れず、“なぞって繰り返す”が基本
患者さんが言葉を荒立てて暴力の恐れがあるとき、実際の場面では、すぐに謝ったり、相手の言いぶんをムキになって訂正したりしないこと。それらをするとますます攻撃を強めてしまいます。
こういう事態を防ぐために最低限覚えておきたいポイントは、【第2回】でも示した“なぞって繰り返す”です。こちらの感情が変に入らず、相手に曲解されない優れた方法なので、これだけは覚えておきましょう。
病院としての姿勢を明確にし、複数人で対応を
そして、必ず逃げ道を確保し、複数人で対応します。数で優位に立つと自分の身を守れますし、相手も冷静になってくれることがあります。1人で対応すると危険で証拠も残りにくいため、複数対応とし
ましょう。場所は防犯カメラのあるところが適切です。
ただし、暴力への対応は職員1人がすることではなく、必ず病院という組織がなすべきもの。対策部門を設立して病院としての一貫した姿勢をつくりましょう。そして、警備員や警察との連携を密にしておくこと。職員1人を危険に晒すわけにはいきません。
この記事は会員限定記事です。