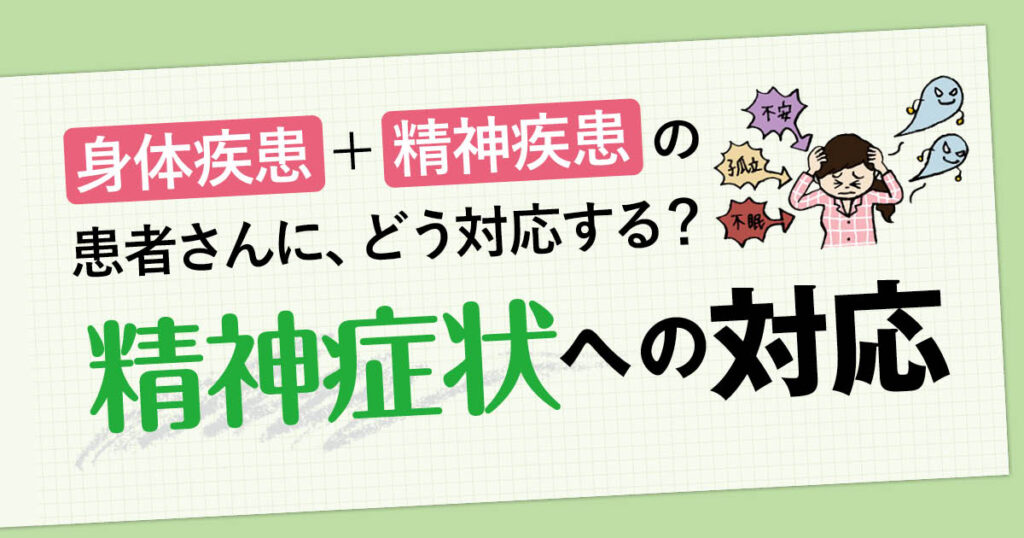不安、抑うつ、焦燥感 ─ 。患者さんに現れる精神症状は多種多様ですが、どれも“つらさからこころを守る反応”であることに変わりはありません。基本として知っておきたい、精神症状との向き合い方を解説する全14回の連載です。
【第1回】治療の場での精神症状へのかかわり方
〈目次〉
●精神症状とは“つらさからこころを守る反応”
●“日常生活の感情”と“精神症状”の境目は?
【第2回】看護師ができる精神症状への対応
〈目次〉
対応1 安易な共感はせず、“認証する”
・基本は患者さんの言葉を“なぞって繰り返す”
・“認証”とは、論理的に患者さんの苦しみを理解すること
対応2 “侵襲的でない空気”をつくる
対応3 患者さんを“あせらせず”、“ゆとり”をもてるようにする
・あせりの誘因①:不安
・あせりの誘因②:不眠
・あせりの誘因③:孤立
【第3回】身体疾患による精神症状を除外する
〈目次〉
●身体疾患を疑う12のポイント
●精神症状を引き起こす身体疾患の例
【第4回】うつ病/双極症の基礎知識と対応のポイント
〈目次〉
●疾患の基礎知識
・うつ病
・躁・軽躁
・薬剤治療の進み方
・経過観察とアセスメントのポイント
・対応のポイント
●自殺の可能性があるとき、ナースに何ができる?
・TALK の原則”に沿って話を聞こう
・徹底した聞き役になることで、患者さんのつらさを抱える
【第5回】統合失調症の基礎知識と対応のポイント
〈目次〉
●統合失調症の基礎知識
・薬剤治療の進み方
・経過観察とアセスメントのポイント
・対応のポイント
●幻聴の訴えがあるときは、“いつもの対応”を尋ねてみる
●治療拒否や攻撃的態度があるときは、不安をやわらげる言葉を
●患者さんが強い興奮状態にあるときは、複数人で対応する
【第6回】不安症、強迫症の基礎知識と対応のポイント
〈目次〉
●疾患の基礎知識
・不安症
・強迫症
・薬剤治療の進み方
・経過観察とアセスメントのポイント
・対応のポイント
●頻回のナースコールがあるときは、ゆとりをもつ姿勢を大切に
・事例:比喩を用いて原因を探る
【第7回】身体症状症の基礎知識と対応のポイント
〈目次〉
●身体症状症の基礎知識
・薬剤治療の進み方
・経過観察とアセスメントのポイント
・対応のポイント
●器質的な原因がみつからない身体症状を訴えるときは、日常生活へと視点をずらす
・事例:患者さんの視点を“あせり”から“ゆとり”にずらす質問法
【第8回】パーソナリティ症の基礎知識と対応のポイント
〈目次〉
●パーソナリティ症の基礎知識
・薬剤治療の進み方
・経過観察とアセスメントのポイント
・対応のポイント
●自傷などの行動化があったとき、ナースに何ができる?
・行動化のプラス面も認めたうえでかかわる
・ナースにできることは“感情”の認証
●極端に好意的な態度や攻撃的な態度をとられたときは、医療者として態度を一定に保つ
【第9回】摂食症の基礎知識と対応のポイント
〈目次〉
●摂食症の基礎知識
・薬剤治療の進み方
・経過観察とアセスメントのポイント
・対応のポイント
●食事を拒否し、栄養面の管理がうまくできないとき、ナースに何ができる?
・診察を通じて、自身の「やせ」に納得してもらうことから始める
【第10回】患者さんの暴力にはどう対応する?
〈目次〉
●暴力の原因は“ゆとり”のなさ
●こちらの感情を入れず、“なぞって繰り返す”が基本
●病院としての姿勢を明確にし、複数人で対応を
【第11回】抗精神病薬の作用と注意したい副作用
【第12回】抗うつ薬の作用と注意したい副作用
〈目次〉
●抗うつ薬は頭の中の停滞をかき混ぜて浮上させるイメージ
●主な新規抗うつ薬
・SSRI
・SNRI
・NaSSA
・S-RIM
●気をつけたい副作用
【第13回】ベンゾジアゼピン系(抗不安薬/催眠鎮静薬)の基礎知識
〈目次〉
●ベンゾジアゼピン系はお酒のようなもの
・半減期、筋弛緩作用、鎮静作用で薬剤の特徴が出てくる
●抗不安薬か催眠鎮静(睡眠薬)、用途によって使い分ける
・抗不安薬として用いる主なベンゾジアゼピン系
・催眠鎮静(睡眠薬)として用いる主なベンゾジアゼピン系
【最終回】身体疾患治療薬との飲み合わせの注意点
〈目次〉
●飲み合わせに影響を与える「CYP」とは?
●抗精神病薬との飲み合わせの注意点
●新規抗うつ薬との飲み合わせの注意点
●ベンゾジアゼピン系との飲み合わせの注意点