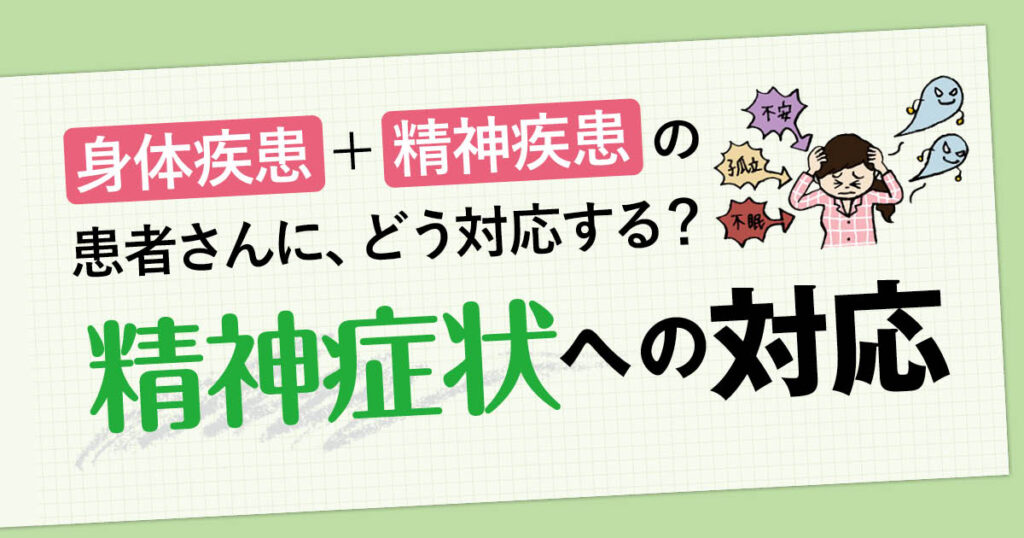一般病棟でもよく出合う精神疾患「統合失調症」について、薬剤治療の進み方、経過観察とアセスメント、対応のポイントをまとめました。実際に現場で、どのような言葉かけで生かしていけばいいのかも紹介します。
統合失調症の基礎知識
統合失調症の患者さんは小さな変化やノイズを敏感に察知する能力をもっていますが、それに揺さぶられてつらさにもつながります。“先を案じる”ことに縛られて、湧き上がる不安感に圧倒されます。
それを抱えられなくなると“外からやってくるもの”として対処しようとし、その現れが幻聴であり被害妄想です(周りに“わかられている”感覚)。
ほかには、自分の考えが他人に筒抜けになると感じる“思考伝播”、身体の感覚が異常なものにさせられると感じる“身体への影響体験”(体中に配線を入れられている、など)、意欲が出なくて活動が落ちる“自発性の低下”、感情の色合いが単調になる“感情の平坦化”などの症状があります。
薬剤治療の進み方
抗精神病薬を用いますが、改善しづらいことがあり幻聴や妄想に苦しむ患者さんも多いです。
副作用は錐体外路症状や高プロラクチン血症、抗コリン作用による口渇や消化管運動抑制など。発熱や筋強剛や意識障害をきたす“悪性症候群”は致死的になることも。
経過観察とアセスメントのポイント
幻覚や妄想が目立たずに自発性の低下が主体の患者さんもいます。患者さんが動かないと何とか動かしたくなりますが、外の世界を怖く感じていることも多いため、無理強いはしないほうがよいかもしれません。また、不眠が続くと容易に症状が悪化します。
注意点は、幻覚や妄想があっても統合失調症とは限らないこと。身体疾患(例えば脳炎やステロイドの副作用)でも起こりますし、どの精神疾患も重症化すると幻覚妄想的な部分が強くなってきます。
対応のポイント
話すときの距離は少しだけ遠めにとることを意識します。関係性ができていないときに距離が近いと、統合失調症の患者さんは怖さを感じることがあります。
幻聴や妄想に対しては後述しますが、「不思議だねぇ」というくらいの返しで、でも特に被害的な幻聴や妄想は、その奥底に不安や不信があるかもしれないというイメージをもっておきましょう。それだけでも患者さんに伝わる空気は違ってくるように感じます。
接するときは、あまり眼を見ないことが大事。じっと眼を見ることは、統合失調症の患者さんにとって侵襲的になることがあります。
この記事は会員限定記事です。