看護師としての仕事にも役立つうえ、自分のためにも知っておきたい精神医学の話をお届けする連載です。
【第1回】病名は大事なのか?看護は「病名」で計画されるものなのか?
〈目次〉
●病名は、患者さんの「道しるべ」となるもの
●発達には濃淡があることを理解しよう
●基準を満たすかどうかではなく、その人に合った生活のヒントを
●診断・病名は治療薬の決定のために大切なもの
●看護は「病名」だけで計画されるものではないはず
【第2回】産業医とは?
〈目次〉
●50人以上の従業員を雇う企業は、産業医を選任しなければならない
●産業医は従業員の就業のために、さまざまなサポートをしている
【第3回】産業保健分野の看護師に求められること
〈目次〉
●今、産業保健の分野で仕事をしたい看護師が増えている
●産業看護職の経験を積むには、都心部以外の企業がねらい目
●産業看護職にとって重要なスキルは、コミュニケーションをとる力
●産業看護職にとってメンタルヘルス対応は当たり前のスキルに
【第4回】病院での産業医の利用のしかた
〈目次〉
●産業医はどんな疾患の相談も受けなければいけない
●産業医には守秘義務があるので相談内容は外に漏れない
●どんなときに産業医に面接に行けばいい?
●メンタル不調を感じたときの一般的な対応の例
【第5回】部下がメンタル不調になったときの対応
〈目次〉
●大前提として、職場で不調を受け入れる
●どのような就業配慮が必要か具体的に考えよう
●配慮の実現が難しくてもねぎらいの声かけをしよう
●就業配慮が業務実態に合わない場合は産業医に伝えよう
●師長クラスになると家庭訪問することもあり
【第6回】発達障害は合併する
〈目次〉
●「神経発達症」という新たな名前をつけられた「発達障害」
●発達障害にはさまざまな種類があり、それぞれ合併することを念頭に置こう
●発達障害を理解するために大切な「スペクトラム」という概念
●発達障害とのかかわりは、疾患とその人の生活を合わせて考える
【第7回】社会に出て明らかになる大人の発達障害
〈目次〉
●成長に伴う「ハードル現象」によって明らかになる大人の発達障害
●社会に出てうまくいかない理由に、仕事が合っていないこともある

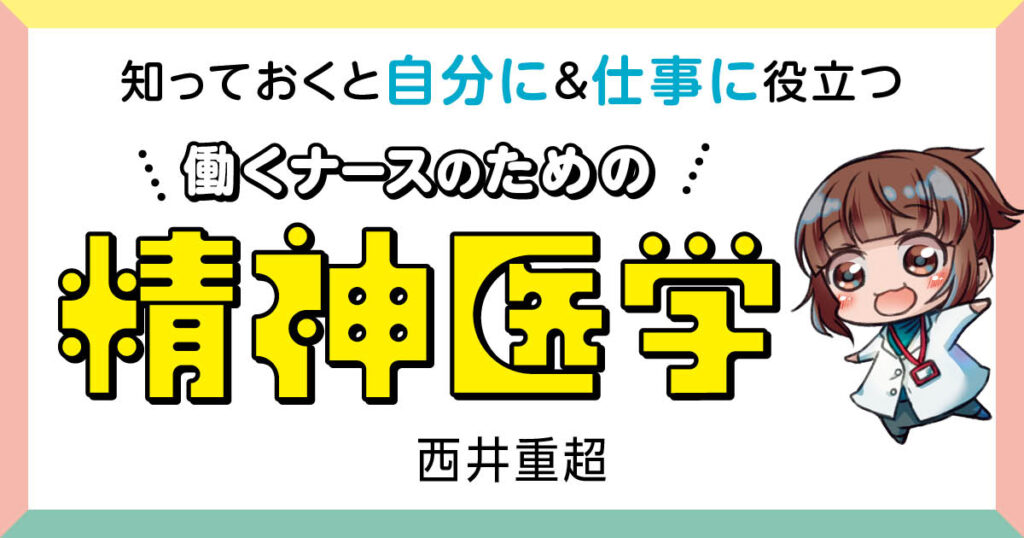
20231123.jpg)


